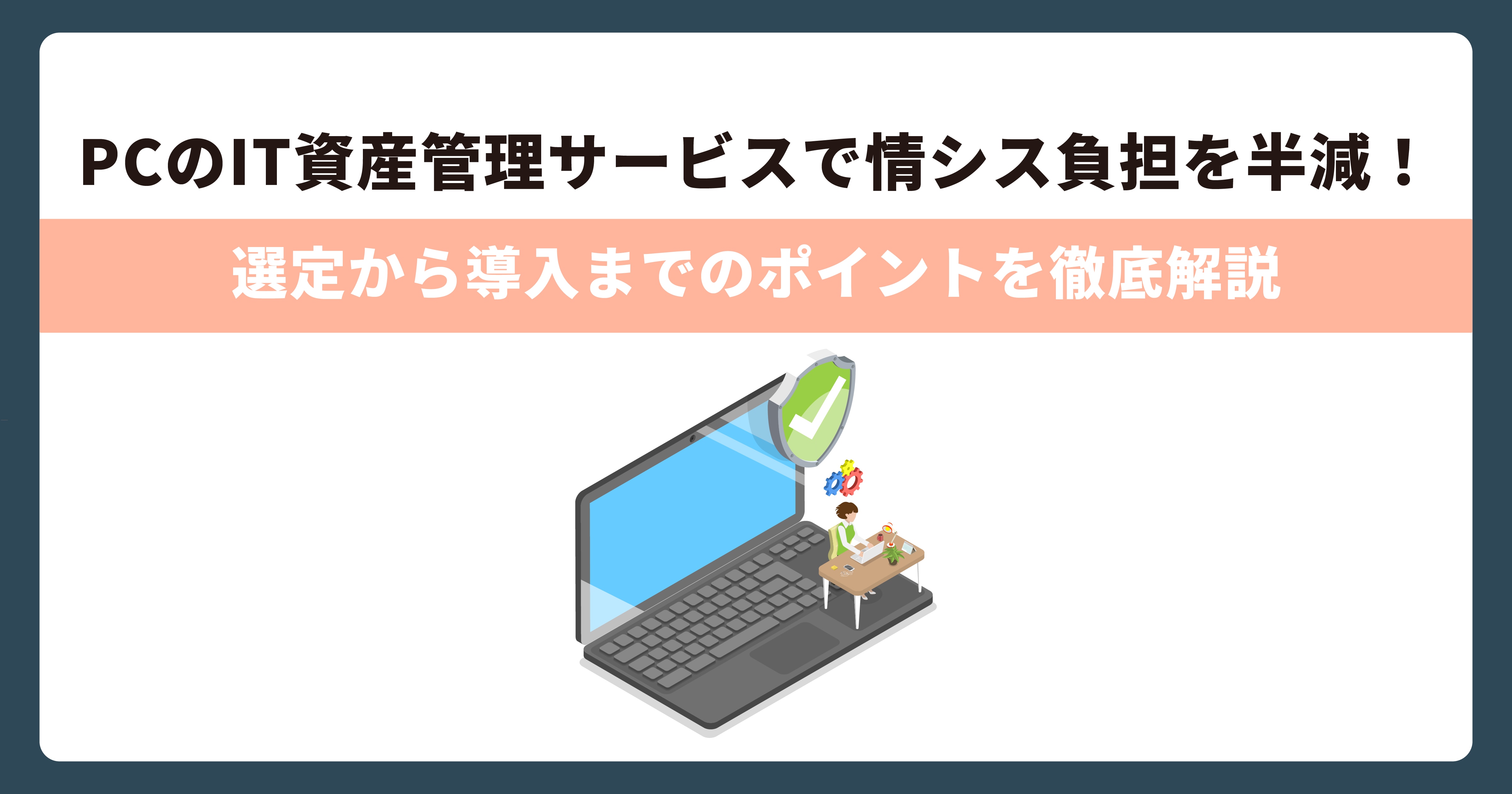
PCのIT資産管理サービスで情シス負担を半減!IT資産管理ツールとの違いや選定から導入までのポイントを徹底解説
近年、社内のPCやモバイル端末、さらにはクラウドサービス(SaaS)の利用が急増し、Excelによる手作業の資産管理は限界に近づいています。IT資産の管理が煩雑になる一方で、情報システム部門(情シス)は限られた人員で対応しなければならず、大きな負担となっています。こうした課題を解決し情シスの作業負荷を半減してくれるのがIT資産管理サービスです。インベントリ収集やライセンス管理を自動化することで棚卸し作業を大幅に効率化でき、セキュリティ対策やコスト最適化も同時に実現します。
本記事では、IT資産管理サービスとは何か、その定義や対象範囲から、従来のIT資産管理ツールとの違い、最新トレンド、クラウド・オンプレミス・BPO各方式の比較、導入前に押さえるべきポイント、料金モデルの違い、さらに具体的な導入事例まで網羅的に解説します。自社に最適なサービスを選定し、導入効果を最大化するためのヒントとしてぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.IT資産管理サービスとは?
- 2.IT資産管理の最新トレンド
- 3.クラウド・オンプレミス・BPOを8指標で比較
- 4.IT資産管理サービスの導入前に押さえる7つのチェックポイント
- 4.1.管理対象の規模と範囲
- 4.2.必須機能と優先順位
- 4.3.導入方式と環境適合性
- 4.4.既存システムとの連携可否
- 4.5.セキュリティ/ガバナンス要件
- 4.6.コスト試算と ROI
- 4.7.ベンダーのサポート体制と将来性
- 5.月額・買い切り・無料版の違い
- 5.1.月額課金と買い切り型の違いと損益分岐点
- 5.2.無料版・トライアル版の実力と注意点
- 6.IT資産管理サービス導入の成功事例
- 7.IT資産管理サービスで最大効果を得るために
IT資産管理サービスとは?
IT資産管理の定義と対象資産
IT資産管理とは、企業や組織が保有・利用するあらゆるIT資産(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク機器、クラウドサービスなど)を把握し、ライフサイクル全体で適切に管理することを指します。単なる資産一覧の作成だけでなく、導入から運用、保守、廃棄に至るまで一元管理し、コストの削減やセキュリティリスクの軽減、ライセンスコンプライアンスの確保を目的とします。
管理対象にはPCやサーバー、モバイル端末、周辺機器から、インストールされているソフトウェアやそのライセンス、さらには契約中のクラウドサービスやSaaSアカウントまで含まれます。昨今はリモートワークの普及により社外利用のデバイスやクラウド資産も増え、これらを含めた包括的な管理が求められています。
サービスとツールの違い【ソフトウェア資産管理との関係】
IT資産管理サービスとIT資産管理ツールはしばしば混同されますが、実際には異なります。一般に「ツール」はIT資産管理のためのソフトウェア製品やシステムそのものを指し、自社導入のオンプレミス型ソフトやクラウド提供のSaaS型ツールなどが該当します。
一方「サービス」は単にツールを提供するだけでなく、運用代行やサポートまで含めて提供される形態を指すことがあります。例えば専門業者による資産管理BPO(アウトソーシング)はサービスの一種で、ツール運用を外部に任せられる選択肢と言えます。
また、多くのサービスはソフトウェア資産管理(SAM)の機能も備えており、ライセンス数とインストール状況を照合して無駄や違反を防ぐSAM機能も重要です。IT資産管理サービスを選ぶ際には、ハード資産だけでなくソフトウェア資産管理までカバーしているかを確認すると良いでしょう。
IT資産管理の最新トレンド
クラウドが台頭、一方でオンプレも選ばれ続ける
IT資産管理ツールの提供形態は、大きくオンプレミス型(自社サーバーに構築)とクラウド型(サービス事業者の環境を利用)の2種類があります。近年はクラウド型が台頭しており、その背景にはテレワークの普及やSaaS利用増加によって社外からでも遠隔で資産状況を把握できるニーズが高まったことがあります。クラウド型はインターネット経由で管理でき、常に最新バージョンへのアップデートが自動提供されるため、情シスの運用負荷を大幅に減らせます。
一方でオンプレミス型も依然選択肢として残っています。社内規定やセキュリティポリシー上クラウド利用が制限されている企業、細かなカスタマイズが必要なケース、あるいはオフライン環境での利用など、オンプレ型が適している場面もあるためです。最近では両者の利点を組み合わせたハイブリッド型を採用し、重要データは社内で保持しつつクラウド管理の利便性も享受する企業も見られます。
MDM・SaaS・ID管理との統合が加速
IT資産管理の範囲はPCやソフトだけでなく、スマートフォンやタブレットなどモバイル端末のMDM(Mobile Device Management)、各種クラウドサービスのSaaS管理、さらにはユーザーアカウントのID管理(IAM)へと広がっています。
昨今のゼロトラストセキュリティの潮流においては、ユーザーだけでなくデバイスも信頼性を常に検証する必要があり、IT資産管理ツールと認証基盤の連携は重要なテーマです。例えばIT資産管理とID管理を統合し、許可されたユーザーのみが許可された端末から社内システムにアクセスできるようにすれば、ゼロトラストの理念を体現できます。
また、PC管理ツールとMDMの連携によるデバイス一元管理や、SaaS管理ツールとの連携による利用状況の可視化なども進んでいます。こうした統合管理によって社内外のIT資産を包括的に把握し、セキュリティとガバナンスをより一層強化できるようになります。
クラウド・オンプレミス・BPOを8指標で比較
クラウド型:手軽さと拡張性を重視する企業向け
クラウド型のIT資産管理サービスは、サービス事業者のクラウド上で提供されるSaaSモデルです。インターネット環境さえあれば申込後すぐに利用開始でき、サーバー購入やシステム構築が不要なため初期費用は抑えられます。月額課金で導入しやすく、必要に応じて利用ライセンス数を柔軟に増減できる拡張性も魅力です。バージョンアップやメンテナンスもベンダー側で自動対応してくれるため、アップデートの手間やサーバー保守負担から解放されます。
その反面、自社要件に合わせた細かなカスタマイズは難しい場合があり、社外クラウドに資産データを預けることへの不安から利用できない業種(金融機関など)もあります。しかし総じて、スピーディーな導入と運用負荷の軽減を優先したい企業にはクラウド型が適した選択と言えるでしょう。
オンプレミス型:自社運用とセキュリティを優先する場合
オンプレミス型は、自社内にサーバーや管理システムを構築して運用するタイプのIT資産管理ツールです。自社環境内で完結するため、機能追加やレポート項目のカスタムなど自由度が高く、既存の社内システムとの細かな連携も実現しやすい利点があります。また資産データを社内に保持できることから、「情報を外部クラウドに出せない」というセキュリティ要件にも応えられます。
一方で導入までにサーバー調達・環境構築など時間と初期コストがかかり、数百万円規模の初期投資が必要になるケースもあります。また運用面でも自社でシステムを維持するため、ソフトウェアのバージョンアップ対応やサーバーメンテナンス、人員の確保など継続的な負担が発生します。中長期的に見れば買い切りライセンスのオンプレ型はランニング費用を抑えられる可能性もありますが、導入ハードルや維持コストを考慮すると、主に大企業や高度なセキュリティ要求のある環境で選ばれる傾向があります。
BPO型:リソース不足の企業が任せる選択肢
BPO型(Business Process Outsourcing)は、IT資産管理業務そのものを専門業者に委託する形態です。自社内にツールを導入する代わりに、外部のサービスプロバイダーが機器の調達・キッティングから資産台帳の管理、故障対応、廃棄処理までライフサイクル全般を代行します。情シス担当者が少なく日常業務で手一杯な企業でも、BPOを活用すれば資産管理の標準化・効率化が図れ、本来注力すべきコア業務に専念できます。専門業者には豊富な知見を持つスタッフが揃っており、万一のトラブル対応や最新技術へのキャッチアップも任せられる安心感があります。
ただし、サービス範囲や品質は提供企業によって様々なため、どこまで任せられるか(調達のみ、運用全般まで等)を事前に確認する必要があります。また自社内にノウハウが蓄積されにくい側面もあるため、契約ベンダーのサポート体制や実績をよく見極めることが重要です。
IT資産管理サービスの導入前に押さえる7つのチェックポイント
管理対象の規模と範囲
まず、自社のIT資産管理の対象規模と範囲を明確にすることが重要です。管理すべき端末台数や拠点数、対象となる資産の種類(PC、モバイル、サーバー、周辺機器、ソフトウェア、SaaSなど)を洗い出しましょう。例えば数百台規模までであればシンプルな機能のツールで十分な場合もありますが、数千台を超える大規模環境ではより強力な検索・レポート機能や自動化機能が求められるでしょう。
また、ハード資産だけでなくソフトウェアライセンスやクラウドサービス契約も含めて管理したいのかといった範囲によって、必要なサービスは異なります。現状の資産規模と将来的な増減予測を踏まえ、スケーラビリティも考慮に入れて選定する必要があります。
必須機能と優先順位
次に、IT資産管理サービスに求める必須機能を洗い出し、その優先順位をつけましょう。一般的な機能には、インベントリ自動収集(ハード・ソフト情報の自動取得)、ソフトウェアライセンス管理、セキュリティパッチ適用状況の可視化、端末の遠隔操作・制御、デバイス紛失時のリモートロック/ワイプ、操作ログ管理、レポーティング機能など多岐にわたります。自社の課題に直結する機能はどれかを見極め、必須のものとあれば便利なものに分類すると選定がスムーズです。
例えば、「使われていないPCやソフトを把握してコスト削減したい」が主目的ならインベントリとライセンス管理が最重要になりますし、「セキュリティリスクを低減したい」ならパッチ管理やデバイス制御、ログ監視機能が不可欠となります。このように目的に沿って優先度を決めておけば、製品比較の際に不要な機能に惑わされず、自社に合ったサービスを選びやすくなります。
導入方式と環境適合性
クラウド型かオンプレミス型か、あるいは前述のBPO型か、自社に適した導入方式もあらかじめ検討しておきましょう。自社のITポリシーやインフラ環境との適合性を考える必要があります。クラウド型は手軽ですが、社内ネットワークからインターネットへの接続が必須となるため、オフライン環境では利用できません。
一方オンプレ型は自社サーバーを用いるためネットワーク帯域やサーバー性能の確保、対応OSやデータベース要件など技術的適合性を確認する必要があります。また、既存資産台帳をクラウドに預けることへの社内合意が得られるか、逆にオンプレ導入に必要なサーバー資源や予算が確保できるかも重要です。各方式のメリット・デメリットを踏まえ、自社の事情に最も合致する形態を選択しましょう。
既存システムとの連携可否
IT資産管理サービスを単独で導入するだけでなく、社内の既存システムと連携できるかもチェックポイントです。具体的には、社内のディレクトリサービス(Active Directoryなど)からユーザーや組織情報を取り込めるか、ソフトウェア配布ツールやITサービス管理(ITSM)システムと連携してライフサイクルイベントを自動連携できるか、あるいは人事システムと連動して入退社時にアカウント発行・削除を自動化できるか等が挙げられます。これらが可能だと、資産情報の重複入力を防ぎ、一貫した運用フローを構築できます。
またAPI提供の有無も確認しましょう。APIがあれば、自社でカスタムスクリプトを組んで他システムとデータ連携させる柔軟な運用も可能となります。将来的なシステム拡張やDXを見据え、社内のIT基盤との親和性はしっかり確認しておきましょう。
セキュリティ/ガバナンス要件
情報セキュリティやガバナンスに関する自社の要件も、サービス選定前に洗い出す必要があります。例えば、資産データベースに含まれる端末情報やソフトウェア情報は社外秘に当たるため外部クラウドには置けない、といった制約がないか。クラウド型サービスを利用する場合は、データセンターの所在地(国内か海外か)、サービス提供会社のセキュリティ認証(ISO27001やSOC2等)の取得状況、データ暗号化の有無、アクセス制御の仕組みなどを確認しましょう。
オンプレ型の場合も、管理サーバー自体のセキュリティ(脆弱性対応やアクセス権管理)に留意が必要です。また、監査ログの保存や証跡管理が内部統制上必要な場合は、その機能が備わっているかも重要です。ライセンス監査に対応するためのレポート機能の有無など、自社のガバナンス水準に適合したサービスかどうかを事前にチェックしてください。
コスト試算と ROI
導入にかかるコストを試算し、期待される効果と比較してROI(投資対効果)を評価しましょう。コストには初期費用(導入費用、サーバー購入費など)とランニング費用(月額利用料、保守費用、人件費)が含まれます。クラウド型であれば初期費用は低く抑えられるものの月額費用が発生し続け、オンプレ型であれば初期に大きな投資が必要ですが長期利用で元が取れる可能性があります。その損益分岐点が自社にとって何年目かをシミュレーションすることが大切です。例えば、100台規模であればクラウド型の方が初年度コストは安く済むが、5年利用するならオンプレ型購入の方が総コストが低くなる、といったケースもありえます。
また、IT資産管理によって削減できる工数(人的コスト換算)や未使用ライセンスの解約によるコスト削減額、セキュリティ事故防止による損失回避など定量効果も試算し、総合的にROIを見積もることが重要です。
ベンダーのサポート体制と将来性
最後に、サービス提供ベンダーのサポート体制や製品の将来性も重要なチェックポイントです。導入後、困ったときに問い合わせできるサポート窓口の対応時間や質、担当者の専門知識レベル、さらにはオンサイトでの支援可否などを確認しましょう。日本語でのきめ細かなサポートを提供しているか、サポート費用はどの程度かも判断材料です。
またそのサービス自体の開発元企業の信頼性(上場企業か、長年の実績があるか等)や、ロードマップ(今後どんな機能拡充が予定されているか)、ユーザーフォーラムやコミュニティの充実度などもチェックしてください。せっかく導入してもサービスが数年で終了してしまったり、時流に乗ったアップデートが行われなければ、長期的な効果は得られません。ベンダーの継続的な製品改善意欲や経営の安定性にも目を配り、安心して任せられるパートナーを選ぶことが成功への鍵です。
月額・買い切り・無料版の違い
月額課金と買い切り型の違いと損益分岐点
IT資産管理サービスの料金体系には、大きく月額課金制(サブスクリプション)と買い切り型(永続ライセンス)の2種類があります。それぞれメリット・デメリットがあり、利用期間や資産規模によってお得度が変わります。月額課金制は初期費用が低く始めやすい反面、長期的には支払い総額が買い切りより高くなる可能性があります。
一方、買い切り型は初期にまとまった投資が必要ですが、その後のランニングコストを抑えられる利点があります。ただし買い切りの場合でも保守サポート費やバージョンアップ費用が別途かかるケースも多く、完全に支出がゼロになるわけではありません。損益分岐点を見極めるには、自社の導入規模や利用年数を踏まえてTCO(総所有コスト)を比較検討することが大切です。
例えば、オンプレ型で100台分のライセンスを購入する場合とクラウド型で100台を5年間利用する場合では、初年度はクラウドの方が安価でも5年合計ではオンプレ購入の方が安くなる、といった可能性もあります。自社の資産台数や運用計画に照らして、何年間利用すればどちらが有利になるか試算しておきましょう。
無料版・トライアル版の実力と注意点
IT資産管理ツールの中には、機能限定の無料版や一定期間利用可能なトライアル版を提供しているものもあります。無料版はコストゼロで導入でき魅力的ですが、管理可能な端末数が少なかったり、使える機能が基本的なインベントリ機能に限られていたりする場合が多いです。無償ゆえにサポートが受けられなかったりアップデート頻度が低かったりするリスクもあります。
一方トライアル版は有料サービスを一定期間試せるもので、本番導入前の検証に最適です。トライアル期間中に自社の環境でエージェントを配布し、インベントリ収集の精度や操作感、レポート出力の内容を確認しましょう。注意点として、トライアルで登録した資産データが正式導入時に引き継げるかなどを事前に確認しておきましょう。無料版・トライアル版はいずれも製品選定の有力な参考になりますが、そのまま本格運用するには限界があるため、最終的には有料版の導入を見据えて評価することが大切です。
IT資産管理サービス導入の成功事例
製造業:IT資産棚卸しを自動化し作業時間を75%削減
ある老舗製造業の企業では、毎年数回実施していたPCや周辺機器の棚卸し作業に膨大な人手と時間がかかっていました。各部署からExcel台帳を回収し現物と突き合わせる手法ではミスも多く、情シス担当者は通常業務の合間に深夜残業で対応する状況だったといいます。そこでIT資産管理サービスを導入し、エージェントプログラムによる資産情報の自動収集と、Web上での台帳一元管理に切り替えました。
その結果、手作業での照合作業が不要となり棚卸し工数は大幅に圧縮されました。実際、NTTデータグループ企業の事例ではExcel台帳から解放され棚卸し作業時間が75%削減されたケースがあります。この製造業企業でも同様に、棚卸しに費やしていた時間が4分の1に削減され、情シス担当者は浮いた時間を他の戦略的IT業務に充てられるようになりました。
上場IT企業:SaaS管理の最適化でコスト年間1,200万円削減
従業員数千名の上場IT企業では、部門ごとに様々なSaaSを導入した結果、全社で把握しきれないほど多くのクラウドサービス契約が乱立し、重複利用や未活用ライセンスによるコスト増が問題となっていました。そこで統合型のIT資産管理サービスを採用し、全SaaSアカウントを一元管理する取り組みを行いました。まず各部門で使われているSaaSを調査・棚卸しし、類似ツールが複数あるものは集約、契約プランも適切な人数分に最適化しました。
その結果、ある金融系企業では17種類のSaaSを9種類に統合し年間約1,200万円のライセンス費用を削減した事例もあるように、この企業でも年間数百万円単位のSaaSコスト削減に成功しました。なお、可視化により不用意な重複契約を防ぎ、IT予算の最適化にも繋がりました。さらには一元管理によって従業員からの「どの部門がどのツールを使っているか分からない」といった問い合わせも減少し、情シスの管理負荷軽減にも寄与しました。
医療法人:MDM連携でセキュリティとガバナンスを強化
ある医療法人では、院内で利用する多数のPCやiPadなどを少人数のIT担当者で管理しており、端末が今どこにあるか誰が使用中か把握しきれないという課題を抱えていました。特に医療機関では患者情報を扱うため、デバイスごとの利用状況を追跡し不適切な利用を防ぐことが重要です。そこで、IT資産管理ツールとモバイル向けMDMを組み合わせて導入し、PCからタブレットまで全デバイスを統合管理する仕組みを構築しました。各端末にはエージェントやプロファイルを適用し、リアルタイムで所在と使用者を把握できるようにしたほか、利用ポリシーに反するアプリインストールや不正な設定変更が行われた場合に即座に検知・遠隔制御する体制を整えました。
その結果、端末管理の属人化を排除して監査対応も容易になり、情報ガバナンスが飛躍的に向上しました。院内の紙資料をタブレット閲覧に切り替えたことで年間1万枚以上の紙資料印刷を削減する副次効果も得られ、IT活用による働き方改革の一環として社内外から高い評価を受けています。
IT資産管理サービスで最大効果を得るために
IT資産管理サービスは導入して終わりではなく、活用してこそ初めて価値が生まれます。最大効果を得るためには、まず社内ルールの整備が欠かせません。例えば新しい資産を調達した際には必ず台帳に登録する、従業員が勝手にソフトをインストールしないよう申請フローを設ける、といった運用ルールを明確化しましょう。
またサービス導入時に教育を実施し、各部署のIT担当者や従業員に対してIT資産管理の重要性と基本的な操作方法を周知することも大切です。定期的な棚卸しレポートや未使用ソフトの洗い出し結果を経営層に報告し、継続的な改善につなげるPDCAサイクルを回すことも効果を持続させるポイントです。
さらに、MDMやID管理ツールとの連携、ゼロトラストを見据えた運用の高度化など、導入後も最新の技術トレンドを取り入れて発展させていく姿勢が求められます。IT資産管理サービスを単なる台帳管理ツールに留めず、社内DXとセキュリティ強化の基盤として積極的に活用し続けることで、情シスの負担軽減と企業全体のITガバナンス向上という最大の効果を享受できるでしょう。




