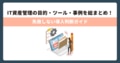IT資産棚卸の目的と方法を徹底解説!押さえるべき基礎と効率化のためのポイント
企業のIT投資が複雑化する今、情報システム部門や総務部門で「棚卸しをしたいが、何から手を付ければいいのか」と悩む担当者は少なくありません。
本記事では、IT資産棚卸の基本概念から実施タイミング、具体的な手順、効率化ツールの選び方までを、現場目線で解説します。コンプライアンス遵守、セキュリティリスクの最小化、そしてコスト最適化という3つの目的を達成しながら、全社のIT資産を正しく把握し活用するための実践ポイントをご紹介します。
目次[非表示]
- 1.IT資産棚卸とは?
- 2.IT資産棚卸をする3つの目的
- 2.1.コンプライアンスの遵守
- 2.2.セキュリティリスクの低減
- 2.3.コスト最適化
- 3.棚卸の対象となるIT資産
- 4.IT資産棚卸の実施タイミングと頻度の目安
- 5.IT資産棚卸を行う方法・手順
- 6.IT資産棚卸を効率化する3つの方法
- 6.1.定期的なチェック体制の構築
- 6.2.バーコード・RFIDの利用
- 6.3.IT資産管理ツールの導入
- 7.IT資産の棚卸を定期的に実施し、自社のIT資産の状況をしっかり把握しよう
IT資産棚卸とは?
IT資産棚卸とは、企業や組織が所有するパソコンやサーバー、ネットワーク機器、ソフトウェアライセンスなどのIT資産を定期的に洗い出して現状を把握する作業のことです。もともと棚卸は「期末に在庫の数量を確認し、期末の棚卸資産の金額を確定させる目的で行われる作業」のことを言います。IT資産の場合は金額の算定ではなく資産の所在と利用状況を確認する目的が重視され、棚卸を行うことで、どのようなIT資産がどこにあり、どのように利用されているかを明確にできます。
また、IT資産棚卸を行うことで、資産の紛失や重複購入を防ぎ、無駄なコストの削減やセキュリティリスクの低減が可能になります。さらに、多くの業界でIT資産管理の基準やセキュリティ基準への準拠が求められており、定期的な棚卸はコンプライアンス維持の観点からも重要です。
IT資産棚卸をする3つの目的
IT資産棚卸を定期的に実施することには、大きく分けて「コンプライアンスの遵守」「セキュリティリスクの低減」「コスト最適化」の3つの目的があります。それぞれの目的について詳しく見ていきましょう。
コンプライアンスの遵守
IT資産棚卸の第一の目的は、コンプライアンス(法令遵守)の確保です。特にソフトウェアライセンスの管理を怠ると、許可された数以上のインストールや契約期間を過ぎた利用など、ライセンス違反が発生しかねません。実際にライセンスの不正使用が行われれば、ソフトウェアメーカーから損害賠償請求を受けたり刑事罰の対象となったりするリスクがあります。
管理部門でライセンスを一元管理するとともに、定期的に棚卸を行って契約通りに使用していることを確認することで、こうしたライセンス違反を防止できます。また、情報セキュリティ規格(ISO/IEC 27001など)でも資産管理の徹底が求められているため、定期的な棚卸を継続することはこうした規格や社内監査基準の遵守にも役立ちます。
セキュリティリスクの低減
2つ目の目的は、セキュリティリスクの低減です。正確にIT資産を把握できていないと、社内にセキュリティパッチが未適用のパソコンや古いソフトウェアが残存していても気づかず、脆弱性を抱えたまま放置される恐れがあります。
管理されていないハードウェアやソフトウェアが脆弱性を持ったままだと、不正アクセスなどサイバー攻撃の標的となり、企業のセキュリティリスクを高めてしまいます。棚卸によって全ての機器やソフトウェアの更新状況を確認し、必要なアップデートを適用することで、セキュリティ上の弱点を減らすことができます。
例えば、サポート期限が切れたOSや古いソフトウェアが社内に残ったままだと、それ自体が重大な脆弱性となりえます。棚卸でそのような端末やソフトを洗い出し、アップデートや使用停止など適切な対処を行うことができます。さらに、棚卸を定期的に行ってデバイスの所在を確認しておけば、紛失した端末が放置されて情報漏えいにつながる事態も防げるでしょう。
コスト最適化
3つ目の目的は、ITコストの最適化です。IT資産は年々増加し、使われていないPCやソフトウェアライセンスが社内に潜んでいる可能性があります。棚卸を通じて未使用の機器や余剰なライセンスを発見すれば、不要な資産を廃棄・売却したり、余っているライセンスを解約したりすることで無駄なコストを削減できます。
また、利用頻度の低いハードウェアが見つかった場合、新規にハードウェアを購入する代わりに必要な業務に転用することで、無駄な保守費用の圧縮やソフトウェアライセンスの有効活用につながります。このように社内のIT資産を正確に把握することで、重複投資を防ぎ、限られた予算を効率的に活用できるようになります。
棚卸の対象となるIT資産
IT資産の棚卸では、対象となる資産を大きく「ハードウェア」「ソフトウェア」「ソフトウェアライセンス」の3種類に分類できます。以下のようなものが棚卸の対象例です。
ハードウェア |
デスクトップPC、ノートPC、サーバー、ルーターやスイッチなどのネットワーク機器、
スマートフォン・タブレットなどのモバイル端末、プリンターやディスプレイ、周辺機器類
|
ソフトウェア |
OSやOffice製品などのアプリケーションソフト、セキュリティ対策ソフトなど、
ハードウェアにインストールされているすべてのソフトウェア
|
ソフトウェアライセンス |
各ソフトウェアの使用権(利用可能なライセンス数)と、その割当状況や使用者数、
使用期限などの契約内容
|
IT資産棚卸の実施タイミングと頻度の目安
IT資産棚卸は一般的に年に1~2回、決算期末や中間期末(3月や9月、12月)に実施されることが多いです。特に会計上、期末の時点で資産の状況を正しく把握する必要があるため、多くの企業が年度末に一斉棚卸を行います。
棚卸の頻度は企業の規模やIT資産の増減にもよりますが、長期間実施しないと所在不明の資産が生じるリスクが高まり、資産計上にも影響を与えかねません。そのため、最低でも年に1回は実施し、可能であれば半年に1回や四半期ごとなど定期的なスケジュールで棚卸することが望ましいでしょう。
IT資産は社内で日々増減するため、棚卸の間隔が空きすぎると全体を把握することが難しくなります。適切な頻度で棚卸を実施し、常に最新の資産状況を把握しておくことが重要です。
IT資産棚卸を行う方法・手順
ここからは、IT資産棚卸を具体的に進める方法と手順について解説します。一般的に、棚卸作業は以下のステップで進めます。
STEP1:棚卸の計画を立てる
まずは棚卸の計画を立てます。どの資産を対象に棚卸を行うか、全社のIT資産すべてを対象とするのか特定の部門に限定するのか、といった棚卸しの目的と範囲を明確に定めます。その上で、棚卸を実施するチームを編成し、メンバーの役割と責任を決めます。IT部門だけでなく各部門の担当者も巻き込むことで効率的に進められるでしょう。
また、棚卸の実施日時を計画し、本番に向けて必要な準備(台帳フォーマットの用意や資産管理番号シールの手配など)も行います。事前に計画を綿密に立てておくことで、棚卸当日の混乱を防ぎスムーズに作業を進めることができます。
STEP2:資産を洗い出し、台帳を作成する
次に、棚卸の対象となるIT資産をすべて洗い出し、資産管理台帳を作成します。
社内で保有しているすべてのハードウェア(自社購入品だけでなくリース品も含む)と、インストールされている主要なソフトウェアを漏れなくリストアップしましょう。台帳には「資産の種類」「品名」「管理番号」「設置場所」「購入元」「取得年月日」「取得価格」「耐用年数」などの項目を記載します。
また、ソフトウェアライセンスについても契約内容(ライセンス数や契約期間、購入元など)を確認し、使用している機器や利用者に紐付けて整理しておきます。資産点数が少ないうちはExcelなどで管理できますが、台数が多くなると手作業ではミスが発生しやすいため、専用のIT資産管理ツールの活用も検討するとよいでしょう。なお、後の照合作業を円滑に進めるため、資産ごとに固有の管理番号(バーコードなど)を割り振り台帳に記載しておくと良いでしょう。
STEP3:現物と台帳を照合する
台帳の準備ができたら、実際に現物のIT資産と台帳の内容が一致しているかを確認します。棚卸対象のハードウェア一つひとつに資産管理用の番号ラベルを貼付し、台帳上の登録情報と照合していきます。現物と台帳を付き合わせるこの作業によって、紛失・未返却のデバイスや、台帳未登録のデバイスなどがないかを洗い出せます。
一般的には担当者が目視で番号を確認してチェックしますが、IT資産管理ツールとバーコードスキャナーなどを活用すれば効率的に照合作業が行えます。例えば、デバイスに貼ったバーコードやICタグを専用の機械で読み取って台帳データと自動照合することで、人的な作業時間を大幅に削減できます。
もし台帳には存在しているのに現物が見当たらない場合は、関係者に確認して紛失や未返却の可能性を調査します。逆に現物はあるのに台帳に記載がないデバイスについては、新規に台帳へ登録する必要があります。
また、テレワークなどで社外に持ち出されているデバイスについては、管理ツールで遠隔から情報を取得するか、利用者に所在と機器情報を報告してもらう方法で確認を行います。
STEP4:台帳を更新し、継続的にモニタリングする
棚卸作業で判明した情報をもとに、資産台帳を最新の状態に更新します。確認の結果、実在しない資産が台帳に載っていた場合は台帳から削除し、所在不明の資産があれば原因を調査して適切に対処しましょう。同時に、今回の棚卸で発見された未記入事項や誤情報を修正し、次回以降の棚卸に活かせるよう台帳の精度を高めます。
棚卸は一度やって終わりではなく、継続的なモニタリング体制を整えることも重要です。ハードウェアの導入・廃棄や設置場所の変更などが発生した際には、その都度台帳を確実に更新するルールを定め、関係者に徹底しましょう。台帳更新時にダブルチェックを行うなど、更新漏れを防ぐ仕組みを設けておくと安心です。日頃から台帳をメンテナンスしておけば、定期棚卸の際もスムーズに進み、大きな差異が出にくくなります。
IT資産棚卸を効率化する3つの方法
IT資産の棚卸作業は手間がかかりますが、いくつかの工夫によって効率化することが可能です。ここでは、棚卸業務の負担を軽減するための3つのポイントを紹介します。
定期的なチェック体制の構築
一つ目の効率化策は、定期的な棚卸チェック体制を構築することです。棚卸を不定期に行うと、間隔が空いた場合に現物と台帳の差異が多く発生し、その原因究明にも大変な労力を要します。逆に、棚卸を毎年または半年ごとなど決まった時期に定期的に実施すれば、棚卸作業を習慣化して台帳更新の重要性が社内で共有されやすくなります。
定期スケジュール化することで、要員の確保や関係部署との調整もしやすくなり、結果的に短期間で効率よく棚卸を完了できるでしょう。なお、年1回の一斉棚卸に加えて、四半期ごとに一部の部署や資産カテゴリごとに分散して棚卸を行うなど、自社の状況に応じて柔軟に計画することも有効です。
バーコード・RFIDの利用
二つ目の効率化策は、資産管理にバーコードやRFIDタグを活用することです。棚卸対象の機器にバーコードやICタグ(RFIDタグ)を貼り付け、棚卸時に専用のハンディスキャナーなどで読み取ることで、台帳との照合を一括して行えます。人手で一つずつシリアル番号や型番を照合するよりも格段にスピーディーで、入力ミスも防げるため棚卸作業の時間短縮に繋がります。
特に、RFIDタグであれば多数の資産を一度に読み取ることも可能なため、規模の大きい現場での棚卸に有効です。ただし、RFIDタグや専用リーダーの導入コストも考慮する必要がありますので、自社の資産規模に見合った方法を選びましょう。
IT資産管理ツールの導入
三つ目の効率化策は、IT資産管理ツール(専用ソフトウェア)の導入です。保有するIT資産の情報を一元管理できるツールを活用すれば、棚卸に必要なデータを自動収集・更新でき、人手による管理と比べてミスが減ります。各PCに管理エージェントを導入すれば、ハードウェアの仕様やインストール済みソフトウェアを常に把握できるため、棚卸時に個別調査する手間を省けます。
IT資産管理ツールには資産の台帳管理機能はもちろん、ソフトウェアライセンス契約の管理や保守期限の通知、予算管理との連携など便利な機能を備えた製品もあります。クラウド型のIT資産管理システムであればリアルタイムにデータが更新され、リモート環境からでもアクセス可能なので、多拠点での資産管理にも適しています。自社の規模に合わせて適切なツールを導入することで、棚卸業務を大幅に効率化し、担当者の負担を軽減できるでしょう。
IT資産の棚卸を定期的に実施し、自社のIT資産の状況をしっかり把握しよう
IT資産の棚卸は、コンプライアンスの遵守やセキュリティ対策、コスト管理の最適化に欠かせない重要な取り組みです。近年、一人の社員がPCとスマホなど複数のデバイスを扱うケースや、リモートワークで社外にデバイスを持ち出すケースが増え、IT資産管理の難易度が上がっています。だからこそ、自社のIT資産がどのように利用され、適切に管理されているかを定期的に棚卸することで、不正や無駄を未然に防ぎ、安心してIT資産を活用できるようにしましょう。
まだ十分な棚卸体制が整っていない場合は、本記事で解説した目的や手順、効率化のポイントを参考に、早めに取り組んでみてください。定期的な棚卸の実施によって自社のIT資産の状況を正確に把握し、適切な管理と運用に役立てていくことが大切です。