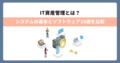クラウド型IT資産管理のすべて──メリットから管理ツール比較・導入成功事例まで
近年、社内のPC・モバイル端末やクラウドサービス(SaaS)の利用が急増し、従来のExcel台帳による管理は限界を迎えつつあります。テレワークの定着により社外からの利用状況も把握する必要が生じ、リアルタイムな可視化とセキュリティ確保が求められています。こうした課題に応える解決策として注目されているのがクラウド型IT資産管理です。この記事では、クラウド型IT資産管理の基本からオンプレ型との違い、導入が進む背景やメリット、主要ツール比較、導入ステップや成功事例、さらにセキュリティ強化策までを網羅的に解説します。“脱Excel”による効率化・DX推進のヒントとして、ぜひご一読ください。
目次[非表示]
- 1.クラウド型IT資産管理とは?オンプレ型との違い
- 1.1. IT資産管理とは何か?
- 1.2.クラウド型とオンプレ型の違い一覧
- 2.クラウドITAMが注目される背景と市場動向2025
- 2.1.リモートワーク普及とSaaS増加
- 2.2.国内市場規模と成長率
- 3.クラウドIT資産管理のメリット5選
- 3.1.遠隔管理のしやすさ
- 3.2.自動アップデートでコスト削減
- 3.3.スケーラビリティの高さ
- 3.4.コンプライアンス強化とライセンス管理の効率化
- 3.5.初期費用を抑えたコスト最適化
- 4.機能でわかるクラウドITAM選定チェックリスト
- 4.1.自動インベントリ機能
- 4.2.ライセンス管理自動化
- 4.3.SaaSアカウント棚卸し
- 5.主要クラウドIT資産管理ツール比較表(価格・機能・導入規模)
- 6.料金体系とコスト試算:年間予算はどれくらい?
- 6.1.初期費用と月額課金モデル
- 6.2.100台規模の料金シミュレーション
- 7.導入ステップと移行のポイント:失敗しない手順書
- 7.1.現状台帳のデータ移行
- 7.2.権限設計・アクセス制御
- 8.事例で見る導入効果:工数40%削減した企業の声
- 8.1.製造業A社:工数40%削減
- 8.2.ITベンチャーB社:SaaS可視化
- 9.セキュリティ&ガバナンス強化の実践術
- 9.1.ゼロトラストとITAM連携
- 9.2.監査レポート自動生成
- 10.クラウドIT資産管理でDXを加速させよう
クラウド型IT資産管理とは?オンプレ型との違い
IT資産管理とは何か?
「IT資産管理(IT Asset Management、略してITAM)」とは、企業や組織が保有・利用するあらゆるIT資産(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク機器、クラウドサービスなど)の情報を正確に把握し、ライフサイクル全体で適切に管理する活動です。
具体的には、PCやサーバー等の台数や構成、ソフトウェアのインストール状況やライセンス数、利用しているクラウドサービスの契約情報などを一元管理します。適切なIT資産管理によって無駄な機器・ライセンスの購入を抑え、コスト最適化やセキュリティ強化、コンプライアンス遵守につなげることができます。また内部統制上も、誰がどの資産を使っているかを明確にしておくことが重要です。
かつてはExcelによる手作業管理が一般的でしたが、IT資産の種類・数が増えた現在では継続的で拡張性のある管理手段としてExcel管理は限界です。そこで専用のIT資産管理ツールの活用が進んでおり、特にクラウド型IT資産管理ツールが注目されています。
クラウド型とオンプレ型の違い一覧
IT資産管理ツールには、自社内サーバーに構築するオンプレミス型と、サービス提供事業者のクラウド環境を利用するクラウド型(SaaS型)があります。それぞれメリット・デメリットがあり、主な違いは以下の通りです。
クラウド型(SaaS型) |
オンプレミス型 |
|
|---|---|---|
初期費用 |
サーバー購入不要で低コスト |
自社サーバー構築が必要で高額 |
導入スピード |
申し込み後すぐ利用開始 |
環境構築・検証で時間がかかる |
運用・保守負荷 |
ベンダーがアップデート・監視を担当 |
自社で対応、人的コスト大 |
カスタマイズ性 |
提供範囲内の設定が中心(自由度中) |
自社要件に合わせ高度に変更可 |
利用場所 |
インターネット経由でどこからでも管理 |
社内ネットワーク前提(外部はVPN等) |
費用体系 |
月額/年額サブスクリプション(OPEX) |
買い切りライセンス+保守料(CAPEX) |
セキュリティ |
データはクラウド上、第三者管理 |
データを社内保持、完全自社管理 |
可用性 |
ネットワーク障害時に利用不可のリスク |
オフラインでも利用可能 |
スケーラビリティ |
端末・拠点増に即応、拡張が容易 |
追加サーバー調達・構築が必要 |
以上のように、初期コストや手間を抑えて迅速に導入できるのがクラウド型、カスタマイズ性やオフラインでも使える安定運用が魅力なのがオンプレ型と言えます。昨今は両者を組み合わせたハイブリッド型の活用も見られますが、自社の規模・要件・セキュリティポリシーに合わせて選択することが大切です。
クラウドITAMが注目される背景と市場動向2025
リモートワーク普及とSaaS増加
クラウド型IT資産管理がここ数年で注目を集めている背景には、働き方の変化とクラウドサービス利用拡大があります。コロナ禍以降リモートワークやハイブリッドワークが定着し、社員が社外から業務を行うケースが増えました。従来のオンプレ型IT資産管理では社内ネットワーク内のPC把握が中心でしたが、テレワーク下では自宅や出先のPC・モバイル端末も含め遠隔から資産を可視化できる仕組みが求められるようになりました。クラウド型であればインターネット経由で社内外問わずデバイス情報を収集できるため、リモート環境下でも一貫した管理が可能です。
また、業務で使うクラウドサービス(SaaS)の導入も飛躍的に増えています。メールやグループウェアから営業支援、開発ツールに至るまで様々なSaaSを各部門が利用するようになり、アカウントや契約の棚卸し管理が新たな課題となりました。クラウド型ITAMはこうしたSaaSの利用状況も一元的に把握でき、いわゆる「シャドーIT」(会社が把握していない無許可のIT利用)によるリスクへの対策にも有効です。実際、企業が把握していないシャドーIT資産の存在がセキュリティ意識を高め、IT資産管理の重要性が再認識される結果となっています。
国内市場規模と成長率
クラウド型IT資産管理ツール市場は拡大傾向にあります。調査によれば、日本のSaaS型IT資産管理ツール市場規模は2023年に約2,971.6億円、2024年に3,387.6億円、2025年には3,767.0億円規模まで成長すると予測されています。年率にして約10%以上の成長が見込まれ、非常に高い伸び率です。背景には前述のリモートワークやスマートデバイスの普及による管理対象増加があり、スマホやタブレットを含めた資産管理ニーズの高まりが市場拡大の要因とされています。またクラウド化シフトの流れも顕著で、ある調査ではIT資産管理ツールをクラウド型で導入・検討している企業が約9割にのぼったとの結果もあります。オンプレミス型が主流だった領域でもクラウドサービスへの置き換えが進み、市場は2025年に向けてさらなる成長が期待されています。
このように、「いつでもどこでもIT資産を見える化したい」というニーズやDX推進に伴うITガバナンス強化の潮流が、クラウドITAM普及を後押ししているのです。
クラウドIT資産管理のメリット5選
クラウド型IT資産管理ツールには、オンプレ型にはない利点が数多くあります。ここでは主なメリットを5つ紹介します。
遠隔管理のしやすさ
クラウド型の最大の特徴は、インターネット経由でどこからでも資産状況を把握・操作できる点です。管理サーバーがクラウド上にあるため、情報システム担当者はオフィスにいなくてもWebブラウザからリアルタイムに資産台帳を確認できます。
例えばテレワーク中でも社員PCのソフトウェア一覧やセキュリティパッチ適用状況をチェックでき、不正ソフト発見時にはその場で対応策を講じることも可能です。拠点が複数ある企業でも本社から一元管理でき、現地に管理者がいない場合でもクラウド経由で遠隔監視・サポートが行えます。地理的な制約を超えてIT資産管理の「見える化」を実現できるのは、クラウドITAMならではの強みです。
自動アップデートでコスト削減
クラウドサービスでは、ソフトウェアのバージョンアップやパッチ適用が提供ベンダー側で自動的に行われます。そのため利用企業は常に最新機能・最新セキュリティパッチが適用された状態でツールを使え、オンプレ型のように自社でアップデート作業をする必要がありません。これは運用工数の大幅削減につながり、IT担当者の負担軽減と人件費コストの削減効果があります。サーバー監視やバックアップ対応もクラウド事業者が担うため、煩雑な保守作業から解放されます。
またバージョンアップに伴う追加費用も原則不要で、古いバージョンを放置した結果機能が陳腐化するリスクも低減します。こうした自動更新による保守コスト削減効果は、クラウド型を採用する大きなメリットと言えるでしょう。
スケーラビリティの高さ
クラウドサービスは必要に応じてリソースを柔軟に増減できるため、IT資産管理ツールもスケーラビリティ(拡張性)が高いです。例えば管理対象デバイスが増えた場合でも、追加ライセンスをオンラインで購入するだけで即対応できます。オンプレミス型のようにサーバー増設やシステム再構築をしなくて済み、急な事業拡大や組織変更にも素早く追従できます。
また一時的に端末台数が減った場合にはライセンス数を縮小してコストを調整することも比較的容易です。「使った分だけ」の従量課金に近い運用も可能なため、無駄のない形でツールを利用できます。ビジネス環境の変化が激しい現代において、この柔軟な拡張性はクラウドITAMの大きな強みです。
コンプライアンス強化とライセンス管理の効率化
クラウド型ITAMは、資産情報を集中的に管理し自動レポート化できるため内部統制やソフトウェアライセンス遵守の強化に貢献します。例えば各PCのインストールソフト情報と保有ライセンス数を自動照合し、ライセンス過不足を可視化できます。これにより未許可ソフトの使用やライセンス超過を早期に発見して是正でき、違法コピーや監査指摘のリスクを低減します。実際にクラウドITAM導入で「ソフト資産棚卸にかかっていた時間を大幅削減できた」との声もあります。
またクラウド上に操作ログやデバイス利用履歴が蓄積されるため、内部不正の抑止や証跡管理にも有用です。USBメモリ利用やソフトインストールのログを自動収集・チェックすることで、情報漏洩対策やISMSの監査対応も強化できます。つまりクラウドITAMはライセンス管理とコンプライアンス管理を効率化し、組織のITガバナンス向上に寄与するのです。
初期費用を抑えたコスト最適化
クラウド型ツールは初期投資が少なく、コスト面でも導入ハードルが低いことが魅力です。オンプレミス版のような専用サーバー購入・構築費が不要で、基本的に月額・年額の利用料だけでスタートできます。資金に限りがある中小企業でも、小規模から気軽に導入を始めて効果を見ながら拡大するといったスモールスタートが可能です。
またハード保守やシステム更新に伴う予期せぬ出費も発生しにくく、費用予測が立てやすいというメリットもあります。例えば「100台規模でクラウドITAMを利用して年間○○万円」など、サブスクリプション費用として年間予算化しやすいでしょう。
さらに不要になれば契約を縮小・停止できるため、情勢変化によるコスト見直しもしやすい柔軟なモデルです。総じて、クラウドITAMは初期費用の低減と運用コストの最適化を実現し、ROIを高めやすい選択肢と言えるでしょう。
機能でわかるクラウドITAM選定チェックリスト
多数のクラウド型IT資産管理ツールが存在しますが、選定の際には自社に必要な機能を備えているか確認することが重要です。ここでは必須機能3点をチェックリスト形式で紹介します。
自動インベントリ機能
まず欠かせないのが自動インベントリ収集です。これは各PCやサーバーにエージェント(管理用プログラム)を配布し、ハードウェア情報やソフトウェア情報を自動収集する機能を指します。
具体的には、CPU・メモリなど端末のスペック、OSやインストールソフト、適用パッチの状況まで一定間隔でクラウド上に報告されます。これにより常に最新の資産台帳を維持でき、手作業による台帳更新漏れや情報のズレを防げます。
Excel管理では新PCの購入時に人手で台帳追加していましたが、自動インベントリ機能があればネットワークに繋いだだけで台帳が更新されます。棚卸作業もボタン一つで完了し、年に数回かかりきりだった資産チェック工数が大幅に削減されます。選定時はこの自動インベントリ機能の精度(取得できる項目の豊富さ)や対応OS(WindowsだけでなくMacやLinux、モバイルOSへの対応)を確認しましょう。
ライセンス管理自動化
次に注目すべきはソフトウェアライセンス管理の自動化機能です。ソフト資産の適切な管理はコンプライアンスとコスト最適化の両面で重要ですが、手作業では難易度が高い領域です。クラウドITAMツールには、保有するソフトライセンス数と各端末のインストール状況を紐付け、利用状況を自動で突き合わせる機能があります。
例えばMicrosoft Officeの購入ライセンスが50本の場合、全端末のOfficeインストール台数を常にカウントして超過がないかチェックできます。未使用ライセンスの把握や二重購入防止にも役立ち、結果的にソフトウェア費用の無駄削減につながります。
また、有償ソフトか無償ソフトかをツール側が辞書データで判別してくれる製品もあり、フリーソフトの混入や使用禁止ソフトの検知も自動化可能です。ライセンス有効期限の管理や更新通知などの機能も含め、ソフト資産管理をどこまで自動化できるかは選定のポイントです。
SaaSアカウント棚卸し
昨今はSaaSのアカウント管理機能も重要になっています。社内で利用するMicrosoft 365やGoogle Workspace、各種クラウドサービスのユーザーアカウント情報をITAMツールと連携し、利用状況を可視化できる製品が増えています。
例えばMicrosoft 365のライセンス割当状況を取得して未使用ライセンスを発見したり、人事情報と連携して退職者のSaaSアカウントを一括洗い出す――といったことが可能です。こうしたSaaSアカウントの棚卸し機能により、使われていないクラウドサービス契約を停止してコスト削減したり、不要なアカウントを放置するセキュリティリスクを防いだりできます。
また、OneLoginやAzure ADなどID管理ツール(IDaaS)と連携して社内で利用中のクラウドサービス一覧を取得し、IT資産管理台帳に反映させる高度な仕組みを持つ製品もあります。自社のクラウド利用が多い場合は、こうしたSaaS管理に強いITAMを選ぶと良いでしょう。
主要クラウドIT資産管理ツール比較表(価格・機能・導入規模)
クラウド型IT資産管理ツールの主要な製品について、代表的なものをピックアップし特徴を比較します。ここでは特に導入が多い国内ツールを例に、2つずつ比較してみましょう。
SkySea と LANScope 比較
SkySea Client View(スカイシー・クライアントビュー)とLanScopeシリーズは、どちらも国内で導入社数の多いIT資産管理ツールです。SkySeaはSky株式会社の製品で、オンプレ版が有名ですが2021年からクラウド版(M1 Cloud Edition)も提供されています。一方LanScopeはエムオーテックス社の製品で、旧来のオンプレ版「LanScope Cat」に加えクラウド版「LanScope エンドポイントマネージャー」が展開されています。両者を比較すると以下のような特徴があります。
-
機能面: SkySeaもLanScopeも資産管理・ログ管理・デバイス制御などオールインワンの豊富な機能を備えています。特にLanScopeクラウド版はPCだけでなくスマホ管理(MDM機能)も統合されており、PC・スマホ一元管理を実現している点が強みです。SkySeaも基本機能は網羅的で、オンプレ版と同等の情報漏洩対策機能をクラウドでも利用できます。UIについてはSkySeaが「大きなアイコンで直感的」「操作性が良い」と評価される一方、LanScopeもクラウド管理画面が洗練され使いやすいとされています。
-
価格体系: SkySea Cloud Editionは月額ライセンス制で、参考価格は1台あたり約1,570円/月(50台以上の場合)という情報があります。一方LanScopeエンドポイントマネージャー(クラウド版)は初期契約料30,000円+月額300〜500円/端末のプラン制で提供されます。例えば全機能利用の“ベーシックプラン”では500円/端末/月なので、100台なら月額50,000円(年間60万円)程度が目安です。SkySeaは機能網羅性とサポートの充実度からやや高価格帯、LanScopeはプラン選択制で比較的コスト調整がしやすいと言えます。
- 導入規模: SkySeaは延べ導入社数が非常に多く(国内シェアトップクラス)、大企業から中小まで幅広く利用されています。LanScopeも「メーカーシェアNo.1」との調査結果があるなど普及しています。どちらも数十台〜数千台規模まで対応可能ですが、大規模展開実績ではSkySeaが先行し、多拠点・多数クライアントの統合管理には定評があります。LanScopeはMDM統合やクラウドサービス連携の面で先進的であり、モバイル含む統合運用を重視する企業に選ばれる傾向です。
総じて、SkySeaとLanScopeは機能面では互角であり、自社環境との親和性や予算、重視ポイントで選ぶことになります。例えば「社内PC中心で操作ログの細かな分析重視」ならSkySea、「社給スマホも含めクラウドでライトに使いたい」ならLanScopeといった選択が考えられます。
SS1クラウド と Assetier 比較
SS1(System Support best1)は株式会社ディー・オー・エス(DOS)製の国産IT資産管理ツールで、オンプレ版・クラウド版ともに提供されています。一方のAssetier(アセッティア)はパナソニック コネクト株式会社が2023年に提供開始した新しいクラウド資産管理サービスです。この2つの比較ポイントを見てみましょう。
-
対象範囲: SS1はPCやサーバーのIT資産管理に特化し、ログ管理やセキュリティ対策機能まで統合された総合ITAMツールです。一方AssetierはIT資産に限らず、オフィス家具や工場設備、備品・工具などあらゆる有形資産を一元管理できるプラットフォームとして設計されています。つまりAssetierは固定資産台帳管理に近い広範な用途をカバーし、ネットワーク未接続の資産にもQRコード貼付で対応するのが特徴です。IT資産(PC・ソフト)の細かなログやライセンス管理に強いのはSS1、様々な物品をまとめて管理するならAssetier、とターゲット領域が異なります。
-
主な機能: SS1クラウドはインベントリ収集からソフト配布、操作ログ取得、ライセンス管理、働き方(PC稼働)見える化までフル機能を備え、「顧客満足度No.1」を謳う完成度の高いツールです。特に操作性の良さ(誰でも直感的に使えるUI)やコストパフォーマンスが評価されています。Assetierは資産情報の登録・検索のしやすさや、ダッシュボードでの可視化に加え、ラベル発行や棚卸代行など現場運用支援のBPOサービスも提供する点がユニークです。ITエンジニア以外の資産管理担当者でも扱いやすいよう工夫されており、拠点数が多い企業での統一管理に強みがあります。
-
価格・導入規模: SS1クラウドの料金は公表されていませんが、オンプレ版より低コストでPC1台から利用OKとされています。実績としてはオンプレ版SS1で4,600社以上の導入(2025年1月時点)があり、中堅~大手企業にも多数使われています。Assetierは新サービスのため具体的料金はケースバイケースですが、大規模チェーン展開企業などでの活用を想定しており、全国数千拠点・数万点の資産管理にも耐えうるスケールです。「IT資産管理ツール」として純粋に比較すると、細かなIT管理機能で優れるSS1クラウドに軍配が上がります。ただしIT以外の固定資産もまとめてDXしたい企業にはAssetierが有力な選択肢となるでしょう。
料金体系とコスト試算:年間予算はどれくらい?
初期費用と月額課金モデル
クラウド型IT資産管理ツールの料金体系は、一般に月額または年額のサブスクリプションモデルです。ユーザー数や端末台数に応じて課金され、必要ライセンス数を増減することで柔軟にコスト調整できます。多くのサービスでは初期費用(初回導入費用)が設定されていますが、オンプレ型ほど高額ではなく契約手数料程度の場合もあります。例えばLanScopeクラウド版では初期登録料が契約全体で30,000円と比較的安価です。一方、SkySeaなど一部サービスでは初期費用無料で始められるプランもあります。
契約期間は最低6ヶ月や1年などサービスによりますが、長期契約ディスカウントがある場合もあります。月額料金については、機能レベルや端末種別ごとにプラン分けされているケースが多いです。前述のLanScopeなら、PC資産管理中心の「ライトA」プランは1台300円/月、フル機能利用の「ベーシック」プランは1台500円/月といった具合です。自社の管理対象や必要機能に合わせプランを選択することで無駄なく導入できます。また無料トライアル期間が設けられているサービスも多いため、正式契約前に操作感や機能を評価すると安心です。
総じてクラウドITAMは、初期費用が低く定額課金で計画が立てやすいのが特徴です。オンプレ型のように数百万円の初期投資を一括計上する必要がないため、予算承認も得やすいでしょう。
100台規模の料金シミュレーション
では具体的に、端末100台規模でクラウドIT資産管理ツールを導入した場合のコスト感を試算してみます。前提として、PC管理の標準的な機能をフル利用できるプラン(月額500円/台程度)を選択すると仮定します。そうすると月額費用は100台 × 500円 = 50,000円となります。年間では600,000円(60万円)です。加えて初期費用が仮に30,000円かかったとすれば、初年度合計は約630,000円となります(いずれも税抜きベース)。この程度の予算であれば、中堅企業のみならず中小企業でも十分手が届く範囲ではないでしょうか。
もちろんサービスによって価格は上下します。例えば高機能なSkySeaクラウド版だと100台時の月額費用がもう少し高め(目安: 月額約15万円前後)になる可能性があります。一方でSS1クラウドなどコストパフォーマンスに優れたツールでは100台でも年間数十万円台に収まるケースもあるでしょう。オプション機能を追加すれば費用増となりますが、逆に「ログ長期保存は不要」など外せるものは省いて安価なプランにすることも可能です。
また、オンプレ型で100台分のライセンスを購入する場合との比較では、初年度はクラウドの方が安く済むケースが多いです。オンプレだとサーバー費用や保守費が別途かかりますし、管理者の運用工数も費用換算すれば馬鹿になりません。クラウドITAMなら初年度60~100万円程度、以降毎年同程度の支出で最新環境を維持できるイメージです。自社の資産台数に照らして、何年でオンプレとの差額がペイするか(TCO比較)を試算すると判断材料になるでしょう。
導入ステップと移行のポイント:失敗しない手順書
現状台帳のデータ移行
クラウド型IT資産管理ツール導入の第一歩は、現状の資産台帳データを新システムへ移行することです。多くの企業ではExcelや既存ツールで管理してきた資産リストがあるため、これをクラウドITAMに取り込む作業が発生します。移行時のポイントは次の通りです。
項目のマッピング: 現在の台帳項目(資産番号、ホスト名、ユーザー名、設置場所、購入日など)を洗い出し、新ツールのデータ項目と対応付けます。ツールによって項目名や構造が異なるため、事前にインポート用テンプレートなどを確認しましょう。必要に応じてExcel側の列を並べ替えたり、不要データを整理します。
データクレンジング: 古い台帳には重複や誤記入が含まれていることがあります。移行前に一度棚卸しを行い、最新かつ正確な情報に更新しておくとスムーズです。「廃棄済みだが台帳に残っている資産」「担当者不明のPC」なども、この機会に整理しましょう。
インポート実施: ツールが提供する一括インポート機能(CSVアップロード等)を使ってデータを投入します。テスト的に数件流し込んでうまく項目が入るか確認し、その後全件を移行します。不整合エラーが出た場合は原因を突き止め修正します。
検証: インポート後、新システム上で資産一覧を開き、件数や重要項目が正しく移行されたかチェックします。抜け漏れがあれば追加投入し、ここで台帳情報の正確性を担保します。
移行作業はベンダーのサポート範囲に含まれる場合もあるため、可能なら導入支援サービスを積極的に活用しましょう。専門スタッフに相談しながら進めれば、手戻りなく確実にデータ移行が完了できます。
権限設計・アクセス制御
新しいクラウドITAMを導入したら、誰がどの範囲までシステムを操作できるかを適切に設定することが重要です。これは権限設計・アクセス制御のステップにあたります。
まず、社内でIT資産管理ツールを利用するユーザーを洗い出します。一般的には、情報システム部門の担当者が管理者権限を持ち、人事・総務など連携部門が閲覧専用権限を持つ、といった形になります。管理者アカウントは必要最小人数にとどめ、不用意に多くの人が設定変更できないようにします。次にシステム上でユーザー登録を行い、ロール(役割)ごとに権限を割り当てます。例えば「全社の資産を閲覧・編集できる管理者」「自部門の資産だけ閲覧できる部門担当者」など役割を作成し、アカウントに適用します。
加えて、ログイン認証の強化も不可欠です。シングルサインオン(SSO)連携や多要素認証(MFA)の有効化に対応しているツールであれば、ぜひ有効にしましょう。特にクラウドサービスはインターネット経由でアクセスできるため、MFAによって不正ログインリスクを大幅に低減できます。また初期状態のデフォルトパスワードは必ず変更し、アクセス可能IPアドレス制限などの機能があれば併せて設定します。
最後に、データアクセス権限も見直します。例えば資産台帳のCSVエクスポート機能は管理者のみに許可し、一般ユーザーには操作ログ閲覧のみ許可する、といった細かな制御を行います。自社のセキュリティポリシーに沿って設定を最適化し、初期設定のまま使い始めないことが重要です。以上のように権限と認証をしっかり設計すれば、導入後の運用を安全・円滑にスタートできます。
(補足)なお、新ツール導入に伴い運用ルールの整備も必要です。例えば「資産情報の更新はどういうフローで行うか」「棚卸し結果の社内展開方法」などを文書化し、関係者に周知しましょう。加えて従業員全体にも、新管理ツール導入の目的や変更点を説明して協力を仰ぐことが成功のカギです。
事例で見る導入効果:工数40%削減した企業の声
製造業A社:工数40%削減
A社(製造業、従業員500名規模)では、全国に点在する工場・営業所のPC約800台を情報システム部門の2名で管理していました。以前は各拠点の担当者にExcel台帳を更新してもらい、それをメールで集約するという方法を取っていましたが、データのとりまとめや整合性チェックに多大な工数がかかっていました。さらにソフトウェアライセンスの棚卸しでは、人手でインストール数を数えて回る必要があり、担当者は「台帳管理だけで手一杯」という状況でした。
そこでA社はクラウド型IT資産管理ツールを導入し、管理プロセスを大幅に効率化しました。まず全PCにエージェントを配布して自動インベントリ収集を実施。常に最新の資産情報がクラウド上で一元管理できるようになり、年2回行っていた手作業棚卸し業務は不要に。ソフトウェアライセンス管理も自動化され、手作業比で40%の工数削減を達成しました(棚卸し準備・集計の時間が月10時間→月6時間に短縮)。また、クラウド管理に切り替えたことで本社から全拠点の端末をリモート監視できるようになり、各拠点への問い合わせ対応や現地出張が激減しました。結果として情報システム担当者は浮いた時間を他のIT戦略業務に充てられるようになり、社内からも「対応が早くなった」と評価されています。
担当者のコメント: 「Excel台帳時代はデータ集計と確認作業に追われ、本来やりたい改善策に手が回りませんでした。クラウドITAM導入で資産管理が格段に楽になり、漏れもなくなりました。システム投資のROIが明確に出ています。」
ITベンチャーB社:SaaS可視化
B社(IT系スタートアップ、従業員100名規模)では、エンジニアを中心に多数のクラウドサービスを活用していました。開発ツールやプロジェクト管理、営業支援SaaSなど部署ごとに導入されていましたが、社内で誰がどのサービスのアカウントを持っているかが把握しきれておらず、「シャドーIT」が懸念される状況でした。ある時、退職した社員が個人で契約したクラウドストレージに機密資料を保存していた事実が発覚し、経営層も含めSaaS利用の可視化と統制が急務となりました。
B社はクラウドIT資産管理ツールを導入し、まず全社員の主要SaaSアカウントを洗い出しました。Google WorkspaceやGitHub、Slackなど主要サービスとはツールをAPI連携させ、利用中のアカウント情報や最終ログイン日時を一覧化しました。これにより社内で使われているクラウドサービスが漏れなくリストアップされ、それまで存在を把握していなかったSaaSが10種類以上判明しました。併せて不要なアカウントの削除や、部署横断で重複契約していたツールの統廃合も実施。結果として年間で20%以上のSaaSコスト削減につながり、セキュリティ面でもリスク低減が図れました。
担当者のコメント: 「クラウドサービスは便利な反面、放置するとアカウント管理が崩壊します。ITAMツールのおかげで全容を掴むことができ、無駄払いも止められました。今では新しいサービス導入時は必ずIT資産台帳に登録し、運用ルールを徹底しています。」
このように、クラウドIT資産管理ツール導入により工数削減やコスト削減、可視化によるガバナンス向上などの効果が各社で報告されています。自社の課題に即したツール選定と適切な運用により、大きなROI(投資対効果)を得ることができるでしょう。
セキュリティ&ガバナンス強化の実践術
ゼロトラストとITAM連携
クラウド時代のセキュリティモデルとして注目されるゼロトラストにおいて、IT資産管理(ITAM)との連携は重要な要素です。ゼロトラストの基本原則は「何も信頼せず常に検証する」ことであり、ユーザーだけでなくデバイスも常に信頼性を検証されます。ここでクラウドITAMが果たす役割は、デバイスの状態と存在を常に最新把握することです。具体的には、ITAMツールで管理下にない未許可デバイスからのアクセスを検知しブロックしたり、デバイス側のセキュリティパッチ適用状況と連動してアクセス権限を動的に制御したりといった運用が考えられます。
例えばAzure ADやOktaなどのIDaaS(Identity as a Service)とITAMが統合されていれば、従業員IDに紐づく端末情報をリアルタイムで参照し、「社内登録された端末からのみシステムアクセスを許可する」ポリシーを適用できます。万一紛失・盗難したPCがあれば、ITAM経由でその端末のIDを失効させネットワークから隔離することも可能です。またクラウドITAM上で取得する操作ログやSaaS利用ログを分析することで、通常と異なる振る舞いを検知しIAM(Identity & Access Management)側でセッションを強制終了させるといった高度な対応も実現できます。
要するに、ITAMとIAMを融合させることでゼロトラストの理念を具現化し、ユーザー・デバイス両面からの強固なセキュリティ対策が可能になります。クラウドITAM導入時にはぜひID管理/認証基盤との連携オプションも検討し、「正しい人が正しい端末でのみアクセスできる」仕組みを構築しましょう。これによりリモートワーク下でも安全なIT利用環境を維持でき、内部不正やサイバー攻撃のリスク低減につながります。
監査レポート自動生成
ITガバナンス強化の観点で見逃せないのが、各種監査に対応するレポートを自動生成できるクラウドITAMの活用です。情報システム部門にとって、内部監査やソフトウェアライセンス監査、ISMS/ISO27001の審査対応は大きな負担ですが、IT資産管理ツールを使えば必要情報を瞬時に取り出すことが可能です。
例えばソフトウェアライセンス監査では、「全PCの特定ソフトウェアのインストール数一覧」「ライセンス購入数との比較レポート」などを提示する必要があります。クラウドITAMがあれば、管理画面からワンクリックで最新のインストール台帳やライセンス過不足レポートを出力できます。また内部統制の証跡として、「過去◯ヶ月分のUSBメモリ使用ログ」「管理台帳の更新履歴」等もツール上に蓄積されており、そのままCSVやPDFで監査担当に提供できます。ある企業ではISMS定期審査の際、ITAMツールの操作ログ画面をその場で auditor(審査員)に見せ、PC操作履歴やアクセス権設定状況を実証してスムーズに合格できた例もあります。
さらに、多くのクラウドITAMには定型レポート機能があり、資産状況・ライセンス遵守率・セキュリティパッチ適用率などをグラフ付きでレポート化してくれます。これらを定期的に経営層や監査部門に提出すれば、ITガバナンスの「見える化」と説明責任を果たすことができます。監査対応に追われていた担当者も、自動レポートのおかげで準備工数を大幅に削減できるでしょう。
このようにクラウドITAMは、単なる資産台帳管理に留まらず経営視点での内部統制ツールとしても有効です。IT資産管理の徹底ぶりを社内外に示すことで、組織全体のITリスクマネジメント水準を底上げできます。
クラウドIT資産管理でDXを加速させよう
クラウド型IT資産管理は、単にIT担当者の業務効率を上げるだけでなく、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を下支えする重要な基盤となります。IT資産を適切に可視化・最適化することで、無駄なコストを省き、その分のリソースを新たなデジタル投資に振り向けることが可能になります。また、煩雑な台帳管理や保守作業からIT部門を解放することで、戦略的なIT企画やデータ活用に人材をシフトできるのも大きなメリットです。現代のビジネスではスピード感あるIT活用が求められますが、クラウドITAMを導入すれば環境整備にかかる時間を大幅に短縮でき、新サービスの展開や働き方改革にも素早く対応できます。
さらに、クラウドITAM導入そのものが社内のデジタル化推進の一環となり、従業員のITリテラシー向上や業務改革への意識醸成につながります。「Excel台帳からクラウドツールへの移行」はDXのわかりやすい成功体験となり、他の業務領域のクラウド化・効率化にも良い波及効果をもたらすでしょう。
最後に強調したいのは、クラウドIT資産管理は導入して終わりではなく、継続的な活用と改善が重要という点です。定期的にレポートを分析し、運用ルールを見直し、ツールの新機能も取り入れながらPDCAを回すことで、その価値は時間とともに高まっていきます。IT資産という企業の土台をクラウドでしっかり管理することは、これからの時代のビジネス変革を力強く支える鍵となるでしょう。ぜひクラウド型IT資産管理を活用し、貴社のDXを加速させてください。