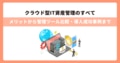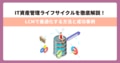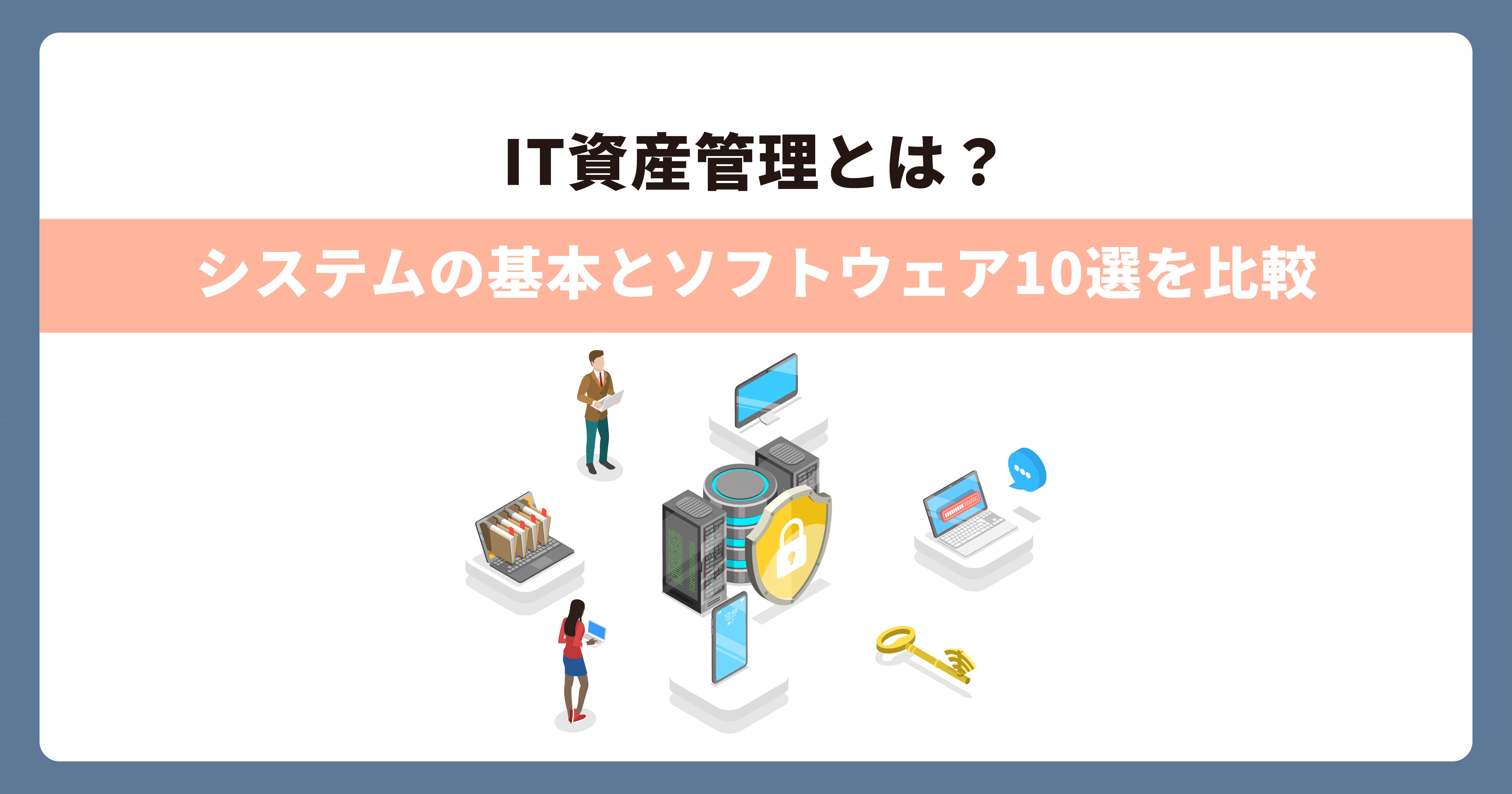
IT資産管理とは?IT資産管理システムの基本とIT資産管理ソフトウェア10選を比較
近年、テレワークやクラウドサービスの普及により、企業が管理すべきIT資産はますます多様化・分散化しています。PCやサーバーといった物理資産だけでなく、ソフトウェアライセンスやクラウド契約、さらにはシャドーITまで、目の届きにくい“見えない資産”の存在が、情報漏洩やライセンス違反といった新たなリスクを生み出しています。
こうした課題に対応する手段として、注目を集めているのが「IT資産管理システム」です。IT資産を一元管理し、セキュリティ強化・コスト削減・コンプライアンス対応を同時に実現するツールとして、多くの企業が導入を進めています。
本記事では、IT資産管理の基本からシステム導入の流れ、おすすめソフトの比較ランキングまでを網羅的に解説します。自社に合った管理体制の構築にお役立てください。
目次[非表示]
- 1.IT資産管理とは?
- 2.IT資産管理システムがなぜ今必要とされるのか?
- 3.IT資産管理システムの基本構成と機能とは?
- 3.1.インベントリ管理機能(資産の自動収集・更新)
- 3.2.ライセンス管理機能(ソフトウェアの正当使用)
- 3.3.ログ・使用状況監視機能(操作履歴や稼働状況の可視化)
- 3.4.情報一元化とダッシュボードの活用
- 4.IT資産管理システム導入の流れ【5ステップ】
- 4.1.STEP1:自社課題の洗い出しと要件定義
- 4.2.STEP2:システムの選定と試験導入
- 4.3.STEP3:全社展開と運用ルールの整備
- 4.4.STEP4:台帳の統一・インベントリ連携の構築
- 4.5.STEP5:改善と定期棚卸しサイクルの確立
- 5.2025年版IT資産管理ツールランキング【比較表あり】
- 6.IT資産管理システムの運用改善ポイント
- 7.最適なIT資産管理システムで効率と安心を両立しよう
IT資産管理とは?
IT資産管理とは、企業が保有するすべてのIT関連資産(ハードウェア、ソフトウェア、その利用権であるライセンス、クラウドサービスなど)を適切に把握し管理することです。
パソコンやサーバーなどの物理機器から、OSや業務アプリケーション、クラウドサービスの契約情報に至るまで、IT資産は企業活動を支える重要なリソースとなっています。そのため、オフィスの設備や不動産と同様に、IT資産も継続的な管理と最適化が必要です。
近年ではセキュリティ強化、コスト削減、コンプライアンス遵守といった観点からIT資産管理に取り組む企業が増えており、単なる台帳管理にとどまらずソフトウェア資産管理(SAM)やセキュリティ対策まで含めた包括的な活動として重要性が高まっています。
IT資産管理システムがなぜ今必要とされるのか?
現代のビジネス環境においてIT資産管理システムが注目される背景には、大きく3つの理由があります。
クラウドやリモートワークの普及による“見えない資産”の増加、法規制強化に伴うコンプライアンス対応ニーズ、そして情報漏洩リスクの高まりに対処するための統合管理の必要性です。それぞれ詳しく見てみましょう。
クラウド・リモート時代の“見えない資産”が増加
クラウドサービスの拡大やテレワークの定着により、企業のIT資産はこれまで以上に分散化・不可視化しています。
従業員が独自に利用するシャドーITや、許可を得ていない個人デバイスの業務利用、部署ごとに契約されたクラウドサービスなど、従来の管理の目が届かない“見えない資産”が新たなセキュリティホールになりつつあります。
実際、リモートワーク増加に伴い無許可のクラウドアプリ利用や、社外へのPC持ち出しによるリスクが拡大しており、遠隔からでも資産を一元把握できる仕組みが求められています。
IT資産管理システムを導入すれば、ネットワーク上のハードウェア・ソフトウェアを自動検出して“見える化”でき、社内外に散在する資産を漏れなく管理可能です。これによりシャドーITの排除やクラウド利用状況の統制が進み、組織のセキュリティリスク低減につながります。
コンプライアンス・監査対応を支える基盤として
個人情報保護やライセンス遵守に関するコンプライアンス要件が年々厳しくなる中、IT資産管理システムは内部統制の基盤としても重要です。
例えば、EUのGDPRや改正個人情報保護法では、企業に対しデータやソフトウェア利用状況の適切な管理が義務付けられており、違反すれば法的リスクや社会的信用の低下を招きます。また、ソフトウェアライセンスに関しても、契約数を超えるインストールは著作権法違反となり得ます。
IT資産管理ツールを使って日頃からライセンス保有数と使用数を照合し、超過利用を即座に検知・是正することで、ライセンス違反の未然防止と監査対応が可能です。
さらに、IT統制の一環として操作ログや資産データをレポート出力し経営層へ定期報告する仕組みも整えやすく、内部監査や外部監査に備えた証跡管理にも役立ちます。要件遵守とガバナンス強化のために、今やIT資産管理システムは不可欠なプラットフォームとなっています。
情報漏洩や不正使用を防ぐ統合管理の必要性
サイバー攻撃の高度化や内部不正のリスク増大により、統合的なIT資産管理によるセキュリティ対策が求められています。
適切な資産管理ができていないと、例えば社内のPCに脆弱な古いソフトウェアが放置されマルウェア感染を許してしまったり、従業員が与えられた権限を悪用して機密データを持ち出すといったインシデントが発生しかねません。IT資産管理システムは、ハード・ソフトのバージョン管理を通じて常に最新のパッチ適用を促し、脆弱性悪用による攻撃リスクを低減します。
また、USBメモリの接続制限や操作ログの監視によって、許可なきデータ持ち出しや内部不正行為の兆候を検知・抑止できます。万一デバイスの紛失・盗難が起きた際も、遠隔から利用停止やデータ消去を行うことで情報漏洩を防ぐことが可能です。
このようにセキュリティ対策機能と資産管理を一元化できる点こそ、IT資産管理システムが重要視される理由です。統合管理により情報システム部門の監視網を強化し、企業全体の安心・安全を支えることができます。
IT資産管理システムの基本構成と機能とは?
IT資産管理システムには、資産のライフサイクル管理や情報の可視化を実現するために様々な機能が搭載されています。中でも中核となる基本機能として、一般的に以下のようなものが挙げられます。
インベントリ管理機能(資産の自動収集・更新)
IT資産管理システムの基本は、インベントリ情報の自動収集による資産台帳の最新化です。
エージェント(管理用プログラム)やネットワークスキャンを通じて社内のPC、サーバー、周辺機器に関する各種情報を自動取得し、データベースに蓄積します。例えば、端末のメーカー・型番、CPUやメモリ容量、インストールされているOS・ソフトウェア名とそのバージョン、IPアドレスや最終ログイン日時など、多岐にわたる項目を収集可能です。
こうした機器情報をネットワーク経由で取得・更新し続けることで、統一的な資産管理台帳を作成できます。人手によるExcel入力では抜け漏れが発生しがちですが、自動収集なら常に正確で網羅的なデータベースが維持されます。
資産台帳が一元化・最新化されていれば、「どの部署にどんなPCが何台あるか」「各端末のスペックやソフトウェア構成はどうか」といった情報を即座に把握でき、資産の重複購入防止や計画的な更新にも役立ちます。
インベントリ管理機能はIT資産管理ツールの根幹であり、これによって見える化された資産情報をもとに様々な管理業務を効率化できるのです。
ライセンス管理機能(ソフトウェアの正当使用)
ソフトウェア資産のライセンス管理も重要な機能の一つです。
IT資産管理システムでは、各ソフトウェアの購入ライセンス数や契約情報を登録し、それと実際のインストール数や利用端末を照らし合わせて管理します。
例えばOfficeやAdobe製品などライセンス数に上限があるソフトの場合、エージェントがPC上のインストール状況を検出し、許諾範囲を超えて使用されていないかをチェックします。もし保有ライセンス数以上にインストールされているソフトが見つかれば管理者にアラートを出し、即座に是正措置を取れる仕組みです。これにより契約違反や著作権侵害につながる事態を未然に防ぎます。
また、利用されず放置されたソフト(未使用ライセンス)の把握も可能なので、不要なサブスクリプションを解約してコスト削減するなど、ソフトウェア資産の最適化にも貢献します。
さらに監査対応として、ライセンス証書や購入証明書の管理機能を備える製品もあります。IT資産管理システムのライセンス管理機能を活用すれば、日頃からソフトウェア使用状況を統制し、コンプライアンス違反のリスクを大幅に低減できるでしょう。
ログ・使用状況監視機能(操作履歴や稼働状況の可視化)
多くのIT資産管理ツールには、クライアントPC上の操作ログ収集や利用状況のモニタリング機能も搭載されています。
具体的には各PCで行われた操作履歴(起動・シャットダウン時刻、ログオンユーザー情報、実行したアプリケーションやアクセスしたWebサイト履歴、ファイル操作履歴など)をエージェントが記録し、管理サーバーへ送信します。管理者は集中管理画面からこれらのログを検索・閲覧でき、社員のIT利用状況を俯瞰できます。
例えば、長時間のPC無操作によるテレワーク中のサボりや、業務に関係ないソフト使用・Webアクセスの有無をチェックしたり、内部不正の兆候を発見したりできます。また、USBメモリ等のデバイス接続ログや印刷ジョブの履歴を取得し、情報持ち出しの監視や抑止にも役立てられます。さらにシステムによってはPCの稼働率やソフト利用頻度をグラフ化し、遊休PCの発見やソフトウェアの利用実態把握にも活用可能です。
これらのログ・監視機能によりITガバナンスを強化し、問題発生時には証跡を追跡して原因究明や是正措置に迅速に繋げられます。なお個人のプライバシーに配慮しつつ適切に運用することも重要です。
情報一元化とダッシュボードの活用
IT資産管理システムは集約したデータをダッシュボード上で可視化し、管理者にわかりやすく提供します。各種資産情報(デバイス数、ソフトウェア一覧、ライセンス使用率等)やセキュリティステータス(未適用パッチ数、ウイルス定義の最新適用状況、違反端末の検知件数など)をリアルタイムに集計し、グラフや一覧で表示する機能です。
これにより「組織内の弱点やリスク箇所」が一目で把握でき、対策の優先度を判断する助けとなります。例えば、ある部署だけPCのWindows更新が遅れていれば警告を出したり、ソフトウェアのライセンス利用率が低いものを洗い出したりできます。
また、管理台帳へのインポート・エクスポート機能や他システムとのデータ連携も備えており、既存のExcel台帳から情報をまとめて移行したり、人事システムや購買システムと連携して社員異動や購入情報を反映することも可能です。
このように情報を一元管理し活用することで、IT資産全体の状況を俯瞰しながら的確な経営判断につなげられます。さらに経営層向けのレポート生成機能を活用すれば、月次の資産レポートや監査報告資料をボタン一つで作成できるなど、管理業務の省力化と精度向上が図れるでしょう。
IT資産管理システム導入の流れ【5ステップ】
IT資産管理システムを効果的に導入し定着させるには、いくつかのステップを踏んだ計画的な進め方が重要です。一般的には以下の5つのステップが推奨されます。

STEP1:自社課題の洗い出しと要件定義
まずは現状の課題を明確化し、システムに求める要件を整理するフェーズです。
現在のIT資産管理プロセスを評価し、運用上の問題点やリスクを洗い出しましょう。
例えば「資産情報の把握漏れがある」「管理工数が膨大で非効率」「ソフトウェア管理が属人的でライセンス違反の懸念がある」など、現状の課題を書き出します。同時に、経営戦略や将来のIT方針も踏まえ、理想とする管理体制や解決すべき課題を定義します。
これらをもとに導入目的を明確化し、「セキュリティ強化」「コスト最適化」「内部統制の強化」等の目標を設定します。
また、必要な機能要件も洗い出します。
主な導入目的がセキュリティ対策であればログ監視機能が重要になるでしょうし、資産台帳の整備が中心ならインベントリ収集機能を重視すべきです。自社の規模、扱う資産種別(PC台数やソフト種別)、管理体制なども考慮し、「我が社にとって必要な機能は何か」を明確に定義します。
このステップを丁寧に行うことで、後のツール選定がブレずに的確に行えるようになります。
STEP2:システムの選定と試験導入
次に、市場のIT資産管理ツールから自社要件に合致する製品を選定します。
Step1で整理した必須機能や目的に照らし、各製品の機能一覧・対応範囲を比較検討しましょう。「クラウド型かオンプレミス型か」「Windows PCだけでなくMacやスマホにも対応しているか」「ログ管理やデバイス制御などセキュリティ機能が充実しているか」「他の社内システム(例えばITサービス管理ツールや人事DB)と連携できるか」など、評価基準を設定してチェックします。
また、現在の資産数や将来の拡張を考え、対応可能な管理規模(ライセンス台数)やサーバースペック要件も確認します。いくつか候補を絞り込んだら、トライアル導入(PoC)を実施することをおすすめします。選定中のツールを実際に自社環境で一定期間使ってみて、資産情報の収集精度や操作性、レポートの使い勝手などを検証します。特に管理者画面のUIが直感的か、現場担当者でも扱いやすいかは重要です。
また、パイロットユーザーを選び、負荷テストや他システムとの連携テストも行いましょう。試験導入の結果を踏まえ、最終的に自社に最適なシステムを選定し、正式契約へと進めます。
STEP3:全社展開と運用ルールの整備
正式に導入するシステムが決まったら、いよいよ全社展開の段階です。
まずはサーバーやクラウド環境を構築し、エージェントプログラムを全PCやサーバーに配布・インストールします。可能であればソフト配布機能やログインスクリプトを活用して一斉配布し、短期間でエージェント導入を完了させます。
加えて、実運用に入る前に社内の運用体制・ルールを整備することが極めて重要です。具体的には、情報システム部門内で「IT資産管理責任者」や各部署のIT資産担当者を明確に任命し、役割と権限を定義します。
そして、その責任者を中心に、総務・経理・各事業部門を巻き込んだ部門横断的な連携体制を構築します。例えば、新入社員のPC手配は総務から情シスへ連絡、廃棄時は経理に減価償却処理を共有、など部署間の協力がスムーズに行くようワークフローを定めます。
また、台帳更新のタイミング(増減資産の登録ルール)やログ閲覧権限の範囲、棚卸し実施サイクル、インシデント時の報告フローなど、社内ポリシーを文書化して展開します。導入時にきちんとルールを決め教育しておけば、担当者変更時も混乱が少なく、システムが有効活用され続けるでしょう。
STEP4:台帳の統一・インベントリ連携の構築
システム稼働開始後は、既存の資産台帳や管理データを新システム上に統合していきます。
もし従来Excelや他ソフトで資産台帳を管理していた場合は、インポート機能を使ってデータを一元化しましょう。これにより社内の資産情報ソースを一本化し、「この情報はExcel、あの情報は別システム」といった分散状態を解消します。
さらに、インベントリ自動収集との連携を強固にすることがポイントです。
例えば、資産管理台帳とインベントリ情報の紐付けを行い、物理資産ごとに自動取得される情報(機器名・スペック・搭載ソフトなど)を台帳項目に反映させます。これにより資産台帳が常に最新の情報で更新され、手動更新の手間やミスが削減されます。
また、PC以外の資産、例えばネットワーク機器やスマートフォン、USBメモリ等についても、可能な範囲でインベントリ収集やバーコード管理を導入し、抜け漏れを防ぎます。社内に複数存在する管理台帳(固定資産台帳やリース管理表など)がある場合も、IT資産管理システムに集約・連携させて「一本の台帳」として管理する仕組みを構築します。
こうして統一された資産データベースができれば、以降の定期棚卸しや更新作業はシステム上でシームレスに実施でき、属人的な管理から脱却できます。
STEP5:改善と定期棚卸しサイクルの確立
導入後は、それで終わりではなく継続的な改善と運用サイクルの定着が重要です。
まず、導入初期に想定していなかった課題や新たなニーズが出てきた場合、定期的に運用体制や設定を見直し改善していきます。例えば、収集データ項目の追加やレポート項目の変更、社内ルールの微修正などを行い、運用品質を向上させます。
また、システム導入効果を最大化するため、定めたサイクルでの定期棚卸し(資産監査)も欠かせません。
半年または年度ごとに各部署で現物資産の所在確認を行い、システム上の台帳データと照合します。バーコードやRFIDを活用すれば短時間で棚卸しでき、未回収機器や滞留ソフトライセンスを洗い出せます。棚卸し結果を次の運用改善にフィードバックし、「使われていないPCは回収する」「不要ソフトはアンインストールする」など継続的な最適化サイクルを確立します。
さらに、ツール利用に慣れた担当者が異動・退職した場合に備え、ナレッジの蓄積と引き継ぎも計画しましょう。
以上のようにPDCAを回すことで、IT資産管理システムは単なるソフト購入に終わらず組織に根付き、長期的に効率化とリスク低減をもたらしてくれるのです。
2025年版IT資産管理ツールランキング【比較表あり】
ここでは2025年時点で注目されるIT資産管理ツール10選を紹介します。
オンプレミス型からクラウドサービス型まで国内外の代表的なソフトウェアをピックアップしました。それぞれ特徴や強みが異なるため、自社のニーズに合わせて比較検討しましょう。以下の表に主要項目をまとめます。
製品名 |
提供形態 |
対応OS・デバイス |
特徴・強みの概要 |
|---|---|---|---|
オンプレミス / クラウド |
Windows PC, Mac, モバイル |
エージェントレス対応 / WebベースITAM / 資産ライフサイクル全般を網羅 / 手頃な価格で中小~大企業まで導入実績 |
|
オンプレミス |
Windows PC, Mac(一部機能) |
国内導入トップクラス / 資産+ログ監視+デバイス制御 / 内部統制に強み / 操作性◎ |
|
クラウド(SaaS) |
Windows PC, Mac 他(現物資産管理) |
PC〜什器まで一元管理 / バーコード・RFID棚卸し / 固定資産台帳と連携 / 棚卸し工数を大幅削減 |
|
オンプレミス / クラウド |
Windows PC, Mac, モバイル |
ITAM+エンドポイント+パッチ管理を統合 / CMDB連携 / グローバル19,000社導入 |
|
オンプレミス |
Windows PC (多言語対応) |
資産・ログ・パッチを一括管理 / 1万台超対応の高いスケーラビリティ / グローバル運用・多言語UI |
|
クラウド(SaaS) |
Windows PC, Mac 他(情報連携) |
ITSM/CMDBとシームレス連携 / 資産ワークフロー自動化 / コストとリスクの可視化 |
|
オンプレミス / クラウド |
Windows PC, Mac, モバイル |
資産+操作ログ+脅威対策を統合 / USB制御・Web制限 / 日本企業向けUI |
|
クラウド(SaaS) |
Windows PC, Mac 他(データ連携) |
SAM・クラウドコスト最適化に特化 / 多ベンダーライセンス管理 / 監査対応に定評 |
|
オンプレミス/クラウド |
―(固定資産台帳) |
中小企業向け / 固定資産・減価償却に特化 / 弥生会計と連携し帳簿仕訳を自動化 |
|
クラウド/オンプレミス |
Mac(macOS)・iOS |
Apple専用MDM / キッティング自動化・App配布 / 「脱AD」運用を支援 |
(注)表中「提供形態」はソフトの導入形態、「対応OS・デバイス」は管理対象として公式サポートされるクライアントOS/機器種別を示します。一部製品でMac対応が限定的である旨はで記載しています。
上記のように、それぞれのツールは特色があります。
例えば「とにかく網羅的なIT統制機能が欲しい」ならSKYSEAやLanScope、MCoreなど国内オールインワン型が候補になりますし、「ソフトウェアライセンス管理やクラウドコスト管理を重視したい」ならFlexera OneのようなSAM特化型が適しています。
また「Macを多用する環境」ではJamf Pro+他ツール併用、「既存ITSMに組み込みたい」ならServiceNow、「低コストで基本機能を抑えたい」ならManageEngine、といった選び方ができるでしょう。自社の規模・目的に合わせて最適なソフトを選定してください。
IT資産管理システムの運用改善ポイント
IT資産管理システムは導入して終わりではなく、運用を定着・改善させて初めて真価を発揮します。ここでは、システム導入後に特に留意すべき運用改善のポイントを紹介します。
導入して終わりにしないための運用体制づくり
せっかくIT資産管理ツールを導入しても、運用体制が不十分だと活用しきれず形骸化してしまう恐れがあります。そうならないために、人とプロセスの整備を継続しましょう。
まず、組織内でツール運用の責任者・担当者を明確に定め、異動や退職で担当者が交代してもスムーズに引き継げるようマニュアルや運用フローを整備します。
また、ツール自体が使いにくい場合、担当者交代時に十分な引き継ぎができず運用品質が低下する懸念もあります。そのため、日頃から操作研修や教育も実施し「誰が使っても使いこなせる」状態を目指します。
さらに情報システム部門だけで完結せず、他部門との協力体制も継続的に築きましょう。
総務・人事からの人員情報提供、現場部門での棚卸し協力など、部門横断でIT資産管理に取り組む文化を根付かせることが大切です。トップマネジメントにも定期レポートで状況を共有し、全社でIT資産管理の重要性を認識することで、組織ぐるみでの運用体制が強化されます。
更新・棚卸しの自動化で継続的な管理を実現
IT資産管理を継続的に有効活用するには、定型作業の自動化を推進して担当者の負担を減らすことがポイントです。
資産情報の更新や棚卸し作業を可能な限りツールに任せ、人手によるミスや抜け漏れを防ぎます。具体的には、インベントリ自動収集機能によりPCの増減やスペック変更をリアルタイムに台帳へ反映させます。ソフトウェアのアップデートも一斉配布機能で自動化し、古いバージョン放置を防止します。
また、定期棚卸しにはモバイルアプリやバーコード読み取りを活用し、手作業でシリアル番号を照合する手間を省きましょう。Excel台帳では入力漏れ・誤記入が発生し管理目的を達成できなくなる恐れがありますが、ツールで情報収集を自動化すればそうしたミスを大幅に削減できます。
さらに、データ収集からレポート作成までをスクリプトやジョブで定期実行し、毎月の資産レポートを自動生成するといった工夫も有効です。自動化により担当者は煩雑な入力作業から解放され、例外対応や分析といった付加価値の高い業務に注力できます。「ツールに任せるところは任せ、人が判断・改善するところに注力する」体制を整えることで、長期間にわたって効率的な管理を持続できるでしょう。
他部門との連携でガバナンスと全社最適を強化
IT資産管理は情報システム部門だけで完結するものではなく、全社的な協力があってこそ最大の効果を発揮します。他部門との連携を深め、組織全体でのITガバナンス強化と最適化を目指しましょう。
例えば、購買部門とはPCやソフト調達時に必ず情シス台帳へ登録するワークフローを共有します。
人事部門とは入社時の機器手配・退社時の機器回収のプロセスを連動させます。現場の各部門には定期棚卸しやソフト利用状況ヒアリングに協力してもらい、現物確認や不要資産の報告フローを作ります。
このように部門横断的な資産管理体制を築くことで、属人的・縦割りの管理を排し、会社全体で統制の取れた運用が可能になります。
また、他部門から上がってくる現場の声(「このソフトは使われていない」「この端末は性能不足だ」など)を資産管理担当が集約し、資産配分の見直しや無駄コスト削減に役立てることもできます。経営層には全社視点でのIT資産の状況・ROIを報告し、投資判断の材料として提供します。
こうした全社的な連携によって、IT資産管理が企業全体の最適化サイクルの一部となり、結果的にガバナンス強化とビジネス価値向上の両立が実現できるのです。
最適なIT資産管理システムで効率と安心を両立しよう
IT資産管理は、単なる在庫管理ではなく「企業のITリソースを最大限に活用しリスクを抑える」戦略的な取り組みです。クラウド時代の見えにくい資産を可視化し、コンプライアンスとセキュリティを維持しながらコスト最適化を図る――その実現には、自社に合ったIT資産管理システムの導入と定着が欠かせません。
幸い現在は用途や規模に応じた様々な優れたツールが市場に揃っており、本記事で比較したように特徴も多彩です。ぜひ自社の課題にマッチするシステムを選び、紹介したステップに沿って導入・運用してください。最適なIT資産管理システムを活用すれば、煩雑だった管理業務は効率化され、「見えていなかったリスクが見える化される安心感」を得ることができます。
情報システム部門の負荷軽減とガバナンス強化を同時に達成し、企業のIT活用を次なるステージへと進化させていきましょう。効率と安心を両立したIT資産管理体制の構築が、これからのDX時代における競争力の土台となるのです。