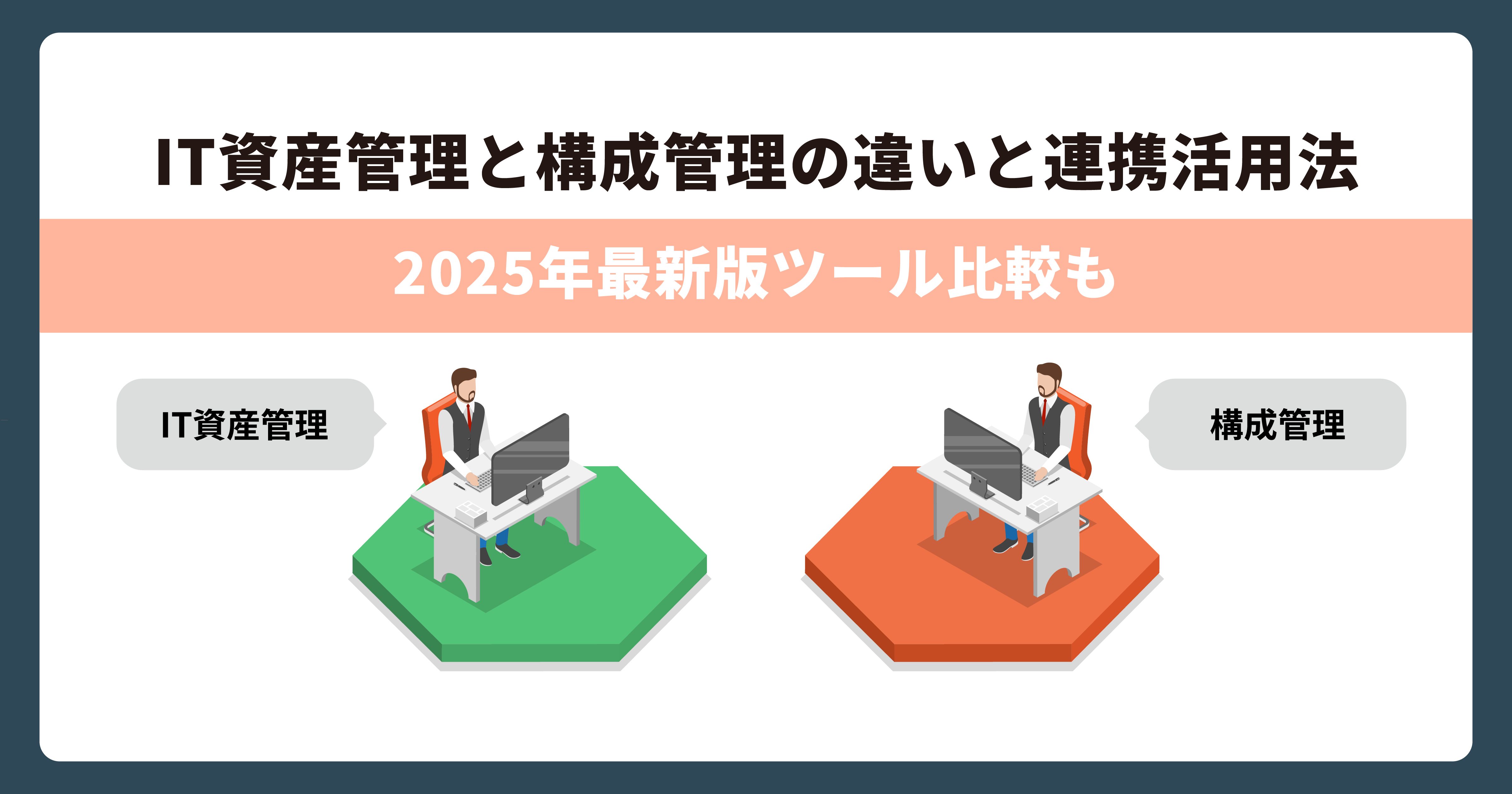
IT資産管理と構成管理の違いと連携活用法|2025年最新版ツール比較も
近年、ITサービスの複雑化やリモートワークの普及によって、IT資産管理と構成管理の重要性がますます高まっています。これらは一見似ていますが、管理の目的や対象が異なり、双方をうまく連携させることで大きな効果を発揮します。
本記事では、IT資産管理と構成管理の定義や違いを解説し、両者を組み合わせるメリットや導入ステップ、最新ツール動向まで詳しく紹介します。2025年時点の最新情報を踏まえ、自社のIT運用改善に役立ててください。
目次[非表示]
- 1.IT資産管理とは?
- 2.構成管理とは?
- 3.IT資産管理と構成管理の違い
- 4.IT資産管理と構成管理を連携させる3つのメリット
- 5.IT資産管理・構成管理ツールを選ぶポイント
- 6.2025年おすすめのIT資産管理・構成管理ツール
- 7.IT資産管理・構成管理の導入ステップと一元管理のコツ
- 7.1.現状の資産と構成を正確に棚卸しする
- 7.2.導入の目的と管理対象を明確に定義する
- 7.3.情報整理とツール要件をドキュメント化する
- 7.4.段階的にPoC(検証環境)を導入する
- 7.5.一元管理を実現する運用ルールを設計する
- 7.6.導入後の定着・改善プロセスを設ける
- 8.構成管理を高度化するCMDB活用ガイド
- 8.1.CMDBとCI設計のキモ
- 8.2.自動ディスカバリとデータ品質管理
- 9.IT資産管理×構成管理の成功事例
- 10.IT資産管理と構成管理を連携し、継続的な運用改善へつなげよう
IT資産管理とは?
IT資産管理とは、企業内にあるPC・サーバー・スマホなどのデバイスや、ソフトウェア・ライセンスといった「IT資産」を一元的に管理・運用することを指します。具体的には、これらIT資産の利用状況や契約情報、ライフサイクル(調達から廃棄まで)を把握し、適切に管理します。IT資産管理の主な目的は、セキュリティ強化や情報漏洩対策、コンプライアンス遵守、そしてコスト最適化です。
例えば未使用のソフトウェアライセンスを把握して重複購入を防いだり、端末のパッチ適用状況を管理して脆弱性からの攻撃リスクを減らすなど、IT資産管理は安全で効率的なIT運用の土台となります。
構成管理とは?
構成管理とは、ITサービス提供に必要な構成アイテム(Configuration Item、CI)を管理するプロセスです。サーバーやOS、ネットワーク設定、ソフトウェア、さらには契約書や手順書といったドキュメントまで、ITサービスを構成するあらゆる要素がCIに含まれます。
構成管理では、各CIの状態や関係性を把握し、ITサービス全体が安定して稼働するようコントロールします。例えば複数のサーバーが同一の構成で動作している場合、構成管理上はそれらをひとまとめのCIとして扱うことも可能です。構成管理の目的は、ITサービスの効率的な提供と変更・障害発生時のビジネス影響の最小化にあります。
構成管理に欠かせないCMDBの基礎
構成管理を語る上で欠かせないのがCMDB(構成管理データベース)です。CMDBとは、組織内のIT資産およびITサービスの構成要素に関する情報を一元管理するデータベースのことです。CMDBにはCIの属性情報(名前、バージョン、場所、オーナー、稼働状態など)や、CI間の関連性(依存関係や影響範囲)が登録されます。
これにより「どのIT資産がどのサービスに紐づいているか」「あるサーバーの障害が他システムに与える影響は何か」といった点を迅速に把握できます。CMDBはITサービスマネジメントの中核を担う仕組みであり、インシデント管理や変更管理と連携して構成管理の効果を最大化します。
IT資産管理と構成管理の違い
IT資産管理と構成管理は管理対象が重なる部分もありますが、目的と視点が異なる点に注意が必要です。IT資産管理が社内のあらゆるIT資産を対象に、利用者・場所・コストなどライフサイクル全般の情報を管理するのに対し、構成管理はITサービス運用に必要な構成要素に注目し、システムとしての状態を管理します。
例えば、導入前のソフトウェアライセンスや稼働していない予備機器はIT資産管理の範囲に含まれますが、構成管理の範囲外です。一方で構成管理では、サービス自体やクラウド上のインスタンスなどもCIとして管理対象に含め、各要素間の関連性まで考慮します。
また、IT資産管理では同じ型番のPC10台は「10台の資産」として扱いますが、構成管理では構成が同一なら「1つのシステム構成」として扱えることも特徴です。このように視点の違いはありますが、いずれも組織のITリソース情報を扱う点で密接に関連しており、両者を統合的に運用することが重要です。
IT資産管理と構成管理を連携させる3つのメリット
IT資産管理(ITAM)と構成管理(CM)の仕組みを組み合わせて活用することで、単独では得られない相乗効果が生まれます。ここでは、ITAMとCMを連携させる主なメリットを3つ取り上げます。
コスト最適化
IT資産と構成情報を結びつけて管理することで、重複投資の削減や利用状況に応じた最適なリソース配分が可能になります。例えば、CMDBによって全IT資産の関係性を可視化することで未使用の機器やソフトウェアを発見し、ライセンス数やデバイス台数を適切に見直せます。
また、資産管理ツールと構成管理ツールを連携させておけば、購入から配備、運用、廃棄に至るライフサイクル全体で必要以上のコストがかかっていないか継続的にチェックできます。ITAM×CMの連携によりコストのムダを徹底排除し、IT投資の最適化が実現できるのです。
リスク低減
IT資産管理と構成管理を連携すると、セキュリティやコンプライアンス上のリスク低減にも直結します。資産台帳と構成情報を紐づけることで、管理対象外の「シャドーIT」や未登録デバイスを洗い出しやすくなり、漏れなくセキュリティ対策を適用できます。
例えば、全端末のソフトウェア構成情報をCMDBで把握しておけば、脆弱性を抱えたアプリケーションがインストールされた端末も容易に特定可能です。ライセンス管理の面でも、誰がどのソフトを使っているかを可視化できるため、不正インストールの抑止や契約違反の未然防止に効果を発揮します。このように、ITAMとCMのデータを一元化することでセキュリティ・法令遵守の抜け漏れを防ぎ、ITリスクを大幅に低減できます。
可視化強化
IT資産管理と構成管理を統合すると、組織内のIT環境を俯瞰できる可視化基盤が強化されます。従来、資産台帳だけでは把握しづらかった「資産と資産の関係性」や「サービス全体での構成」が見えるようになるため、経営層や他部門への説明もしやすくなります。例えば、あるシステム障害がどの事業部に影響を与えるかを、CMDB上の関係マップで示すことが可能です。
また、資産管理の観点からも、台帳情報とリアルタイムの構成情報を付き合わせてダッシュボード化することで、IT資産の利用状況や健全性を常に見える化できます。こうした統合可視化により、属人的になりがちなIT管理を脱却し、誰でも現状を把握できる体制を築ける点も大きなメリットです。
IT資産管理・構成管理ツールを選ぶポイント
IT資産管理ツールや構成管理ツールを導入する際は、自社のニーズに合った製品を選定することが重要です。ここでは、ツール選びで押さえておきたいポイントを解説します。
導入目的に応じた選定基準を押さえる
まずはツールを導入する目的を明確にしましょう。その上で必要な機能要件を洗い出し、要件を満たすツールを選定することが大切です。例えば、「ソフトウェアライセンスの違反を防ぎたい」が目的ならライセンス管理機能に優れたツールを、「インシデント影響範囲をすぐ把握したい」が目的ならCMDB機能を持つITSMツールを選ぶ、といった具合です。
また、製品によってはオールインワンで多機能なものもあれば、必要機能だけモジュール追加できるものもあります。自社に不要な機能まで含めるとコスト増につながるため、目的に照らして必要十分な機能を持つツールを選びましょう。さらに操作性やサポート体制も確認ポイントです。事前にデモやトライアルを活用して使い勝手を検証し、ベンダーのサポート品質も含めて比較検討することが望ましいです。
クラウド型かオンプレ型かを明確に判断する
ツール提供形態がクラウド型かオンプレミス型かも重要な選択基準です。クラウド型はベンダー側のクラウド環境でサービスを提供するため、サーバー設置やメンテナンスの手間がかからず、インターネット経由で社外の端末も管理できる利点があります。初期費用が抑えられ、スピーディーに導入できる点も魅力です。
一方、オンプレミス型は自社内にサーバーを置いて運用する方式で、閉じたネットワーク環境でも利用でき、データ保管先を自社でコントロールできる安心感があります。ただしオンプレ型では社内ネットワーク外の端末は原則管理できないため、テレワークで持ち出されるPCが多い場合はクラウド対応が不可欠です。自社の利用シーンを想定し、クラウドとオンプレのどちらが適切かをあらかじめ明確にしておくことが、ツール選定の重要なステップとなります。
2025年おすすめのIT資産管理・構成管理ツール
それでは、2025年時点で注目のIT資産管理・構成管理ツールを見てみましょう。機能や価格帯、得意分野の観点から代表的なサービスをピックアップします。
ツール名 |
提供形態 |
主な機能・強み |
価格帯(参考) |
こんな企業におすすめ |
|---|---|---|---|---|
クラウド & オンプレ |
資産自動収集、マルチ OS (Mac/iOS/Android) 対応、脆弱性パッチ配布、リモート制御など |
要問い合わせ(端末数ライセンス) |
国内拠点が多くモバイル端末も統合管理したい中堅〜大企業 |
|
クラウド & オンプレ |
使いやすい UI、詳細ログ監視、デバイス制御、情報漏えい対策 |
例:100台 ≈ 119万 円(買切) |
セキュリティ重視・内部統制を強化したい企業 |
|
クラウド & オンプレ |
顧客満足度 No.1、操作が直感的、資産+ログ+デバイス制御を統合 |
要問い合わせ(サブスク & 買切) |
コストパフォーマンスとサポート重視の中堅企業 |
|
クラウド & オンプレ |
資産管理+操作ログ+遠隔削除、機能をモジュール選択可能 |
要問い合わせ(モジュール課金) |
機能を段階導入したい多拠点企業 |
|
オンプレ(Windows/Linux) |
低コスト買切、ソフト/ハード資産・ライセンス・契約管理を一元化 |
無料版〜買切ライセンス |
オフライン環境やコスト重視の中小〜中堅 |
|
クラウド |
ITSM+ITAMを統合、AI自動化(Freddy Copilot)、モバイル CMDB |
月額サブスク(要見積もり) |
ITSMも同時刷新したい中小〜中堅 |
|
クラウド |
大規模向けエンタープライズ機能、強力なワークフローとCMDB |
高価格帯(ユーザー課金) |
グローバル拠点を持つ大企業・ITIL準拠 |
|
自社ホスティング(OSS) or マネージドクラウド |
オープンソースで無償、REST APIで自由連携、ホステッド版も低価格 |
OSS:無料/ホステッド:月$40〜 |
カスタマイズ重視・DevOps文化の企業/スタートアップ |
IT資産管理・構成管理の導入ステップと一元管理のコツ
IT資産管理や構成管理を自社に根付かせるには、計画的な導入と運用設計が欠かせません。以下のステップで段階的に進めると効果的です。それぞれの段階でのポイントも押さえて、一元管理の仕組みを構築しましょう。
現状の資産と構成を正確に棚卸しする
まず最初に、現状のIT資産および構成要素をもれなく洗い出すことから始めます。ハードウェア台帳やソフトウェアのインストール状況、ネットワーク図面、クラウドサービス利用状況など、各方面に散在する情報を集約し、一覧性のある形に整理しましょう。Excelや既存の資産管理台帳があれば活用し、不明点は現場へのヒアリング等で補います。現状把握を厳密に行うことで、後続のステップで見落としを防ぎ、的確なツール要件定義につなげられます。
導入の目的と管理対象を明確に定義する
次に、「なぜIT資産管理/構成管理を強化するのか」という導入目的を明確化します。例えば「PC資産の棚卸し工数を削減したい」「インシデント対応を迅速化したい」など具体的な課題を洗い出し、優先順位を付けましょう。
同時に、管理対象とする範囲も定義します。オンプレミスのサーバー群だけなのか、クラウド上のVMやコンテナも含めるのか、社給スマホや周辺機器も対象にするのか等を決めます。目的とスコープがはっきりすれば、最適なツール選びや体制構築の指針が定まり、プロジェクトを関係者と共有しやすくなります。
情報整理とツール要件をドキュメント化する
現状棚卸しと目的定義ができたら、その内容をもとに必要な管理項目や機能要件を整理します。例えば「ソフトウェアライセンス契約情報を管理項目に含める」「資産の利用部署やオーナーを追跡できること」「CI間の関係性を可視化できる機能が欲しい」など、具体的な要求をリストアップします。これら要件は文書化(RFPの簡易版でも可)し、ツール選定時のチェックリストに使います。
また、現状情報に不足があれば追加調査し、将来運用のためのデータ項目定義も進めます。こうしたドキュメントを用意することで、ベンダーへの説明や社内合意形成もスムーズになります。
段階的にPoC(検証環境)を導入する
候補ツールが決まったら、いきなり本番適用せずにPoC(概念実証)環境で試験導入しましょう。少数の端末や限定的なシステム範囲から、ツールの機能や操作感、既存環境との相性を検証します。多くのIT資産管理ツールは無料トライアル期間があるため、本番データの一部を投入して使い勝手を試すことが可能です。
PoC段階では、現場担当者からのフィードバック収集も重要です。実運用に耐えうる性能か、欲しいレポートが簡単に出せるかなど確認し、問題があればベンダーに問い合わせて解決策を検討します。段階的なPoC導入により、本番稼働後のギャップを最小限に抑えることができます。
一元管理を実現する運用ルールを設計する
ツール導入の目処が立ったら、実際の運用方法について詳細なルール設計を行います。せっかく優れたツールを導入しても、使い方のルールが曖昧だとデータが更新されず形骸化してしまいます。そうならないよう、運用フローや役割分担を明確に定めましょう。例えば「新規購入した資産は必ず台帳に登録するフロー」「異動や廃棄時の情報更新責任者を決める」「定期的にCMDBのCI関係をレビューする」など具体的な手順書やガイドラインを作成します。
また、資産管理と構成管理を一元的に行う組織体制(たとえば同じ担当チームが両データを管理する等)も検討すると良いでしょう。運用ルールの整備によって、一元管理の仕組みが継続的に機能するようになります。
導入後の定着・改善プロセスを設ける
最後に、ツール導入後のフォロー体制を構築します。新しい管理プロセスが定着するまで、現場への周知徹底や定期的な効果測定を行いましょう。導入直後は使い方の問い合わせ対応や、入力漏れのチェックなど手厚くサポートし、数ヶ月かけて習熟度を上げていきます。その上で、半年~1年後を目処に運用状況を監査し、課題点を洗い出して改善策を講じるPDCAサイクルを回します。
例えば、「登録項目が多すぎて入力が大変なら項目精査する」「活用されていない機能があれば研修を実施する」といった改善を重ねます。こうした定着・改善プロセスをあらかじめ設けておくことで、せっかくのIT資産管理・構成管理システムが宝の持ち腐れになるのを防ぎ、長期的な運用成熟度の向上につなげられます。
構成管理を高度化するCMDB活用ガイド
構成管理の効果を最大化するには、CMDBを効果的に活用・運用することが鍵となります。ここでは、CMDB導入の成否を分けるポイントを2つ紹介します。
CMDBとCI設計のキモ
CMDBを構築する際は、CI(構成アイテム)の設計が最も重要です。CIの粒度を細かくしすぎると管理が煩雑になり、逆に大まかすぎると十分な関係性が把握できません。自社のITサービスを分析し、ハードウェア・ソフトウェア・サービスなど適切なカテゴリ分けと階層構造を設計しましょう。
例えば、サーバー1台を1CIとするのか、クラスタ全体を1CIとするのか、用途に応じて管理単位を定義します。また、各CIに紐づける属性情報も予め決めておきます。名称やバージョン、所有者、設置場所、稼働状態、契約情報など、IT資産管理の項目とも重複する情報はマスタを共有することも検討します。CI設計では将来的なスケーラビリティも考慮に入れ、必要に応じて新たなCIカテゴリを追加できる柔軟性も確保しましょう。最初に設計のキモを押さえておけば、CMDB構築後の運用負荷を最小限に抑えつつ、有用なデータベースを構築できます。
自動ディスカバリとデータ品質管理
CMDBを活用する上で、データの最新性と正確性を維持することが不可欠です。そのために有効なのがIT資産の自動ディスカバリ機能の活用です。ネットワークをスキャンして接続された機器を自動検知したり、エージェントソフトで端末の構成情報を定期収集したりすることで、人手を介さずCMDBを更新できます。これにより登録漏れや情報の陳腐化を防ぎ、常に最新の構成情報を保てます。
ただし、自動収集に任せきりではなく、データ品質管理のプロセスも並行して整備しましょう。定期的にCI情報をレビューし、重複登録の統合や不要CIの削除を実施します。変更管理プロセスと連携し、変更承認時にCMDB更新を必須フローとするのも効果的です。さらに、CIごとにオーナー(責任者)を定めておき、その人が情報を定期確認する仕組みも有効です。自動化ツール+運用プロセスの両面からデータ品質を守ることで、CMDBの信頼性を高く維持できます。
IT資産管理×構成管理の成功事例
実際にIT資産管理と構成管理を統合し、効果を上げた企業の事例を2つご紹介します。
製造業A社:資産棚卸し自動化で工数50%削減
グローバル展開する製造業のA社では、拠点ごとにIT資産台帳をExcel管理しており、年次棚卸しに延べ数百時間を費やしていました。そこでIT資産管理ツールとCMDBを導入し、各端末にエージェントを配布して資産情報を自動収集する仕組みに移行しました。
その結果、手作業だった台帳更新作業の大半が不要となり、棚卸し工数を約50%削減することに成功しました。また、常に最新の資産情報が得られるようになったことで、不要機器の迅速な洗い出しやライセンス再分配によるコスト削減効果も出ています。A社では情シス部門と各事業部門が協力して運用ルールを策定し、全社で統一されたIT資産&構成管理体制を築いたことが成功のポイントです。
SaaS企業B社:シャドーIT可視化でリスク低減
急成長中のSaaSプロバイダB社では、社員が各自でクラウドサービスを契約・利用してしまう「シャドーIT」の増加が課題でした。把握されていないSaaS利用は情報漏洩リスクにつながるため、B社ではIT資産管理と構成管理の統合プラットフォームを採用し、社内からアクセスするクラウドサービスやデバイスをすべて一元モニタリングしました。具体的には、全社員端末に管理エージェントを導入し、アクセスログやインストール済みソフトウェアを収集してCMDBに集約しました。
その結果、社内で利用されているクラウドサービスを可視化でき、許可のないサービス利用を発見次第ガバナンスを利かせる運用に移行できました。これにより情報漏洩や認証管理の抜け漏れといったセキュリティリスクを大幅に低減しています。B社では新たなITサービス利用時に情シスへの申請をルール化するなど統制も強化し、利便性と統制のバランスを取りながらIT資産管理×構成管理の仕組みを活用しています。
IT資産管理と構成管理を連携し、継続的な運用改善へつなげよう
IT資産管理と構成管理は、それぞれを単独で行うよりも車の両輪として連携させることで、ITインフラ管理の精度と効率が飛躍的に高まります。資産の状況と構成のつながりが見える化されれば、コスト削減やセキュリティ強化、迅速な障害対応など多くのメリットが得られるでしょう。
本記事で紹介したポイントを参考に、自社のITAMとCMを見直し、ぜひ継続的な運用改善につなげてください。2025年現在も進化するツールやベストプラクティスを取り入れながら、IT資産管理×構成管理の体制をアップデートしていきましょう。




