
IT資産管理を効率化!コスト削減と業務改善を同時に実現する完全ガイド
近年、テレワークの定着やクラウドサービスの普及により、企業のIT資産を取り巻く環境は大きく変化しています。パソコンやソフトウェアの管理が従来の方法では限界が見え始め、コストの無駄やセキュリティリスクも顕在化しています。
そこで本記事ではIT資産管理の効率化に注目し、コスト削減と業務改善を両立するポイントを詳しく解説します。IT資産管理の基本から効率化の必要性、具体的な方法、そしておすすめツールや選定のポイントまでをご紹介しますので、今一度、自社のIT資産管理を見直すきっかけとして、ぜひお読みください。
目次[非表示]
- 1.IT資産管理とは?
- 1.1.IT資産管理とソフトウェア資産管理(SAM)の違い
- 1.2.IT資産管理の管理対象
- 2.IT資産管理の効率化が必要な理由
- 2.1.管理対象のIT機器の拡大と複雑化
- 2.2.ITコストの最適化
- 2.3.セキュリティリスクの削減
- 2.4.業務効率と生産性の向上
- 3.IT資産管理を効率化する3つの方法
- 3.1.IT資産管理ツールの導入
- 3.2.運用ルールの策定
- 3.3.RFID・バーコードで棚卸しの作業時間を短縮
- 4.主要なIT資産管理ツール5選
- 4.1.LANSCOPE Endpoint Manager
- 4.2.SKYSEA Client View
- 4.3.Assetment Neo
- 4.4.AssetView
- 4.5.ジョーシス
- 5.IT資産管理ツールの選定ポイント
- 5.1.管理対象の範囲
- 5.2.運用負担とユーザビリティ
- 5.3.セキュリティ・コンプライアンス対応
- 5.4.拡張性・他システムとの連携
- 5.5.コストとライセンス体系
- 5.6.ベンダーの信用性とサポート体制
- 5.7.導入・移行のしやすさ
- 6.IT資産管理を効率化して、コスト削減と業務効率化を両立しよう
IT資産管理とは?
IT資産管理とソフトウェア資産管理(SAM)の違い
IT資産管理(IT Asset Management, ITAM)とは、企業内のPC、サーバー、ネットワーク機器、ソフトウェア、クラウドサービスなどあらゆるIT資産を把握し適切に管理することです。ハードウェアの一覧やソフトウェアのライセンス情報、利用状況や更新状況まで一元的に管理し、必要なときに全体像を把握できるようにします。
これに対しソフトウェア資産管理(Software Asset Management, SAM)は、その名の通りソフトウェア資産に特化した管理手法です。具体的には、社内で使用するソフトウェアライセンスの利用状況や契約情報を適切に管理し、違法なライセンス超過や未使用ライセンスの洗い出しを行います。
言い換えると、SAMと関連するSaaS管理がソフトウェアに重点を置いているのに対し、ITAMは物理デバイスやクラウドインフラも含めたより包括的なIT資産の管理を目指すアプローチです。
目的にも違いがあり、SAMはソフトウェアのライセンスコンプライアンス確保やコスト最適化が主眼となるのに対し、ITAMは企業が保有するすべてのIT資産を可視化し、有効活用してリスクとコストを減らすことに重きを置きます。つまりSAMはIT資産管理の一部領域(ソフトウェア分野)に特化した取り組みであり、IT資産管理全体の中で重要な役割を果たすものと言えるでしょう。
IT資産管理の管理対象
IT資産管理の対象範囲は非常に広く、 企業が業務で利用するあらゆるIT関連のリソースが含まれます。具体的には、ハードウェア資産(PC、サーバー、プリンタ、ネットワーク機器、モバイル端末など)やソフトウェア資産(OSや業務アプリケーション、ソフトウェアライセンス類)に加え、近年ではクラウドサービスのアカウントやSaaSも重要なIT資産に位置付けられます。
また、IT資産にはこのほかに、それらを利用する上で必要な契約情報や設定情報、アカウント情報なども含まれます。例えば、社内で利用しているクラウドストレージの契約や、社員に貸与しているWi-Fiルーター、さらには周辺機器の備品まで管理対象に含める企業もあります。
IT資産管理ではこうした多種多様な資産情報を一元的に台帳にまとめ、資産ごとの所在や利用者、契約期限などを常に把握します。抜け漏れのない資産台帳を整備しておけば、棚卸しやライフサイクル管理がスムーズになり、老朽化した資産の交換時期の判断や、未使用資産の有効活用といった戦略的な意思決定にも役立ちます。
IT資産管理の効率化が必要な理由
管理対象のIT機器の拡大と複雑化
かつてはオフィスのデスクトップPCや社内サーバー程度だったIT資産も、現在では種類・数ともに急速に増加しています。スマートフォンやタブレットの業務利用が進み、リモートワーク普及によって従業員一人ひとりが自宅用の端末を持つケースも増加しています。さらに、IT機器の種類が増えれば、それに伴い周辺機器やソフトウェアライセンス、アカウント数も増加し、管理すべき対象が年々拡大・多様化しているのが現状です。
こうした複雑化した環境では、従来のエクセル台帳や属人的な管理では全容を把握しきれず、管理漏れが発生しがちです。その結果、どこかに使われていないPCが放置されていたり、部署ごとにバラバラにIT資産を調達して非効率になっていたりすることも少なくありません。IT資産管理の効率化は、このように増え続けるIT資産を統制し全体最適を図るために不可欠な取り組みなのです。
ITコストの最適化
IT資産管理を効率化する最大の目的の一つがコスト削減効果です。適切に管理されていない状態では、往々にして不要な機器やライセンスへのムダなコスト支出が発生します。例えば、事業拡大に伴い人員とPCを増やしたものの、古いPCの廃棄やソフトウェアライセンスの整理が追いついていないと、使っていない資産に保守費用やライセンス更新費を払い続けるリスクがあります。
また、各部署が個別にIT機器を購入していると、全社で見れば同じようなソフトを重複購入しているケースもあるでしょう。IT資産を一元管理すれば、未使用・重複の資産を可視化して統廃合できるため、余分な支出を抑えられます。
さらに、資産情報が整備されていれば、例えばパソコンの一括購入によるボリュームディスカウント交渉や、クラウドサービスの利用プラン見直しなど調達・契約面でのコスト最適化も図りやすくなります。IT資産管理ツール導入には一定の投資が必要ですが、それを上回るIT全体のコスト削減効果が見込めるケースが多いため、効率化の重要な理由となっています。
セキュリティリスクの削減
管理が行き届かないIT資産は、情報セキュリティ上の大きなリスクとなります。
例えば古いソフトウェアが社内に残ったままでパッチが適用されていなかったり、部署によってウイルス対策ソフトの導入状況にムラがあったりすると、そこがサイバー攻撃や情報漏えいの脆弱ポイントになってしまいます。効率的なIT資産管理により、すべての端末に最新のセキュリティパッチを適用したり、インストールされているソフトウェアを一覧で把握して脆弱性のあるものを迅速に洗い出すことが可能です。
また、資産管理ツールの中には端末の操作ログ取得やデバイス制御の機能を備えたものも多く、社員による不正操作や機密データの持ち出しをリアルタイムで検知・抑止できます。仮に情報インシデントが発生しても、どの端末で何が起こったか履歴を追跡できるため迅速な原因究明と被害拡大防止につながります。
「管理の抜け」がない状態を維持することがセキュリティリスク削減の基本であり、そのためにもIT資産管理の効率化が求められます。
業務効率と生産性の向上
IT資産管理の効率化は、情報システム部門や管理担当者の業務負荷軽減と全社の生産性向上にも直結します。
従来、情シス担当者が手作業で行っていた資産台帳の更新や棚卸し作業、ソフトウェア更新作業などは非常に時間がかかり、本来注力すべき戦略的なIT業務の妨げになっていることも少なくありませんでした。
資産管理を見直しツールや自動化を取り入れることで、担当者が一つひとつ手動対応していた作業を大幅に削減できます。同じ人数でもより多くの資産を正確に管理できるようになるため、ひとり情シスのような少人数体制でも安心です。
さらに、IT資産管理が効率化されていれば新入社員のPCセットアップや故障時の交換対応などもスピーディーに行えるため、現場社員が待ち時間でロスすることも減り生産性向上につながります。結果として、IT資産管理を効率化することは情シス部門の働き方改革にもつながり、ひいては全社員の業務効率アップに寄与する重要な施策と言えるでしょう。
IT資産管理を効率化する3つの方法
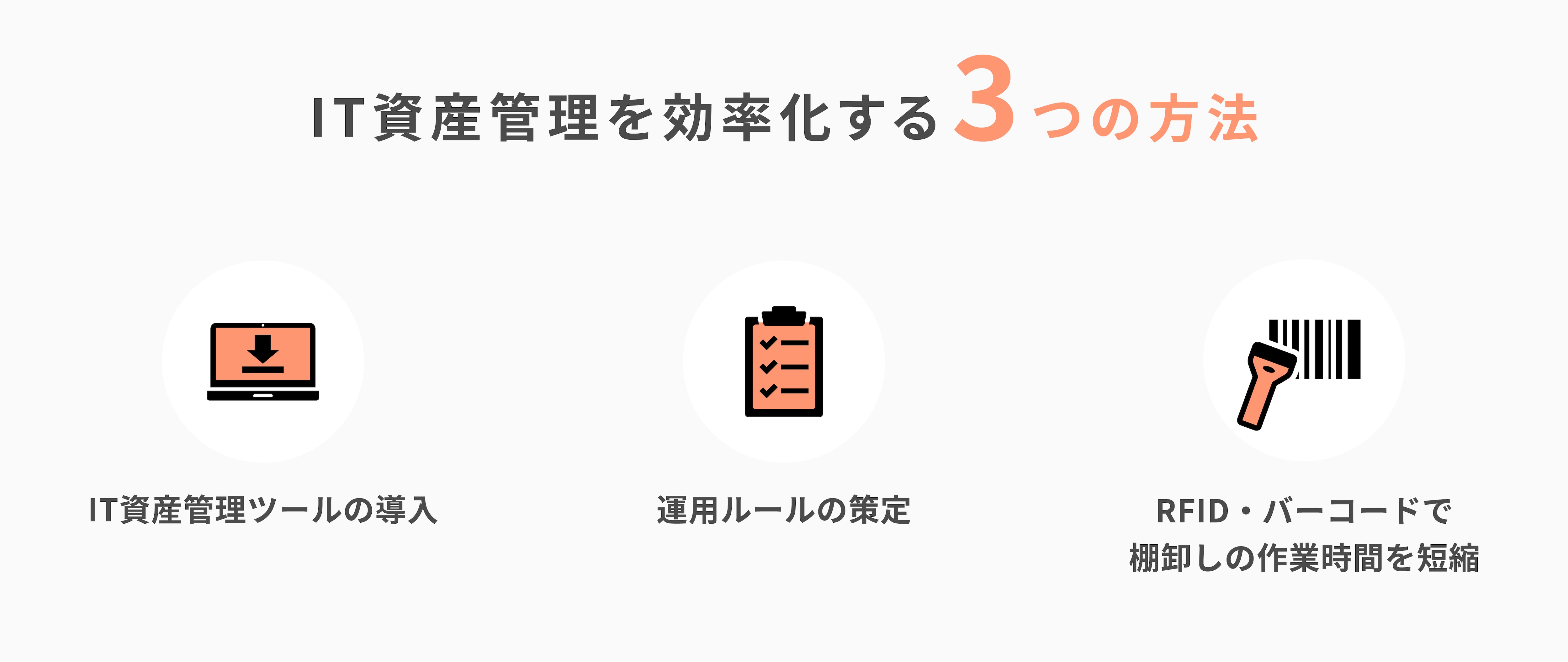
IT資産管理ツールの導入
IT資産管理を効率化するうえで最も効果的な方法が、専用のIT資産管理ツールを導入して資産情報を一元管理することです。
多種多様なIT資産を人手で管理しようとすると限界がありますが、ツールを使えば社内の全IT資産を一括で把握できます。IT資産管理ツールには、クラウド型(ベンダー提供のクラウド上で利用)とオンプレミス型(自社サーバーに導入)の2種類があります。近年は初期費用を抑えて迅速に導入できるクラウド型が人気ですが、自社ポリシーによってはオンプレ型を選ぶケースもあります。
ツールごとに機能は異なりますが、一般的にはIT機器やソフトウェアのインベントリ管理、ライセンス契約の期限管理、操作ログの収集、セキュリティパッチの適用管理など、IT資産管理に必要な基本機能は網羅されています。
製品ごとに、「マルウェア対策機能が強力」「インターフェースやレポート画面が見やすい」など特徴がありますので、自社が特に強化したいポイントにマッチするかや利用ユーザー数に見合うプランかといった観点で選定すると良いでしょう。導入前には無料トライアルやデモを活用し、コストに見合う効果が得られそうか、担当者が使いこなすことができそうかをしっかり見極めることも大切です。
運用ルールの策定
効率化のためツールを導入した後は、適切な運用ルールの策定も欠かせません。ただツールを入れただけでは効果を十分に発揮できず、使いこなせないまま形骸化してしまう恐れもあります。そうならないために、ツール導入時に操作方法や管理範囲、運用フローを明文化した社内ルール(運用マニュアル)を整備することが重要です。
例えば、「新しいIT資産を調達したら必ず台帳に登録する」「異動や退職時には所定の手順で資産の割り当て変更・回収を行う」など、具体的なプロセスと担当を定めます。同時に、導入した管理ツールの機能のどこまでを活用するかも決めておくと良いでしょう。
こうしたルールを文書化し共有しておけば、担当者が交代しても運用が安定しますし、社内のだれもがIT資産管理の手順を把握できるようになります。定期的にルールを見直し、運用の実態に合わせてアップデートしていくことで、ツール導入の効果を持続させられるでしょう。
RFID・バーコードで棚卸しの作業時間を短縮
IT資産の物理管理を効率化するテクニックとして、棚卸し作業にバーコードやRFID(ICタグ)を活用する方法があります。社内のPCや機器にバーコードラベルを貼り、棚卸し時に専用スキャナで読み取れば、シリアル番号を一つひとつメモするより格段にスピーディーです。
さらに、近年注目されているRFIDタグを利用すれば複数の資産を非接触で一括読み取りできるため、バーコードスキャンや目視確認に比べ作業時間を大幅に短縮できます。実際、RFID導入によって棚卸し作業が従来の20分の1の時間で完了したという事例もあり、人的負担の軽減とデータ精度向上に大きく寄与します。ただしRFIDは導入コストもかかるため、まずはバーコードによる管理から始めてみるのも良いでしょう。
いずれにしても、IT資産管理ツールと組み合わせて定期的な棚卸しを半自動化することで、短時間で正確に資産状況を洗い出せるようになります。棚卸し作業の効率化は、そのまま管理台帳の精度向上とコンプライアンス強化にもつながります。
主要なIT資産管理ツール5選
ここでは様々な企業で導入されている主要なIT資産管理ツール5つをご紹介します。それぞれ特徴が異なりますので、自社の課題に合ったものを選ぶ際の参考にしてください。
LANSCOPE Endpoint Manager
LANSCOPE Endpoint Manager(ランスコープ エンドポイントマネージャー)は、MOTEX社が提供する統合エンドポイント管理ツールです。
IT資産管理やデバイス管理、ウイルス対策など豊富な機能を備え、特にクライアントPCの操作ログ収集・活用に定評があります。各PCにエージェントを導入し、ハードウェア情報やソフトウェアインストール状況、ログオン/ログオフ履歴、Webアクセス履歴などを自動で収集してサーバーに送信し、一元的に管理可能です。
クラウド版とオンプレミス版の両方が提供されており、自社の規模やポリシーに合わせて選択できます。クラウド版では標準で2年間、オプション適用で最大5年間の長期ログ保管にも対応しており、大規模環境における証跡管理や監査にも対応可能です。
不正操作のポップアップ警告や外部システム連携(SIEM(SIEM:Security Information and Event Management)連携オプション)などセキュリティ面が充実している点も大きな特長であり、多くの企業で統合IT資産管理ソリューションとして広く利用されています。
サービスサイト:https://www.lanscope.jp/endpoint-manager/
SKYSEA Client View
SKYSEA Client View(スカイシー クライアントビュー)は、Sky株式会社が開発・提供する実績のあるIT資産管理ソフトです。
社内のPCやタブレット、USBメモリなどあらゆるIT機器を一元管理でき、さらにクライアント操作ログの自動収集機能も備えています。ログオン/ログオフや電源ON/OFF、ファイル操作、Webアクセス、印刷、メール送受信、USBデバイス接続といった15種類以上の操作ログを取得してサーバーに集約保存でき、不正や情報漏えいの早期発見に役立ちます。オフライン時に行われたノートPC上の操作もエージェントが記録を蓄積し、ネットワーク復帰後にサーバーへ自動送信することで、オフライン時の操作も漏れなく管理できます。
大企業から中堅企業まで幅広い導入実績があり、オンプレミス型が主流ですがクラウド版も提供されています。「資産管理+ログ管理」の定番ともいえる存在で、長年にわたり培われた信頼性と豊富な機能がその強みとなっています。
サービスサイト:https://www.skyseaclientview.net/
Assetment Neo
Assetment Neo(アセットメント ネオ)は、株式会社アセットメントが提供するクラウド型のIT資産管理ツールです。
特徴はPCやサーバーはもちろん、スマートフォンやソフトウェアライセンス、社員への貸与物まで含めたIT資産全体のライフサイクルを一元管理できる点にあります。部署や社員ごとの資産割当管理がしやすく、棚卸しや監査対応に役立つ機能も充実しています。
また、エージェントによる資産情報の自動収集をはじめ、SaaS連携用のAPIが用意されており、他システムとのデータ統合が容易に行える点も特徴の一つです。クラウドサービスとして提供されているため、インフラの構築が不要で、常に最新版を利用できるのも魅力です。
資産台帳のクラウド化により、日々の管理工数を大幅に削減しつつ、IT資産の利用状況をリアルタイムに可視化できるとして、多くの企業で採用が進んでいます。特に自社内にIT担当者が少ない場合でも扱いやすく、中小企業でも導入しやすいIT資産管理SaaSと言えるでしょう。
サービスサイト:https://www.assetment.net/
AssetView
AssetView(アセットビュー)は、ハンモック社が提供するオンプレミス型の統合IT資産管理ツールです。ハードウェア資産・ソフトウェア資産の台帳管理機能に加え、内部統制・不正対策の観点からクライアントPCの詳細な操作ログ監視機能を備えています。
各PCにエージェントを導入し、PCの起動・ログオン履歴からファイル操作(新規作成・編集・削除)、Webサイトへのアップロード、メール送信、印刷、USBデバイス接続に至るまで幅広い操作ログを自動で取得・集中管理できます。
さらに、不審な操作に対するリアルタイムでの警告ポップアップをユーザー端末上に表示したり、操作自体をブロックする設定も可能で、これにより、従業員のセキュリティ意識を高め、内部不正の抑止にもつながります。取得したログから怪しい操作のみを抽出して前後の履歴を確認する、といった効率的な証跡追跡も可能です。
Webブラウザで操作できる使い勝手の良い管理コンソールを持ち、中堅・中小企業から官公庁まで幅広い導入実績があります。IT資産管理に加えて情報漏えい対策も同時に行いたい企業にとって、非常に有力な選択肢となるソリューションです。
サービスサイト:https://www.hammock.jp/assetview/
ジョーシス
ジョーシス(Josys)は、ジョーシス株式会社が提供するクラウド型IT資産管理プラットフォームです。最大の特徴は、従業員の入社・異動・退職といったライフサイクルに応じて、SaaSアカウントやデバイスを一元管理し、自動処理まで可能にする点です。
例えば、新入社員が入社する際には事前に登録されたワークフローに従って必要なSaaSアカウントの発行やPCのキッティング手配が自動化され、退職時にはアカウント停止やPC回収のタスクが自動的に処理されます。複数のSaaSや社内システムを一括で制御することで、人為ミスやセキュリティリスクの軽減につながるとともに、IT部門だけでなく人事・総務など非IT部門とも連携しやすいUI設計となっています。
まさにDX時代の統合IT資産管理ツールとして注目されており、社員数が少ない企業から急成長中のベンチャーまで導入が増えています。IT資産台帳管理はもちろん、ID管理・デバイス管理・ソフトウェア配布など広範囲をカバーしつつ、ノーコードで設定可能なワークフローによって属人的なIT対応の自動化を実現し、安心して運用できる頼もしいサービスです。
サービスサイト:https://www.josys.com/jp
IT資産管理ツールの選定ポイント
複数のIT資産管理ツールがありますが、導入にあたっては自社に最適なものを選ぶ必要があります。ここでは、ツール選定時に注目すべきポイントを7つ紹介します。それぞれの観点で自社の要件を整理し、優先順位を付けて検討すると良いでしょう。
管理対象の範囲
まず自社が管理したい資産の範囲をカバーできるツールかを確認しましょう。
各ツールにより、収集・管理できる資産情報の種類や深さには違いがあります。例えば、ハードウェアの型番・シリアル番号、OSやソフトウェアのバージョン、インストール済みパッチ情報、クラウドサービスのアカウント情報など、必要な項目が漏れなく管理対象となっているかをチェックします。
また、自動収集される情報の精度や更新頻度も重要です。精度が低いツールでは誤った資産情報が登録されてしまい、かえって管理ミスやセキュリティリスクにつながります。
現在管理対象となっている社内IT資産(オンプレ機器、クラウド資産、周辺機器など)のリストアップを行い、その全てを一元管理できるツールかどうかを見極めることが大切です。
運用負担とユーザビリティ
IT資産管理ツールは導入して終わりではなく、実際に情シス担当者が日常的に使いこなしてこそ効果を発揮します。そのため、ツールの使いやすさや運用時の負担感も重要な選定ポイントです。
具体的には、管理画面のUIが直感的で操作しやすいか、レポート作成や検索機能が充実していて担当者の手作業を省けるか、といった点を確認しましょう。ツールの中には多機能であるがゆえに設定項目が複雑で学習コストが高いものもあります。自社の管理担当部門の体制やITリテラシーに照らし合わせて、無理なく運用できるツールを選ぶことが肝心です。
可能であれば事前に無料トライアル版を試用し、実際の画面で自社業務に合うのかを確かめるのがおすすめです。また、エージェント型ツールの場合はクライアントPCへの負荷も考慮しましょう(過度にPCの動作を重くしない軽量なものが望ましい)。最終的には、「このツールを導入すれば担当者の作業時間がどれだけ減り、何が自動化できるか」をイメージしながら比較検討すると良いでしょう。
セキュリティ・コンプライアンス対応
IT資産管理ツールには、セキュリティ強化やライセンスコンプライアンス対応を支援する機能が多数備わっています。選定にあたっては、特に自社で重視したいセキュリティ/コンプライアンス要件を満たせるかをチェックしましょう。
例えば、ソフトウェア資産のライセンス数を管理して契約違反を防止できる機能は、ソフト資産の多い企業には必須です。ライセンス監査で違反を指摘されれば高額な賠償金につながる可能性もあるため、ツール上で未認証ソフトやライセンス超過を即時検知できると安心です。
また、クライアント操作ログの収集やデバイス制御機能があれば、内部不正や情報漏えいの抑止に役立ちます。端末のウイルス対策ソフト導入状況やパッチ適用状況を可視化し、脆弱な端末を洗い出す機能があるツールも良いでしょう。
さらに、昨今はゼロトラストセキュリティの考え方もあり、クラウド管理下で社内外から端末を監視できることも重要です。自社のセキュリティポリシーや遵守すべき業界規制(例:個人情報保護、内部統制基準など)に合致した機能セットを持つツールを選ぶことで、IT資産管理を通じたリスク低減とコンプライアンス維持が期待できます。
拡張性・他システムとの連携
IT資産管理ツールを選ぶ際には、将来的な拡張性や周辺システムとの連携のしやすさも考慮しましょう。他のシステムとのデータ連携ニーズは企業によって様々ですが、例えば人事システムや勤怠管理システムと連携させて入退社時の資産貸与プロセスを自動化したり、セキュリティ系ツール(ウイルス対策・MDMなど)と連携して脆弱性情報を取り込んだりするケースがあります。その場合、候補のツールについてAPI提供やCSVインポート/エクスポート機能が充実しているかを確認しましょう。
加えて、どの程度カスタマイズが可能かも要チェックです。特に自社開発のシステムや既存のITSM(ITサービスマネジメント)ツールがある場合、資産情報を相互にやり取りできれば運用効率がさらに向上します。
また、将来的に組織規模が拡大した際に対応できるスケーラビリティも重要です。数百台規模から数万台規模まで段階的に拡張できるアーキテクチャか、追加ライセンスで簡単に対応可能かなどをベンダーに確認しておくと安心です。
コストとライセンス体系
ツール導入にあたって無視できないのがコスト面です。初期導入費用や月額料金はツールによって様々ですので、予算内で収まるか慎重に見極めましょう。
一般的にクラウド型は月額サブスクリプション課金(利用端末数やユーザー数に応じて料金変動)が多く、オンプレミス型はライセンス買い切り+保守費用という形が多い傾向です。社内のIT資産数やユーザー数を踏まえ、どちらのライセンス体系が有利か試算すると良いでしょう。
また、契約単位、追加ライセンスの柔軟性、サポート費用の有無など細かい条件も確認が必要です。コストと効果のバランスを測るために、ベンダー提供の料金シミュレーションを利用するのも一手です。「高機能だけれど高額すぎて継続利用が難しい」では本末転倒なので、自社にとって必要十分な機能を持ち、適正価格であることを重視してください。
さらに、何社かの製品を比較する際には初年度費用だけでなく3年~5年スパンの総コスト(TCO)も比較しておくと、長期的なコスト最適化に役立ちます。
ベンダーの信用性とサポート体制
IT資産管理ツールは導入後も長く使い続けるものですから、提供元ベンダーの信頼性やサポート体制も重要な検討材料です。
まず、そのベンダーや製品に十分な実績があるか(導入社数や事例)、金融機関や官公庁など高い信頼性が求められる顧客にも採用されているか、といった点を確認しましょう。歴史の浅い新興サービスであっても、提供企業の資本背景や事業継続性、ロードマップがしっかりしているかを見極める必要があります。
一方、サポート面では導入時の支援や導入後の問い合わせ対応の充実度が鍵となります。具体的には、セットアップ時に技術スタッフが伴走してくれるか、マニュアルや研修サービスが提供されるか、導入後トラブルが起きた際に迅速に日本語サポートが受けられるか、といった点です。
サポート対応時間やサポート窓口の方法も確認しましょう。特に初めてIT資産管理ツールを導入する場合は、手厚い導入支援や操作トレーニングがあるベンダーだと安心です。製品の今後のバージョンアップ計画や機能改善の頻度なども含め、総合的に信頼できるパートナー企業かどうか判断してください。
導入・移行のしやすさ
最後に、ツールの導入プロセスや他方式からの移行が容易かもチェックしましょう。
クラウド型であれば環境構築の手間は少なく、アカウント発行後すぐに利用開始できるものが多いです。一方、オンプレミス型ではサーバー調達やソフトウェアインストール作業が必要になるため、導入に要する期間・工数をあらかじめ想定しておく必要があります。
すでにエクセル台帳等で資産管理を行っている場合は、そのデータを新ツールにスムーズにインポートできるかも重要です。ツールによっては初期設定時に既存資産情報のCSV取り込み機能があり、過去データを活かせるものもあります。
さらに、全社展開する際に段階的にロールアウトできるか、トライアル導入から本格展開への切り替えが容易か、といった運用面の移行のしやすさも検討ポイントです。事前にパイロット導入を行い、小規模で試してから全社に広げるのもリスク低減に有効です。
総じて、「無理なく導入でき、現行業務を止めずに移行できるか」を念頭に置いて選定すると、導入後の定着までスムーズに進むでしょう。
IT資産管理を効率化して、コスト削減と業務効率化を両立しよう
IT資産管理の効率化は、単に台帳管理の手間を省くだけでなく、企業のIT運用全体に多くのメリットをもたらします。適切にツールを導入し運用ルールを整備すれば、資産情報の一元管理が実現し、担当者の負担軽減やセキュリティ対策強化、そしてITコストの最適化まで可能になります。
もちろん、最初は新しい仕組みに慣れるまで試行錯誤があるかもしれませんが、一度軌道に乗れば「もっと早く取り組んでおけばよかった」と感じるほど多くの効果を実感できるでしょう。
本記事で紹介したポイントを参考に、ぜひ自社に合った方法でIT資産管理の効率化にチャレンジしてみてください。IT資産をきちんと管理・コントロールできれば、ムダなコストを削減しつつ業務の生産性を向上させるという一石二鳥の成果が期待できます。効率的なIT資産管理を実現して、コスト削減と業務効率化の両立を達成しましょう。




