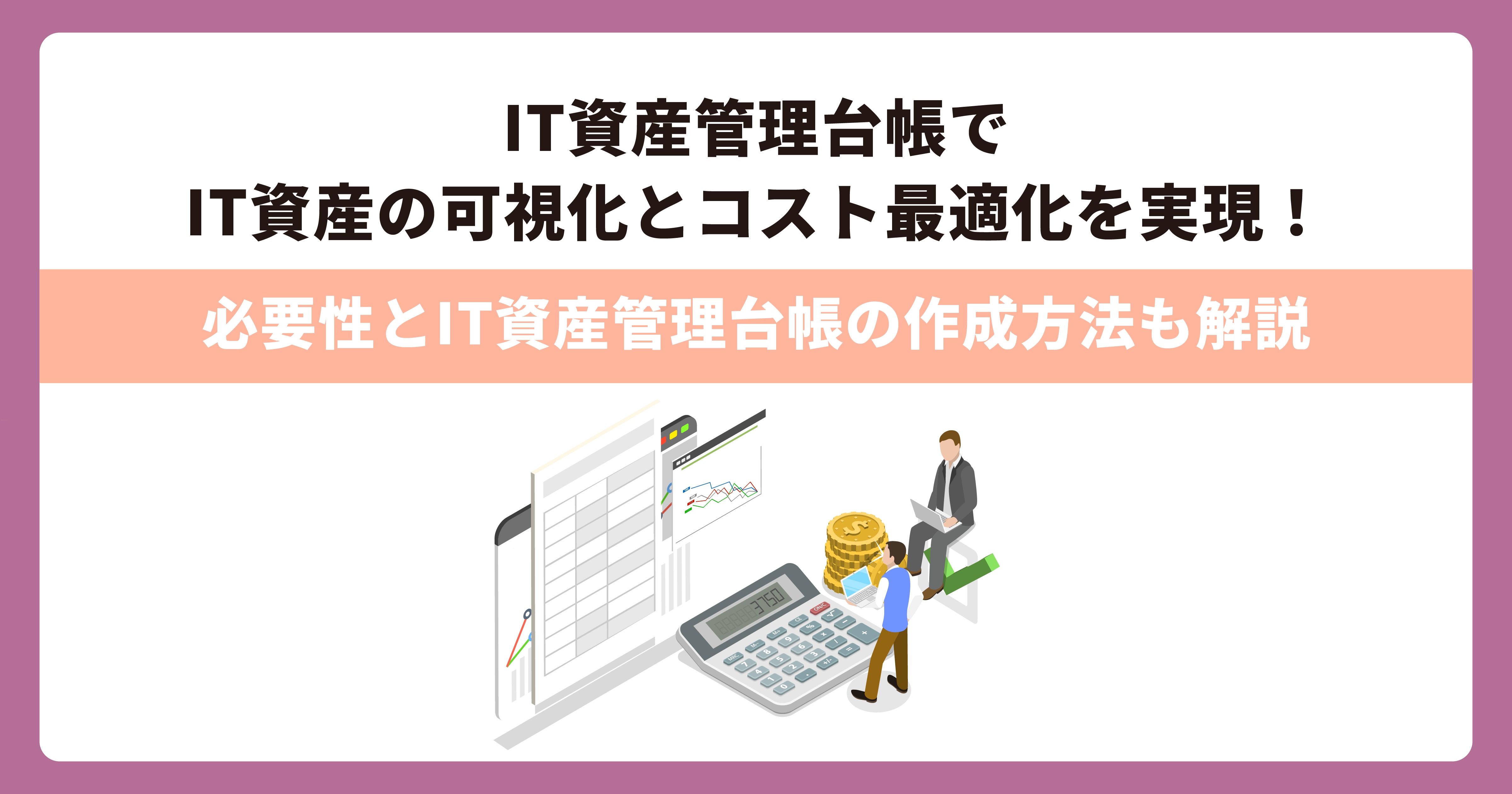
IT資産管理台帳でIT資産の可視化とコスト最適化を実現!必要性とIT資産管理台帳の作成方法も解説
現代の企業では、PCやサーバー、ソフトウェアなどのIT資産が年々増え続けています。そうしたIT資産を効率的に管理するために役立つのがIT資産管理台帳です。IT資産管理台帳を活用すれば、社内のどのIT資産が誰によって使用されているかをひと目で把握でき、無駄なコストの発生を防ぐことにもつながります。
本記事では、IT資産管理台帳とは何か、そのメリット、記載すべき項目と作成方法、さらにIT資産管理ツール導入のメリットまで詳しく解説します。
目次[非表示]
- 1.IT資産管理台帳とは?
- 1.1.IT資産管理台帳の役割
- 1.2.管理対象となるIT資産の範囲
- 2.IT資産管理台帳が必要となる4つの理由
- 2.1.IT資産の可視化と効率的な管理
- 2.2.セキュリティリスクの低減
- 2.3.コスト最適化
- 2.4.コンプライアンス遵守
- 3.IT資産管理台帳に記載必須の10項目
- 4.IT資産管理台帳の作成方法
- 4.1.STEP1:ガバナンスポリシーと目的を明確化
- 4.2.STEP2:IT資産の棚卸
- 4.3.STEP3:管理項目(10項目+α)を設計
- 4.4.STEP4:フォーマットを用意(Excel/スプレッドシートなど)
- 4.5.STEP5:初期データ入力・データ品質チェック
- 4.6.STEP6:運用ルールの策定
- 5.IT資産管理ツール導入のメリットと注意点
- 6.IT資産管理ツールの費用対効果
- 7.IT資産管理台帳を活用してIT資産の効率的な管理を実現しよう
IT資産管理台帳とは?
IT資産管理台帳とは、企業が保有するパソコンやソフトウェアなどのIT資産に関する情報を一元的にまとめた管理用の台帳です。まずはその定義と役割、および管理の対象範囲について見ていきましょう。
IT資産管理台帳は情報システム部門(情シス)が中心となって作成・管理するケースが一般的です。一般的にはExcelやスプレッドシートなどで項目ごとに一覧表を作成し、各資産の詳細情報(名称、利用者、購入日など)を記録します。
また、会計上の固定資産台帳が減価償却など財務目的の管理台帳であるのに対し、IT資産管理台帳は日々の運用・セキュリティ管理を目的とした台帳である点が特徴です。ITIL(ITサービスマネジメントのベストプラクティス)においてもIT資産管理は重要なプロセスとして位置づけられており、IT資産管理台帳はその基盤となるツールです。台帳を整備することで、IT資産を漏れなく把握できるようになり、経営層への報告資料作成も容易になるでしょう。
IT資産管理台帳の役割
IT資産を”見える化”して管理することで、資産の利用状況や寿命を把握し、適切なタイミングでのメンテナンスや更新計画に役立てることができます。また、社内の資産状況を正確に把握できるため、IT統制や予算策定において重要な役割を果たします。例えば、「どの部署にどのPCが何台あるか」「このサーバーは購入から何年経過したか」などの問いにも、台帳を参照すればすぐに答えられるようになります。日常のIT管理業務や社内からの問い合わせ対応を効率化するうえでも、IT資産管理台帳は欠かせない存在です。
管理対象となるIT資産の範囲
IT資産管理台帳で管理すべき対象は、多岐にわたります。具体的には、パソコン(デスクトップ、ノートPC)、サーバー、プリンターやルーターなどのネットワーク機器、スマートフォンやタブレット等のモバイル端末といったハードウェアが含まれます。加えて、OSや業務アプリケーションなどのソフトウェア、それらのソフトウェアを利用するためのライセンス契約やクラウドサービスのアカウント情報も重要な管理対象です。
つまり、社内で使用・保有しているあらゆるIT関連の資産(形ある機器から無形のソフトウェア権利まで)が、IT資産管理台帳に含めるべき範囲となります。デジタル資産も含めて管理する点がポイントです。IoT機器やクラウド上の仮想サーバーも管理対象となります。
IT資産管理台帳が必要となる4つの理由
IT資産管理台帳を整備することには、多くのメリットがあります。ここでは、特に重要な4つの理由について解説します。管理台帳がないために「使っていないPCに気づかず無駄な購入をしてしまった」「ソフトウェアのライセンス違反を指摘された」などの事例も散見されますが、IT資産管理台帳を導入すればこうした問題を予防できます。主に、「IT資産の可視化」「セキュリティリスクの低減」「コスト最適化」「コンプライアンス遵守」の4点が挙げられます。
IT資産の可視化と効率的な管理
IT資産管理台帳を導入する最大のメリットは、社内のIT資産情報を可視化できることです。台帳によって、どの部署でどんな資産が使われているかを一覧で把握できるため、資産管理者は必要な情報をすぐに確認できます。特に近年はリモートワークの普及により、社外に持ち出されているノートPCや在宅勤務中のデバイスなど、分散する資産の管理が課題です。
IT資産管理台帳があれば、社内外に点在するIT機器の利用状況も一元管理でき、離れた場所からでも効率的に棚卸しや状況把握を行えるようになります。結果として、資産管理業務の効率化につながり、担当者の負担軽減にも寄与します。
IT資産管理台帳がない状態で、数百台規模の端末や複数拠点に分散したIT機器を管理するのはほぼ不可能と言ってよいでしょう。台帳を活用することで、そのような大量の資産でも抜け漏れなく把握でき、組織として統制を利かせやすくなります。
セキュリティリスクの低減
社内のIT資産を網羅的に管理することは、セキュリティリスクの低減にも直結します。
IT資産管理台帳を使って端末ごとのアップデート状況や契約情報を定期的にチェックすれば、脆弱性を悪用されるリスクを減らし、企業全体のセキュリティ強化につながります。紛失・盗難に対しても、資産台帳で管理しておくことで迅速に状況を把握し対応が可能になります。
さらに、誰がどの端末を使用しているかを台帳で管理しておけば、情報漏えいや不正利用の発覚時にも該当端末や担当者を素早く特定できます。社用デバイスが紛失・盗難に遭った場合にも、台帳を参照して端末の管理責任者や最終利用者を把握できるため、速やかな対処(リモートロックやデータ消去等)につなげることが可能です。
コスト最適化
IT資産管理台帳は、ITコストの最適化にも大きく貢献します。台帳を見れば、現在使用されていないパソコンや眠っているソフトウェアライセンスを容易に洗い出せます。その結果、遊休資産を有効活用したり、不要な購入を防いだりすることができます。
例えば、IT資産の利用状況が把握できていないと、実は未使用のPCが社内にあるにもかかわらず新入社員用に新たなPCを購入してしまい、結果的にコストが余計にかかってしまうケースがあります。IT資産管理台帳で「誰が・どの資産を・どれだけ使っているか」を明確にしておけば、このような重複投資を避け、リソースの再配分によってITコストの削減を実現できるでしょう。
さらに、使用されていないソフトウェアのサブスクリプション契約やクラウドサービスのアカウントを把握できれば、不要なライセンスを解約して費用削減するといったこともできます。また、資産の購入年度や耐用年数などの情報を台帳で管理することで、将来の買い替え時期を予測し、計画的に予算を確保するといった戦略的なコスト管理も可能になるでしょう。
コンプライアンス遵守
IT資産の適切な管理は、企業のコンプライアンス(法令遵守)にも寄与します。特にソフトウェアライセンスの使用状況を管理せず放置すると、知らないうちに契約上の許可数を超えるインストールを行ってしまい、ライセンス違反に問われるリスクがあります。ライセンス違反が発覚すると、違約金の支払いや信用失墜など、企業にとって大きなダメージとなりかねません。
また、情報セキュリティマネジメントの規格であるISMS(ISO 27001)においても、保有する情報資産の洗い出しと管理は要求事項の一つです。IT資産管理台帳はそうした外部監査や認証審査の際に、資産を適切に管理している証拠ともなります。
日頃から台帳でライセンスの使用状況も管理しておけば、ライセンス違反を防ぎ、企業のコンプライアンス遵守につながるでしょう。近年はソフトウェアベンダーによるライセンス監査が厳しくなっており、管理が不十分だと違約金を請求される場合があります。
IT資産管理台帳に記載必須の10項目
IT資産管理台帳を作成する際は、以下の10項目は最低限盛り込むことをおすすめします。これらの情報を網羅しておくことで、基本的な資産状況を把握しやすくなります。
- 管理番号:各資産に付与するユニークな識別ID
- 資産種別:PC、サーバー、ソフトウェアなど資産のカテゴリー
- 資産名(メーカー/型番):資産の名称やモデル名(ハードならメーカー・型番、ソフトなら製品名など)
- 所有・管理部門:その資産を管轄または所有している部署名
- 担当者(利用者):資産を実際に使用している担当者や所有者の氏名
- 設置場所:資産の設置先や保管場所(オフィス内の場所、在宅利用なら持ち出し状況など)
- 購入日:資産を取得した日付(購入日やリース開始日)
- 購入価格:資産の取得価格(金額)
- 保守サポート期限:メーカー保証や保守契約の有効期限
-
ライセンス契約情報:ソフトウェアの場合はライセンスの種類・有効期限・契約数など
IT資産管理台帳の作成方法
それでは、実際にIT資産管理台帳を作成し、運用していくための手順を6つのステップに沿って説明します。ここで紹介するステップに沿って進めれば、抜け漏れのない台帳が完成するはずです。もちろん自社の状況に応じて手順や内容を調整して構いません。各ステップを順に見ていきましょう。
STEP1:ガバナンスポリシーと目的を明確化
まずは、自社におけるIT資産管理の目的とルール(ガバナンス)を明確にしましょう。台帳を作成することで何を達成したいのか、どのような方針で運用するかを決めておくことが重要です。「セキュリティ強化のため全資産を漏れなく管理したい」「コスト管理に重点を置きたい」など、目的によって重点項目も変わります。
経営層や関連部署の理解と協力を得ることで、会社全体で統一された方針に基づいた運用体制を整えることも重要です。情報システム部門だけでなく各部門の現場担当者や経営層にもヒアリングを行うことで、ニーズを洗い出すと実態に即した方針を立てやすくなります。
さらに、社内に既存の情報セキュリティ方針や資産管理ルールがある場合は、それらに沿った目的設定・ルール策定を心がけましょう。
STEP2:IT資産の棚卸
次に、社内のIT資産をすべて洗い出します。パソコンやサーバーはもちろん、社用スマホやタブレット、ネットワーク機器、インストールされている主要なソフトウェアやクラウドサービスのアカウントまで、漏れがないように一覧化しましょう。
現物に資産管理番号のラベルを貼付して管理する場合は、このタイミングでラベリングも行います。社内の各部署に確認しながら、所有している全てのIT資産情報を収集することがポイントです。また、棚卸しは、休日や業務の少ない時期を選ぶなど、現場への影響を最小限に抑える工夫も大切です。
STEP3:管理項目(10項目+α)を設計
棚卸しで把握した資産情報を基に、管理台帳に記載する項目を設計します。基本となる項目は先述の10項目ですが、目的に応じて必要な情報を追加しましょう。例えば、セキュリティ対策を徹底したい場合はOSやソフトウェアのバージョン、IPアドレスなどを項目に加えると効果的です。
逆に不要な項目は省いて構いません。自社のニーズに合わせて柔軟に設計することで、使いやすい台帳に仕上げることができます。例えば、リース物件が多い場合はリース契約番号や期限、会計管理も兼ねるなら固定資産管理番号や減価償却状況、といった具合に、自社の事情に合わせてカラムを増やすことができます。
逆に重要でない情報は無理に盛り込まず、運用しやすさを優先しましょう。なお、管理番号の付与ルール(例:「PC-001」「SV-001」のように種別ごとに通し番号を振る等)もこの段階で決めておくと、運用時に資産を識別しやすくなります。
STEP4:フォーマットを用意(Excel/スプレッドシートなど)
管理項目が決まったら、その項目を列見出しとした台帳フォーマットを作成します。ExcelやGoogleスプレッドシートなど、お馴染みの表計算ソフトでシートを準備しましょう。自作が難しい場合は、インターネット上で公開されているテンプレートを利用するのも一つの手です。
ポイントは、後から項目の追加・変更がしやすいようシンプルな構造にしておくことと、社内で共有・編集がしやすい形にすることです(クラウド上で管理すればバージョン管理も容易です)。また、項目入力の際にプルダウンメニューを設定するなどして入力ミスを減らす工夫を取り入れると効果的です。さらに、台帳ファイルは定期的にバックアップを取り、万一に備えておきましょう。
STEP5:初期データ入力・データ品質チェック
用意したフォーマットに、棚卸しで収集した資産データを入力していきます。資産名や管理番号、日付などタイプミスが起こりやすい情報は特に注意し、正確に記載しましょう。全ての資産について必要項目の入力が完了したら、抜け漏れや誤りがないかデータ品質のチェックを行います。
例えば、存在しない資産が紛れ込んでいないか、重複登録がないか、日付や数字のフォーマットが統一されているかといった点を確認します。初期段階でデータの正確性を担保しておけば、後々の運用がスムーズになります。
必要に応じて初期版の台帳を関係部署にも回覧し、記載漏れの資産や誤情報がないか確認してもらうと安心です。各部署の担当者にも確認してもらえば、より確実です。また、資産名の表記ゆれ(メーカー名と型番の順序など)や日付・金額のフォーマット統一など、データを整理しておくことで後から検索・分析する際の手間が軽減されます。
STEP6:運用ルールの策定
最後に、作成したIT資産管理台帳を継続的に維持していくための運用ルールを定めます。
具体的には、新しい資産を購入・リースした際の登録手順や、不要になった資産の廃棄・売却時の台帳更新手順を明文化しておきます。また、定期的に棚卸しを実施し台帳を最新状態に保つサイクルも決めましょう(例えば年に1~2回、全社的な資産棚卸しを実施する等)。さらに、台帳の管理責任者や更新の担当者を明確に割り当てておくことで、「誰が」「いつ」台帳を更新するのかが分かり、情報更新漏れを防げます。
これらのルールを社内で共有し運用を徹底することで、IT資産管理台帳を長期的に有効活用できるようになります。また、資産を利用する従業員にもルールを周知し、異動や退職などで使用者が変更される際には、必ず担当者への報告を徹底させることも重要です。
IT資産管理ツール導入のメリットと注意点
台帳管理が複雑になってきたら、専用のIT資産管理ツールの導入を検討しましょう。スプレッドシートにはない自動資産発見や一括管理などの機能が利用できます。こうしたメリットにより、資産台数が多い場合でも人手に頼らず効率的に管理できるようになります。
<メリット>
- 資産情報の自動収集・更新により台帳管理の手間を大幅に削減できる
- 複数担当者でリアルタイムに情報共有・編集が可能
- ライセンス数やアップデート必要性などを自動検知・通知してくれる
<注意点>
- 導入コストが発生する(費用対効果の検討が必要)
- 初期設定や社内展開に時間がかかる場合がある
- 製品によっては自社の運用に合わず、現場で使いこなせない可能性もある
なお、管理対象が数十台程度の小規模であれば、まずはExcelで運用し、不便を感じた段階でツール導入を検討しても遅くありません。また、導入前に候補製品のトライアルで使い勝手を確認することで、現場で使いこなせないといった可能性を減らすことができるでしょう。
IT資産管理ツールの費用対効果
IT資産管理ツールの導入コストは決して安くありませんが、適切に活用できれば十分に費用対効果が見込めます。例えば、台帳管理に割いていた担当者の工数削減や、余分なIT機器の購入を防止できる効果を金額換算すれば、ツール導入費を上回るコスト削減につながるケースも多いです。
また、セキュリティ事故の未然防止やライセンス違反による罰金回避といったリスク低減効果も考慮すると、目に見えない損失を防ぐという意味で大きなメリットがあります。特に管理対象のIT資産が数百を超えるような中堅以上の規模では、ツール導入による効率化メリットが大きくなるでしょう。一方で、小規模で資産数が少ない場合は、まずExcelでの運用から始め、必要に応じてツール導入を検討するのがおすすめです。
さらに、IT資産管理の精度が向上すれば、「このPCは誰のものか」といった社内問い合わせ対応も円滑となり、情報システム担当者が他のコア業務に充てられる時間も増えるでしょう。ツール導入は単なるコストではなく、生産性向上への投資と捉えることができます。
IT資産管理台帳を活用してIT資産の効率的な管理を実現しよう
IT資産管理台帳は、社内のIT資産を「見える化」し、セキュリティやコストの面で最適な運用を行うための土台となるものです。
最初はExcelによる管理でも構いませんが、運用していく中で必要性を感じたら専用ツールの活用も検討し、会社の規模や状況に合った形でIT資産の効率的な管理を実現していきましょう。IT資産管理台帳は一度作成して終わりではなく、常に最新情報に更新してこそ効果を発揮します。まだIT資産を台帳で一元管理できていないという方は、この機会にぜひ台帳の整備を進めてみてください。




