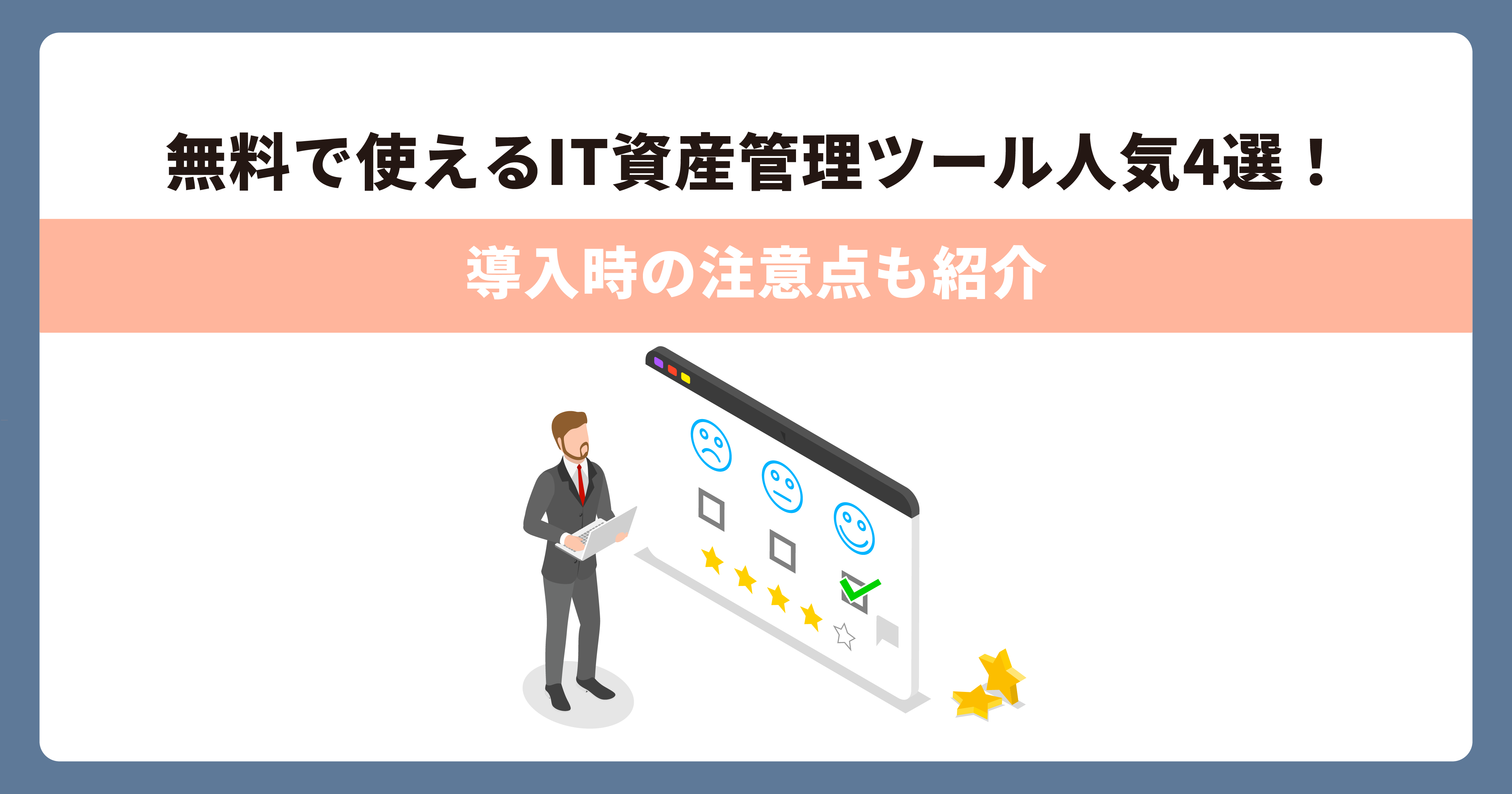
無料で使えるIT資産管理ツールおすすめ人気4選!導入時の注意点も紹介
社内のパソコンやソフトウェア、クラウドサービスのアカウントなど、企業が保有するIT資産は年々増加・多様化しています。これまではExcelなどでなんとなく管理できていたという企業も、テレワークの普及やクラウド活用の進展によって「何がどこにあるのか分からない」「ソフトのライセンス状況が不明」など、管理の限界を感じ始めているのではないでしょうか。そこで注目されているのが、無料で導入できるIT資産管理ツールです。
本記事では、コストをかけずに使えるおすすめのツール4選とその特徴、導入時の注意点、無料版から有料版へ移行すべき判断ポイントまでをわかりやすく解説します。導入の第一歩として、ぜひ参考にしてください。
目次[非表示]
IT資産管理とは?
IT資産管理とは、企業や組織が保有するパソコン・サーバーなどのハードウェア、インストールされているソフトウェアとそのライセンス、ネットワーク機器、クラウドサービスのアカウントなどあらゆるIT資産を一元管理することです。単なる資産リストの作成に留まらず、IT機器の導入・配備から日々の利用状況の把握、保守・更新、最終的な廃棄まで資産のライフサイクル全体を通じて管理します。これにより、IT資産の現状を正確に把握し、重複購入の防止によるコスト削減や、未許可ソフトウェアの利用防止によるセキュリティリスク軽減、さらにはライセンス超過利用の防止などを実現することが目的です。
無料で使えるおすすめのIT資産管理ツール4選
無料で利用できるIT資産管理ツールには、オンプレミス型のOSS(オープンソースソフトウェア)からクラウドサービス型まで様々な種類があります。本章では、特に代表的な無料ツールとしてSnipe-IT、GLPI、Ralph、そして日本発のクラウドサービスであるワスレナイの4つを紹介します。
Snipe-IT
Snipe-IT(スナイプIT)はWebベースのオープンソースIT資産管理ツールです。PCやソフトウェアライセンスはもちろん、プリンターなどの周辺機器や文房具などの消耗品まで幅広く登録・管理できる柔軟性が特徴で、社内のあらゆるIT資産を一元管理できます。資産ごとにシリアル番号や購入日、設置場所、利用者など細かな情報を登録でき、貸出状況の管理や画像添付によって視覚的に把握することも可能です。
また、保証期限の通知や、消耗品在庫のアラート機能も備えており、期限切れや在庫切れによるトラブルを未然に防げます。日本語UIやLDAP認証にも対応しており、自社サーバーにインストールして無料で利用できます。
公式サイト:https://snipeitapp.com/
GLPI
GLPIは、ITサービスマネジメント機能も備えたオープンソースのIT資産管理ツールです。開発開始は2003年と古くから継続して改良が重ねられており、世界的に利用されています。特徴は、資産を細かくカテゴリ分類して管理できる点で、あらかじめ30種類以上の資産タイプ(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク機器など)が用意され、それぞれに豊富な項目を記録できます。
社内のインシデント管理やヘルプデスク機能と統合できるため、資産情報とサポート情報を一元化した運用も可能です。また、検索機能も強力で、複雑な条件での資産の絞り込みや検索条件の保存にも対応しています。
一方で、あらかじめ用意された項目が多く、運用の自由度はやや低く、使用しない項目であっても入力を求められる場合があります。中小規模の環境であれば十分に実用的ですが、大量の資産を扱う場合には、サーバーリソースの消費や設定の煩雑さに注意が必要です。
公式サイト:https://glpi-project.org/
Ralph
Ralph(ラルフ)は、ポーランドのAllegro社が開発するオープンソースのIT資産管理ツールで、データセンター向けに特化した設計が特徴です。サーバーラックやネットワーク機器などのインフラ資産の管理を想定しており、あらかじめ詳細な分類と項目が設定されています。
資産購入から廃棄までのライフサイクル管理やライセンス管理といった基本機能に加え、柔軟なワークフロー設定をはじめ、複雑な資産管理を支援する高度な機能も備えています。強力な検索機能も備えており、複数条件でのフィルタリングや検索クエリの保存が可能で、大量の資産から必要な情報を素早く引き出せます。
ただし、GLPIと同様に項目や分類があらかじめ固定されているため、運用の自由度はやや低く、運用にはツールの仕様に合わせた情報入力が求められます。データセンター級の資産管理が必要な場合には有力な選択肢ですが、一般的な中小企業がPCや周辺機器を管理する目的で利用するには、機能が多すぎて運用が複雑になる場合もあるでしょう。
公式リポジトリ:https://github.com/allegro/ralph/
ワスレナイ
ワスレナイは、日本企業である株式会社SHIFTが提供するクラウド型のIT資産管理ツールで、すべての機能を永年無料で利用できる点が最大の特徴です。インストール不要のSaaSとして提供され、Web上でアカウント登録するだけですぐに利用を開始できます。
社内のハードウェア資産だけでなく、Google WorkspaceやSlackなど多様なクラウドサービス(SaaS)の利用状況やアカウントを一元的に管理できます。具体的には、各SaaSの契約プランやアカウント数、利用料金、更新日を可視化し、未利用アカウントの検出や、シャドーIT(無許可のクラウド利用)の発見にも対応しています。
さらに、入退社時のアカウント発行・削除の自動化や契約更新通知などにも対応しており、情報システム部門の負担を大きく削減できます。「無料で全機能が使える」という点は経営層への説明もしやすく、提供元による導入サポートも受けられるため、初めて資産管理ツールを導入する企業にもおすすめできるサービスです。
公式サイト:https://lp.wasurenai.jp/
なぜIT資産管理ツールが必要とされているのか?
現代の企業では、テレワークの普及やクラウドサービス利用の拡大に伴い、管理すべきIT資産が増加・多様化しています。従来はExcelや紙の台帳でPCやソフトの管理が可能だった規模でも、社員が50~100人を超え、PC・スマホ・周辺機器・ソフトウェア・クラウドアカウントと対象が膨らむにつれて手作業での把握は困難になります。
その結果、「どの部署にどんな端末が何台あるか把握できない」「ソフトウェアの契約ライセンス数が不明で監査が不安」といった声がよく聞かれます。実際、資産の利用状況を管理できず所在不明のデバイスが出たり、更新漏れのソフトが放置され、セキュリティリスクになるケースもあります。また、ライセンス違反(契約数以上のソフト利用)は監査で多額の賠償金請求につながる恐れもあり、IT資産管理の重要性は年々高まっています。
IT資産管理ツールを導入すれば、資産情報を自動収集して常に最新の台帳を維持でき、棚卸し作業の効率化、コストの適正化、不正利用防止とコンプライアンス遵守といった効果が期待できるのです。
IT資産管理ツールの基本機能
一般的なIT資産管理ツールには、企業内のIT資産を適切に管理するために次のような基本機能が備わっています。それぞれの機能を押さえておくと、ツール選定や運用の際に「何ができるのか」「どこまで自動化できるのか」を把握しやすくなります。
IT資産の一元管理
社内に点在する様々な資産情報(端末のスペック、設置場所、ユーザー情報、ソフトウェア契約情報など)を一箇所のシステムでまとめて管理できるのがIT資産管理ツールの最大の強みです。個別のExcel台帳では部署ごと・資産カテゴリごとに情報が分散しがちですが、ツール上で一元管理することで「何がどこにいくつあるか」を瞬時に把握できます。
また、クラウド型ツールであればインターネット経由で社外からでも最新の資産台帳にアクセスでき、リモートワーク環境でも一貫した管理が可能です。
インベントリ管理
インベントリ管理とは、端末やソフトウェアの構成情報を収集して資産台帳を最新化する機能です。多くのIT資産管理ツールでは、管理対象のPCにエージェントプログラムをインストールしたり、ネットワーク経由でスキャンすることで、OSやソフトの種類・バージョン、搭載メモリ容量、周辺機器の接続状況などを自動検出できます。
この機能により、手作業で一台一台スペックを確認したり、ソフトウェア一覧を人力で更新するといった負担が大幅に軽減されます。例えばリモートワーク中の社員PCでも、オンラインにさえなっていれば定期的にインベントリ情報を収集し、管理者はオフィスにいなくても各資産の状態を把握可能です。
ライセンス管理
企業が保有するソフトウェアのライセンス数や契約状況を把握し、適切に利用するための機能です。IT資産管理ツールでは、インストールされているソフトウェア情報と購買済みのライセンス契約数を紐付けて管理し、ライセンス超過利用の防止や契約更新の漏れ防止をサポートします。例えば、各PCのソフト一覧を集計し、利用中のライセンス数が契約上限を超えていないか自動でチェックできます。
また、未使用ソフトがあればライセンスを回収して別の必要な部署へ再配分するといったコスト最適化も可能です。ライセンス満了日が近づいた際に通知を出したり、契約証書を台帳に添付して、監査時の提出に備えることが可能です。
契約管理
IT資産に関する様々な契約情報を管理する機能です。ハードウェアであればリース・レンタル契約や保守サポート契約、ソフトウェアであれば利用期限やサブスクリプション契約の更新日、クラウドサービスであれば契約プランや月額費用など、資産ごとの契約内容をひとまとめに記録できます。契約満了が近づいた際にアラートを出し更新判断を促す機能や、契約書PDFを資産情報に添付しておき必要時にすぐ参照するといった使い方も可能です。
契約管理を徹底することで、「気づいたらサポート期限が切れていた」「自動更新で不要な契約を続けていた」といった事態を防ぎ、適切な更新・解約のタイミングを逃さないようにできます。
アラート機能
各種のアラート(通知)機能もIT資産管理ツールには欠かせません。上記のような契約期限の迫った資産や、保証期限が近づいているハードウェア、残りわずかになった消耗品がある場合に、事前に管理者へメール通知することで対策の抜け漏れを防ぎます。特に大量の資産を抱える環境では、人力で期限管理するのは困難ですが、ツールのアラート機能によって「知らないうちに期限が切れていた」というリスクを大幅に低減できます。
また、異常を検知した際にダッシュボード上で警告を表示したり、棚卸し未実施の拠点がある場合にリマインドを出すといったツールもあります。
無料のIT資産管理ツールを導入する際の3つの注意点
コストを抑えて導入できる無料のIT資産管理ツールですが、利用にあたって注意しておきたいポイントがいくつかあります。特に次の3点については事前に理解した上で、自社の要件に適合するか検討しましょう。
機能や台数制限があり、大規模運用は難しい
無料で使えるツールは多機能とはいえ、有料のエンタープライズ製品と比べるとどうしても機能面で劣る部分があります。また、クラウドサービスの無償プランの場合、資産数やユーザー数に上限が設けられているケースも多く、数百台規模以上の環境では十分な管理が難しくなるでしょう。
OSSの場合ライセンス上の資産数制限はありませんが、自前サーバーで運用するため規模が大きくなるとサーバー増強やDBチューニングなど技術的ハードルが高まります。一般に、PC台数が数十台程度で基本的な台帳管理ができれば良い段階では無料ツールでも選択肢になりますが、数百台以上を管理したり高度なセキュリティ連携が必要な場合は有料製品の方が現実的です。
セキュリティ更新・サポートが自己責任
無料のOSSツールを導入する場合、ベンダーからの公式サポートがない点に留意が必要です。インストールや設定方法はコミュニティのドキュメントを参照し、自社で試行錯誤しながら構築するケースが大半です。不具合やトラブル発生時も、自力で調査・解決するか、ユーザーフォーラムで情報収集する必要があります。有料版であればサポート窓口に問い合わせて迅速に解決できるような問題も、フリーソフトでは対応に時間を要するかもしれません。
また、セキュリティアップデートの適用も自己責任となります。脆弱性が公表された際に速やかにソフトウェアをアップデートしなければ、資産管理ツール自体が情報漏えいの起点となるリスクもあります。IT担当者のリソースが限られる中で、こうしたメンテナンスまで自前で賄うのは難しい場合、サポート付きの有償版導入を検討すべきでしょう。
他システム連携や将来の移行の隠れコスト
無料ツールは単体で使う分には低コストですが、既存の社内システムとの連携や将来的な他製品への乗り換えに際して、見えにくいコストや手間が発生することがあります。
例えば、人事システムやデバイス管理(MDM)ツールなどとデータ連携させたい場合、OSSではAPIが十分用意されておらず個別開発が必要になるケースがあります。また、無料版から有料版へ移行する際に資産データをエクスポートしてインポートし直す必要があったり、項目の互換性問題で移行作業に工数がかさむことも考えられます。
あらかじめ連携ニーズや将来のスケールアップ計画を見据えて、選定段階でそのツールが柔軟に対応できるか確認しておくことが重要です。
無料版から有料版へ移行する判断ポイント
実際に無料の資産管理ツールを使い始めても、運用の中で「そろそろ有料版を検討すべきか」と感じるタイミングが訪れることがあります。以下のようなポイントを判断材料に、必要に応じて有料製品への移行を検討しましょう。
資産数の上限達成
フリープランに資産台数やユーザー数の上限が設定されている場合、その上限に近づいた時点が乗り換え検討のサインです。上限を超えてしまうとそれ以上登録できなくなり運用に支障をきたすため、早めに有料プランへのアップグレードや他製品への移行を計画する必要があります。
また、OSSの場合でも管理対象が増えすぎると現在のツールではパフォーマンスが追いつかなくなる可能性があります。レスポンスが極端に遅くなる、データベース容量が逼迫する、といった兆候が見えたら要注意です。
ガバナンス・監査要件の強化
組織の成長や業種的な要請により、資産管理に対するガバナンスや監査対応の要求が高度化した場合も、上位ツールへの切り替えを検討すべきです。
例えば内部統制の一環で資産管理のログを厳格に残す必要が出てきたり、より詳細なアクセス権限管理や証跡レポートが求められたりするケースです。無料ツールではログの保存期間が短かったり、監査レポートの自動生成機能が乏しいことがあります。そうした要件強化に伴い、エンタープライズ向けの有料製品(統制機能が充実しているもの)への移行が必要になるでしょう。
他システム連携・自動化ニーズの急増
資産情報を他のIT管理システムと連携させたり、社内のワークフローに組み込んで自動化を進めたいというニーズが高まった場合も、無料ツールでは限界があるかもしれません。
例えば、ソフトウェア配布ツールやID管理システムとリアルタイムにデータ同期したり、資産管理ツール上で申請・承認のプロセスを回すといった高度な運用を目指す場合です。OSSでもAPI提供があれば対応可能なケースもありますが、複雑な統合には多大な開発工数がかかる場合もあります。有料のエンタープライズ製品であれば、他製品との連携モジュールや包括的な自動化機能が備わっていることが多いため、ニーズに合わせて移行を検討しましょう。
IT部門の運用負荷の限界
ツール自体の運用・保守にIT部門のリソースが割かれすぎて本来の業務に支障が出ている場合も、転換のタイミングです。無料のOSSではアップデート対応やバックアップ、障害対応まで自社で担う必要があり、台数増加と比例して運用負荷も増大します。
最初は無料で始めたものの、定着するにつれて「社内で管理しきれない」「担当者が他業務と兼任で限界」と感じる場合、思い切ってサポート付きの有料版へ切り替えることで運用負荷を外部に委託できます。特に情シス人員が少ない企業では、ツール運用自体が目的化してしまう前に、本来のIT戦略に集中できる環境を整えることが重要です。
まずは無料のツールを活用して、IT資産管理の第一歩を踏み出そう
IT資産管理は一朝一夕には確立できませんが、まずは手軽に始められる無料ツールで現状の可視化から着手するのがおすすめです。小規模なうちはコストをかけずに運用ノウハウを蓄積し、実際に使ってみる中で自社に足りない機能や運用上の課題が見えてくるでしょう。そのタイミングで有料版への移行や別製品の導入を検討すれば、やみくもに高額なソフトを導入するより失敗が少なく、納得感のある選択ができます。
ぜひ、本記事で紹介したような無料のIT資産管理ツールを活用して、自社のIT資産を適切に管理するための第一歩を踏み出してみてください。




