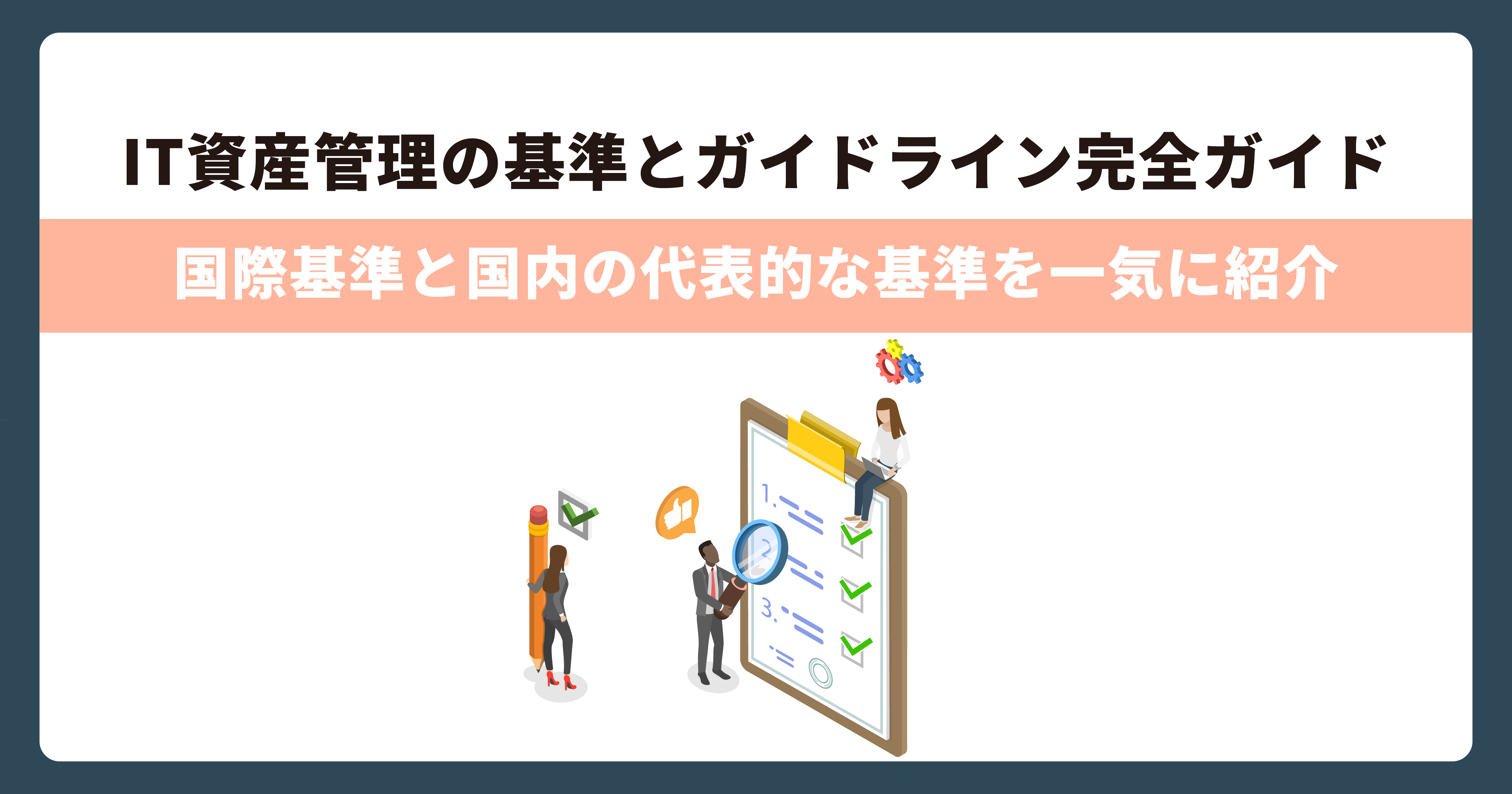
IT資産管理の基準とガイドライン完全ガイド──国際基準と国内の代表的な基準を一気に紹介
クラウドサービスやサブスクリプション型ソフトウェアの普及により、企業が保有・利用するIT資産は年々複雑化しています。こうした中で、重複投資の防止やライセンス違反リスクの回避、さらにはセキュリティの強化を実現するためには、「IT資産管理基準」の整備が欠かせません。
本記事では、IT資産管理に関する国際的なフレームワーク(ISO/IEC 19770シリーズ、ITIL、COBIT)と、日本国内で活用されているガイドライン(ISMSやSAMAC基準)について解説します。また、基準策定に必要な現状分析やKPI設定のポイントについても紹介しますので、自社に最適なIT資産管理体制を構築するためのヒントとして、ぜひお読みください。
目次[非表示]
IT資産管理基準とは?
IT資産管理基準とは、企業が保有するハードウェア・ソフトウェア・クラウドサービスなどのIT資産を、その取得から運用・廃棄に至るライフサイクル全体で適切かつ効率的に管理するための方針や枠組みです。
これが整備されていないと、重複投資やライセンスの不正利用、セキュリティリスクの増大などさまざまな問題が発生しかねません。そのため国際的なフレームワークや国内ガイドラインが整備されており、各企業もそれらを参考に自社の実情に合わせたルール作りが求められています。
IT資産管理基準の策定が求められる理由
IT資産の多様化と管理難易度の増加
クラウドサービスの普及やサブスクリプション型ソフトウェアの増加により、管理すべきIT資産が従来より多様化しています。従来の管理方法では全体像を把握しきれなくなり、未管理の資産が発生するリスクが高まっています。
未管理資産によるリスク
IT資産の全容を正確に把握できないと、未使用のソフトウェアライセンスが放置されたり、古いデバイスにセキュリティホールが残ったりする可能性があります。こうした未管理資産はセキュリティインシデントやライセンス違反など重大なリスクにつながります。
コスト増大と重複投資
明確な評価基準がないまま資産管理を行うと、不必要な資産を維持したり、同じソフトを重複購入したりなど、ITコストが無駄に増大する恐れがあります。基準を設けて資産の価値や利用状況を定期評価すれば、こうした無駄な支出を削減できます。
法令遵守と企業信頼性
ソフトウェアのライセンス違反や管理不備による法的トラブルを防ぐためにも、資産ごとに明確な管理ルールが必要です。しっかりとしたIT資産管理基準を策定し運用することは、コンプライアンスを徹底し企業の信頼性向上にも寄与します。
IT資産管理の国際基準
IT資産管理を体系的に進めるには、国際的に認知された標準規格やフレームワークを参考にすることが有効です。こうした国際基準は、自社でルールを策定する際の土台となり、外部監査やコンプライアンス対応の強化にも役立ちます。
ISO/IEC 19770 シリーズ
ISO/IEC 19770シリーズはIT資産管理、特にソフトウェア資産管理(SAM)に関する国際標準規格です。単なる資産の台帳管理に留まらず、企業に必要なソフトウェアを最適に利用することを目的として定められています。
ソフトウェアの検出・識別方法からライセンス管理、運用プロセスまで包括的なベストプラクティスが示されており、ソフトウェア導入から利用・更新・廃棄まで一貫した管理体制を構築する際に参考になります。IT資産のライフサイクル全体で管理プロセスを標準化することで、重複購入の防止や利用効率の向上に役立ちます。
ITIL
ITIL(Information Technology Infrastructure Library)は、ITサービスマネジメント(ITSM)のベストプラクティスをまとめたフレームワークです。実際のビジネス環境で効果が証明された手法の集大成であり、世界的に広く評価・採用されています。経営層から現場のIT担当者まで組織横断で共通の指針として活用できる点が特徴で、ITサービスの品質向上や効率化に寄与します。
IT資産管理においても、単なる物品の在庫管理ではなく、ビジネス価値を生み出す戦略的な活動として資産を捉える視点を提供してくれます。ITILのプロセスを取り入れることで、IT資産管理を含むIT運用全体を継続的に改善する仕組み作りが可能です。
COBIT
COBIT(Control Objectives for Information and Related Technology)は、ITガバナンスとITマネジメントの両立を支援するフレームワークです。企業の経営層とIT部門との橋渡し役を果たす構成となっており、IT戦略とビジネス戦略の整合性を高めるのに有用です。
具体的には、組織内で活用されるITリソースやサービスについて管理目標を明示し、それを実現するための評価指標(KPI)や実践的なコントロール項目が整理されています。これによりビジネス目標とIT目標を紐付け、企業価値の向上につながるIT資産管理の仕組みを構築する助けとなります。COBITの採用によって、内部統制や監査の観点からも抜け漏れのない包括的なIT資産管理体制を整えられるでしょう。
国内の代表的なIT資産管理の基準・ガイドライン
次に、国内で参照されている代表的なIT資産管理の基準やガイドラインを紹介します。日本におけるこれらの基準には、法令遵守や内部統制の強化につながる要素も多く含まれています。自社の運用実態に合わせてうまくカスタマイズしつつ活用するとよいでしょう。
「情報セキュリティ管理基準(ISMS)」経済産業省
経済産業省が策定した「情報セキュリティ管理基準」は、企業や組織が情報資産(IT資産を含む)を適切に保護し、リスク管理を遂行するためのガイドラインです。この基準はISO/IEC 27000シリーズ(JIS Q 27000シリーズ)に準拠しており、ISMS認証制度の基準とも整合しています。
情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の一環として、ハードウェアやソフトウェアを含む資産の取り扱い方針や管理策が示されており、資産の機密性・完全性・可用性を守るための管理措置が重視されています。
ISMSを導入することで、資産ごとのリスク分析や適切な管理策の選定が体系的に行えるようになり、IT資産管理体制をセキュリティの視点から強化できます。特に外部委託やクラウド利用が進む現代では、セキュリティ対策と資産管理を両立するための有効な指針となるでしょう。
「IT資産管理基準」一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)
一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)が提供する「IT資産管理基準」は、企業が統制の取れたIT資産管理を行うための包括的な基準です。IT資産の管理領域をいくつかのカテゴリに分類し、それぞれに管理目標・要件・具体的な管理項目が設定されています。
対象とする資産はハードウェア、ソフトウェアだけでなくクラウドサービスやネットワーク機器など多岐にわたり、業種や企業規模を問わず適用できる内容になっています。例えば、資産の登録・台帳整備、日常の運用管理から監査対応まで視野に入れた項目が含まれており、企業内のIT資産を漏れなく管理する指針となります。
また、この基準はISO/IEC 19770シリーズなど国際規格にも整合して策定されており、定期的な評価による改善サイクルの導入も推奨しています。これによりIT資産の可視化と継続的な最適化を図ることが可能です。
ISMSとSAMAC基準の違い
目的・フォーカス
ISMSの情報セキュリティ管理基準は、情報資産全体のセキュリティ確保とリスク低減が目的であり、機密性・完全性・可用性の維持に重点を置いています。一方、SAMACのIT資産管理基準はIT資産のライフサイクル管理に焦点を当て、資産の効率的な利活用やライセンスコンプライアンスの確保、コスト最適化を目指すものです。
適用範囲
ISMSは組織の情報資産全般(人、情報、ハード・ソフト等すべて)を対象に含み、セキュリティ管理の観点から資産管理を位置付けています。これに対し、SAMAC基準はIT機器やソフトウェアといったIT資産に特化した基準であり、これら有形無形のITリソース管理に関する詳細な手順を提供します。
標準規格/認証
ISMSの基準はISO/IEC 27001および27002に準拠しており、公的なISMS認証の取得を通じて第三者認証を受けることが可能です。一方、SAMACのIT資産管理基準はISO/IEC 19770-1(ITAM規格)に整合した国内標準で、国際規格に直接の認証スキームはありませんが、SAMACによる成熟度評価制度(ユーザー企業成熟度認定)などが存在します。
管理内容・アプローチ
ISMSでは資産目録の作成や管理責任者の明確化など、情報資産を守るための管理策がセキュリティ基準の一部として示されています。SAMAC基準では、資産台帳の整備方法やソフトウェアライセンスの棚卸手順、無断使用を防止する統制手段など、より具体的で実務に即した管理プロセスが詳細に定義されています。
そのため、ISMSは「何を守るか」という視点が強く、SAMAC基準は「どのように管理するか」という実践面での指針が充実していると言えます。
補完関係
両者は対立するものではなく、むしろ補完関係にあります。ISMSで情報資産のリスク管理基盤を構築しつつ、SAMAC基準を活用して日常のIT資産運用管理を徹底することで、セキュリティと効率性の両面から万全のIT資産管理体制を築くことができます。
例えばISMSで要求される資産目録の作成・管理を、SAMAC基準に沿って詳細に実施すれば、監査対応もスムーズになるでしょう。また、SAMACの実践で得られた資産管理データは、ISMSのリスク評価や是正措置の検証にも役立ちます。
IT資産管理基準の策定の際のポイント
自社独自のIT資産管理基準を策定するにあたっては、以下のポイントを意識することが重要です。外部のフレームワークを参考にしつつも、自社の実情に適した管理体制を設計する必要があります。
現状分析を行い、目標を設定する
まずは自社のIT資産管理の現状を客観的に分析しましょう。どんなIT資産がどれだけ存在し、各資産がどのように利用・管理されているかを可視化することで、運用上の課題や改善の余地が明らかになります。例えば未使用のまま放置されている資産がないか、部門ごとにバラバラなルールで管理されていないかなどを洗い出します。
現状を正しく把握できたら、次に何を目的として基準を策定するのかを明確に設定します。コスト削減なのか、セキュリティ強化なのか、ライセンスコンプライアンス遵守なのかなど、目的が定まれば基準に盛り込むべき内容や優先度が見えてくるでしょう。
リスクやコストから管理対象の範囲を決定する
IT資産管理の目的が定まったら、具体的にどの資産を管理対象に含めるかを決定します。ハードウェア・ソフトウェアはもちろん、クラウドサービスや外部ストレージ、モバイル端末、ネットワーク機器など、組織によって管理すべき対象は様々です。すべてのIT資産を網羅的に管理するのが理想ではありますが、実務上はリスクやコストに応じて優先度を付けることが求められます。
例えば、機密データを扱うサーバーやセキュリティリスクの高い端末、ライセンス契約上の制約が厳しいソフトウェアなどは優先的に厳格な管理体制を敷くべきでしょう。自社のリスク評価や費用対効果を踏まえて、どこまでを詳細管理し、どこから先は定期チェック程度に留めるか、といった線引きを行います。
既存のフレームワークを雛形に自社向けにカスタマイズを行う
ISOや業界標準のフレームワークは有用な雛形となりますが、それらをそのまま適用しても定着しない場合があります。既存のガイドラインを参考にしつつ、自社の環境や業務フローに合わせてルールやプロセスを調整することが大切です。例えば、ISO/IEC 19770-1やSAMAC基準に含まれる管理項目をチェックリストとして活用し、自社で不要な項目は省略・簡略化し、必要な独自項目を追加するといったカスタマイズを行います。
具体的な管理ルールを設計する際には、IT資産のライフサイクル全体で誰が何をするかを定義し、社内規程や手順書に落とし込むとよいでしょう。
また、管理台帳の様式や運用方法も自社に適した形にします。スプレッドシートなど簡易な方法から開始して徐々に整備しても構いませんが、可能であれば専用のIT資産管理ツール導入も検討しましょう。重要なのは、自社の実態にマッチしたルールにすることで、現場で無理なく運用できる基準に仕上げることです。
KPIを設定し、期間を決めてPDCAを回す
IT資産管理は基準を作って終わりではなく、継続的に改善していくプロセスです。そのため、効果測定の指標(KPI)を設定し、定期的に見直しを行う仕組みを組み込みましょう。
例えば「未使用ソフトウェアの棚卸で削減できたコスト」「ライセンス違反ゼロの継続期間」「資産台帳の更新遅延件数」など、管理状況や成果を測れるKPIを決めておきます。これらの指標を四半期ごとや半年ごとにチェックするなど、PDCAサイクルを回す期間を定めて運用しましょう。
定期的な監査や棚卸を実施し、その結果をもとに基準や運用プロセスをアップデートすることが重要です。ビジネス環境やIT技術は常に変化していますので、定期的なレビューと改善によって基準の内容も進化させ、組織にフィットし続けるものにしていきます。
IT資産管理のガイドラインを策定し、IT資産を効率的に管理しよう
IT資産管理基準やガイドラインの策定は、企業におけるIT運用の土台を強固にする重要なステップです。国際基準や国内ガイドラインの要点を押さえつつ、自社の実情に適ったルールを設けることで、重複投資の削減やセキュリティリスクの低減、ライセンスコンプライアンスの徹底といった効果が期待できます。
今回紹介したISO/IEC 19770シリーズやISMS、SAMAC基準などは、有用なベースラインとチェックリストになりますので、積極的に活用してみましょう。策定したガイドラインは現場で運用してこそ価値を持ちます。定期的にその運用状況を評価し、必要に応じて改訂を加えながら、継続的な改善(PDCAサイクル)を回していくことが肝要です。自社に合ったIT資産管理の仕組みを構築し、IT資産を効率的かつ安全に管理していきましょう。




