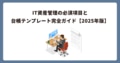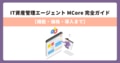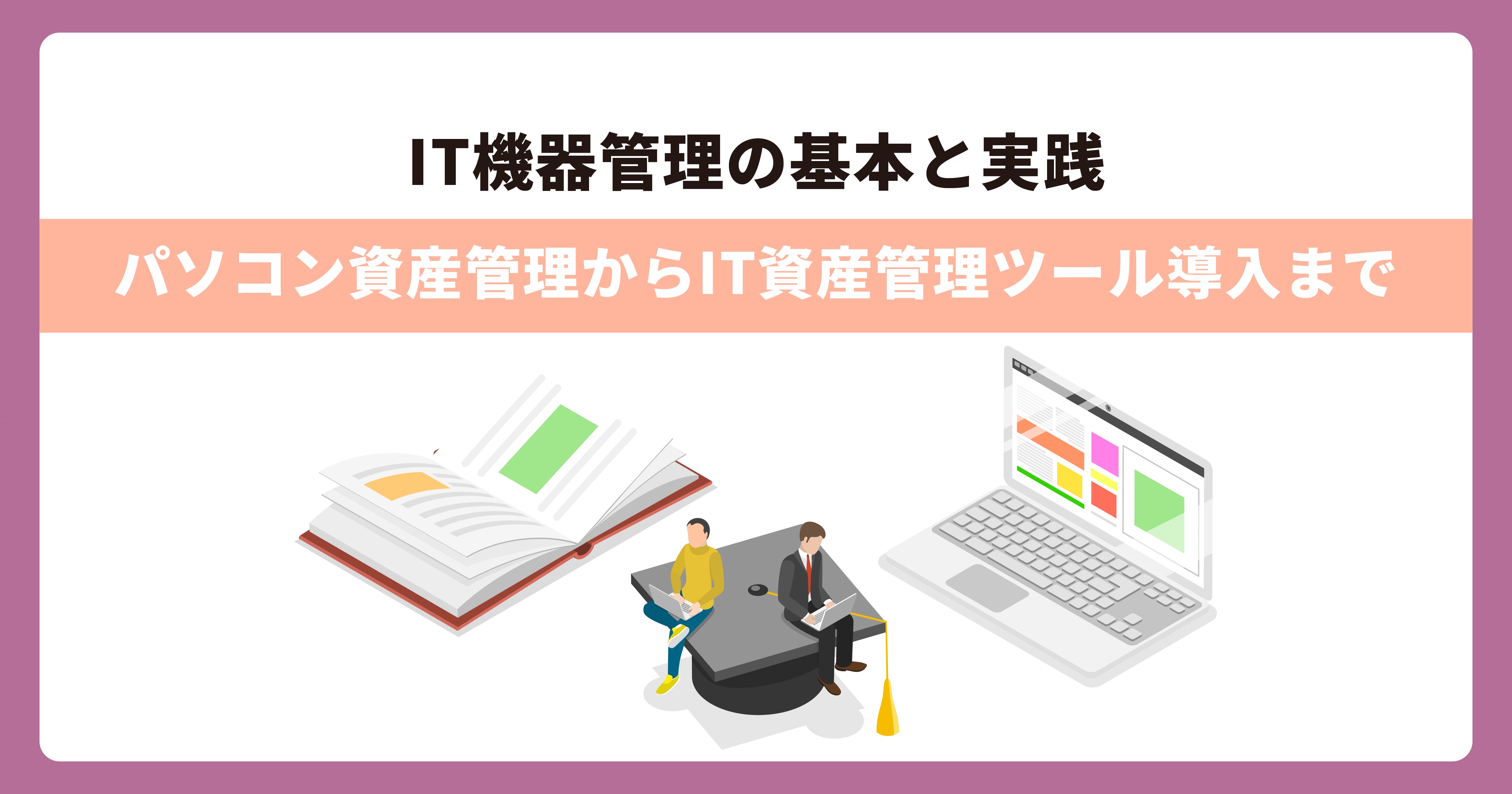
IT機器管理の基本と実践|パソコン資産管理からIT資産管理ツール導入まで
近年、リモートワークの普及やデバイスの多様化に伴い、社内で扱うIT機器(情報機器)の管理がますます重要になっています。パソコンやスマートフォンといった端末はもちろん、ソフトウェアやクラウドサービス契約などの“見えない資産”まで含めた統合管理が求められる時代です。適切なIT機器管理を導入することで、セキュリティ強化やコスト最適化など多くのメリットが得られます。
本記事では、IT機器管理の基本から具体的な実践方法、さらにはIT資産管理ツールの比較や導入ステップまでを詳しく解説します。ぜひ自社の情報システム管理にお役立てください。
目次[非表示]
- 1.IT機器管理とは?
- 1.1.IT機器とOA機器の違い
- 1.2.IT機器管理とIT資産管理の違い
- 2.IT機器管理を導入する目的
- 2.1.情報漏えいリスクを低減する
- 2.2.機器の所在・利用状況を可視化する
- 3.IT機器管理の基本ステップ
- 3.1.台帳作成とラベリング
- 3.2.棚卸し・貸出返却フローの設計
- 4.IT機器管理を効率化するツールの選び方
- 4.1.機能の網羅性
- 4.2.使いやすさ・操作性
- 4.3.自社規模・業務に合った柔軟性
- 4.4.価格・コストパフォーマンス
- 4.5.セキュリティと外部連携性
- 5.IT資産管理ツールおすすめ10選を比較
- 5.1.SKYSEA Client View
- 5.2.System Support best1〈SS1〉
- 5.3.LanScope Cat
- 5.4.AssetView
- 5.5.ManageEngine Endpoint Central
- 5.6.Jamf Pro
- 5.7.Lansweeper
- 5.8.Microsoft Intune
- 5.9.ServiceNow IT Asset Management
- 5.10.Snipe-IT
- 6.IT機器管理ツール導入の手順
- 6.1.現状分析とゴール設定
- 6.2.要件定義とツール選定
- 6.3.パイロット検証とデータ整備
- 6.4.本番環境構築・運用開始
- 6.5.運用定着と効果改善
- 7.自社に合ったIT機器管理を導入し、効率と安心を両立しよう
IT機器管理とは?
IT機器管理とは、企業や組織が保有するパソコンやサーバー、プリンターなどの情報機器について、その保管場所や利用状況を把握・記録する一連の管理活動を指します。社内に点在する多種多様なデバイスをリスト化し、いつ誰がどこで使用しているか、故障や紛失はないかなどを継続的に追跡します。情報セキュリティ上、IT機器の適切な管理は欠かせず、また近年では業務効率化の観点からも多くの企業がIT機器管理の強化に乗り出しています。
IT機器とOA機器の違い
「IT機器」とよく似た言葉にOA機器があります。OA機器とは“オフィスオートメーション機器”の略で、オフィス業務の自動化に欠かせない機器を指します。一般的には電話・パソコン・コピー機・FAX・シュレッダーなどがOA機器と呼ばれ、従来から事務作業に使われてきたハードウェア類です。
一方、IT機器はこれらOA機器を含みつつ、ネットワーク機器やサーバー、モバイル端末など情報技術全般に関わる機器を指すより広い概念です。つまりOA機器は主にオフィス内で使用する事務機器のことであり、IT機器はOA機器も含めた企業のITインフラ全体を支えるデバイス類と考えるとよいでしょう。
IT機器管理とIT資産管理の違い
混同されやすい用語にIT資産管理があります。IT資産管理(ITAM: IT Asset Management)は、企業が保有・利用するあらゆるIT資産(ハードウェア、ソフトウェア、データ、ライセンス等)を一元管理し、その利用状況やコスト、リスクを可視化・最適化する手法です。管理対象の範囲に違いがあり、IT資産管理では無形資産であるソフトウェアやデータファイルまで含めて管理します。そのため、ネットワークを通じたモニタリングや専用ソフトによる遠隔操作など大がかりな管理手法が必要です。
一方のIT機器管理は、有形資産であるデバイス類に対象を限定し、管理ラベルや管理台帳を用いた物理管理が中心となります。大掛かりな仕組みを必要としない場合は、まずIT機器管理から着手するのが現実的でしょう。
IT機器管理を導入する目的
適切なIT機器管理を行うことは、企業にさまざまな利点をもたらします。ここでは主な目的を2つ取り上げます。
情報漏えいリスクを低減する
企業のPCやスマホなどには機密情報が多数含まれており、紛失・盗難や不正利用が起これば情報漏えいにつながります。IT機器の利用状況や保管場所、社外への持ち出しを厳格に管理することで、内部関係者による不正持ち出しや外部へのデータ流出リスクを大幅に下げることができます。
具体的には、誰がどの端末を使用しているか常に把握し、紛失時には速やかに発見・対応できる体制を整えます。また、持ち出しの際の申請ルールやデータ暗号化の徹底など、IT機器管理は情報セキュリティ対策の根幹として機能します。
機器の所在・利用状況を可視化する
社内にある機器の現在の所在や使用状況をリアルタイムに把握できるようになることも、IT機器管理導入の重要な目的です。とくにテレワーク拡大により、会社所有のノートPCやモバイル端末が社外に持ち出される機会が増えています。システム上で各デバイスの保管場所や利用者、使用期間を見える化すれば、離れた拠点にある端末も一元管理が可能です。
これにより、遊休機器の発見や重複購入の抑制といったコスト最適化にもつながります。さらに、利用状況データを分析することで、最適な機器配備計画を立てたり、不要な端末の廃棄・売却による経費削減を図ることもできるでしょう。
IT機器管理の基本ステップ
IT機器管理をゼロから始める際には、いくつかの基本的なステップを踏む必要があります。以下では、その代表的な手順を紹介します。
台帳作成とラベリング
まず、社内のすべてのIT機器を洗い出して管理台帳を作成します。拠点が複数ある場合は情報を集約し、一元的に管理しましょう。台帳には機器名、製造番号、スペック、購入日、使用者、保管場所など必要な項目を過不足なく記入します。
次に、各機器にユニークな識別IDを割り振り、対応する管理ラベル(資産シール)を端末本体に貼付します。このラベリングによって、機器と台帳情報が紐付けられ、現物確認が容易になります。台帳とラベルを整備することが、IT機器管理の出発点となります。
棚卸し・貸出返却フローの設計
初期台帳の整備後は、運用フローを構築します。定期的に実施する棚卸し(実物資産の確認)の手順を決め、担当者や頻度を明確にしましょう。例えば年に1~2回、ラベルのQRコードやバーコードをハンディ端末でスキャンし、台帳データと突合することで効率的に棚卸しを行う方法があります。
また、社員への機器貸出し・返却手順も整備します。誰がどの端末をいつ借り出し、いつ返却したか記録し、未返却や紛失を防ぐ仕組みを作ります。申請書や貸出管理簿のフォーマットを用意し、承認フローを定めておくとよいでしょう。こうした棚卸しサイクルと貸出ルールの確立により、運用開始後の管理業務をスムーズに定着させることができます。
IT機器管理を効率化するツールの選び方
IT機器を多数管理する場合、専用ツール(IT資産管理ソフト)の活用が効率的です。市場にはさまざまな製品があるため、選定にあたって注目すべきポイントを押さえておきましょう。
機能の網羅性
まずは、導入目的に照らして必要な機能を網羅しているかを確認します。自社の課題やニーズを洗い出し、必須機能のリストを作ったうえで、それらを備えた製品を候補にしましょう。例えば、ハードウェアの詳細情報収集やソフトウェアライセンス管理、操作ログの記録、リモート制御、インベントリ(資産一覧)の自動更新など、ツールによって得意とする機能は異なります。
自社にとって外せない機能が何かを明確にし、対象範囲の広いツールを選ぶことが重要です。逆に不要な機能が多すぎる製品は、かえって操作が複雑になる場合もあるため注意しましょう。
使いやすさ・操作性
ツールのユーザーインターフェース(UI)や操作性も重要な選定基準です。せっかく多機能でも、画面が複雑だったり設定が難しすぎると現場で使いこなせず宝の持ち腐れになりかねません。Excel風の台帳画面で直感的に操作できる製品もあり、ITに不慣れな担当者でも導入直後から扱いやすいメリットがあります。製品サイトのデモ画面やトライアル版などを活用し、自社の担当者がストレスなく操作できるかを確認しましょう。
また、日本語サポートの充実度やマニュアルの分かりやすさも、スムーズな定着に影響します。現場で日常的に使うツールだからこそ、「わかりやすく便利に使えるか」を見極めることが大切です。
自社規模・業務に合った柔軟性
会社の規模や運用形態にフィットする柔軟性もチェックしましょう。社員数数十名の中小企業から数万台の端末を抱える大企業まで、必要とする管理範囲は様々です。ツールによって対応可能な端末台数や拠点数、管理者権限の設定範囲などが異なるため、自社の将来的な拡大も見据えてスケーラビリティを備えた製品を選ぶことが重要です。例えば、複数拠点で利用する場合は一元管理できるか、マルチOS環境(Windows/macOS/Linuxやモバイル等)に対応しているかも確認します。
また、自社独自の運用ルールに合わせてカスタマイズ可能か、オンプレミス版とクラウド版の選択肢があるかなども柔軟性のポイントです。組織の変化や成長に追随できるツールであれば、長期的に安心して利用できます。
価格・コストパフォーマンス
導入・運用にかかるコストも無視できません。高機能な製品ほど価格も高くなる傾向があるため、必要十分な機能とのバランスを見極めます。例えば、基本機能に絞って低価格で提供されるツールや、必要な機能をオプションで追加購入できる製品もあります。社内のIT予算に合わせて、初期導入費用だけでなく年間の保守費用やライセンス更新料などトータルコストを算出しましょう。
また、オープンソースの無料ツールという選択肢もあります(後述の「Snipe-IT」など)。ただし無料の場合でも自社でサーバーを用意し運用する手間はかかるため、人件費や運用負荷も含めたコストパフォーマンスで判断することが重要です。
セキュリティと外部連携性
IT機器管理ツールは社内の機密データにもアクセスするため、セキュリティ対策が万全なものを選びましょう。具体的には、クライアントPCのOSやソフトのパッチ適用を遠隔で実行できる機能や、ウイルス感染端末を自動隔離する機能などがあれば脆弱性対策に有効です。
また既存の他システムやセキュリティツールとの外部連携も重視しましょう。例えばウイルス対策ソフトやファイアウォール、MDM(モバイルデバイス管理)サービス、人事・勤怠システムなどとデータ連携できれば、より高度で統合的な運用が可能です。クラウド型の場合はサービス提供会社側のセキュリティ認証(ISO27001取得など)もチェックポイントです。自社のセキュリティ基準を満たしつつ、他ツールと連携して効率を最大化できるIT資産管理ツールを選定しましょう。
IT資産管理ツールおすすめ10選を比較
ここからは、IT機器管理・IT資産管理を効率化するおすすめツール10種を紹介します。オンプレミス型からクラウドサービス型まで、国内外の代表的なソフトウェアをピックアップしました。それぞれ特徴や強みが異なるため、自社のニーズに合わせて比較検討してください。
ツール名 |
提供形態 |
対応 OS / デバイス |
主な特徴 |
想定規模 |
価格帯・ライセンスモデル |
|---|---|---|---|---|---|
SKYSEA Client View |
オンプレ & クラウド |
Windows /(一部)Mac, 周辺機器 |
資産情報自動収集、操作ログ監視、USB制御まで統合 |
中〜大規模 |
初期買取+保守 (要問い合わせ) |
System Support best1〈SS1〉 |
オンプレ中心(クラウド版あり) |
Windows /Mac |
Excel風UI、機能を選んで導入できるモジュール課金 |
小〜中規模 |
永続ライセンス+年次保守 |
LanScope Cat |
オンプレ & クラウド |
Windows・Mac・モバイル |
IT資産管理と内部不正/脅威対策を一体提供 |
中〜大規模 |
要問い合わせ |
AssetView |
オンプレ & クラウド |
Windows・Mac |
IT資産+ログ+セキュリティを網羅する統合型 |
中〜大規模 |
要問い合わせ |
ManageEngine Endpoint Central |
オンプレ & SaaS |
Windows・Mac・Linux・iOS/Android |
UEM型:パッチ配布、リモート操作、MDM機能を標準装備 |
小〜大規模 |
年額/月額サブスク(低価格帯) |
Jamf Pro |
クラウド & オンプレ |
macOS・iOS/iPadOS・tvOS |
Appleデバイス専用MDM、ゼロタッチキッティング対応 |
Apple比率が高い組織 |
デバイス/月課金 |
Lansweeper |
オンプレ & SaaS |
主要 OS, ネットワーク機器 |
エージェントレス資産スキャン、脆弱性可視化 |
小〜大規模 |
デバイス単位課金/無料枠あり |
Microsoft Intune |
100% SaaS |
Windows・Mac・iOS/Android |
Azure AD 連携、MAM/BYOD 対応、クラウドネイティブ |
あらゆる規模 |
ユーザー/月課金 |
ServiceNow IT Asset Management |
100% SaaS |
OS問わず(CMDB連携) |
ITSMと一体の資産ライフサイクル管理、ワークフロー自動化 |
大企業・グローバル |
ローバルサブスクリプション(高価格帯) |
Snipe-IT |
オープンソース(自己ホスト) & SaaS |
Webブラウザ利用で OS 不問 |
無料 OSS、チェックイン/アウト管理・REST API |
小〜中規模 |
OSS版無料/SaaSは資産数課金 |
IT機器管理ツール導入の手順
IT機器管理ツールを選定したら、次は実際の導入プロジェクトを進めます。以下のステップに沿って導入を進めれば、スムーズに本番運用へ移行できるでしょう。
現状分析とゴール設定
まず、現在のIT機器管理状況を詳しく洗い出し、解決すべき課題や達成したい目標を明確にします。例えば「台帳が属人的で情報が散在している」「紛失端末の把握ができていない」「ソフトウェアライセンス数を適正化したい」等、現状の問題点を整理しましょう。
併せて経営層や関係部門から要求事項をヒアリングし、導入の目的とゴールを設定します。セキュリティ強化や業務効率化、コスト削減など、優先順位の高い目標を決めておくことで、後のステップで方針がブレにくくなります。現状分析と目標設定は、以降の要件定義や効果測定の指標にもなる重要なプロセスです。
要件定義とツール選定
次に、導入するツールに求める要件定義を行います。前ステップで洗い出した課題や目標を踏まえ、必要となる機能や対応範囲を具体化していきます。「WindowsとMac両対応」「クラウドサービスとも連携可能」「100台規模で利用」「操作ログを◯年間保存」など、機能要件・非機能要件を書き出しましょう。
要件が固まったら、市場の製品を調査して候補を数点に絞り込みます。各ツールの機能一覧や価格を比較し、自社の要件にマッチするものを選定します。可能であれば無料トライアル版やデモを取り寄せ、実際の使用感を評価すると安心です。関係者を交えて評価基準を設け、公平に比較検討して最適なツールを決定します。
パイロット検証とデータ整備
選定したツールについて、いきなり全社展開するのではなく、まずは小規模でパイロット導入(試験運用)を行います。例えば特定の部署や一部端末のみでテスト的に使ってみて、不具合や運用上の問題がないか確認します。
並行して、実運用に向けて既存データの整備も進めます。現行の資産台帳情報(Excel等)をツールに取り込む準備をしたり、不足している項目(購入日の記録など)があれば追加取得します。ラベル発行し直しが必要な場合はこの段階で実施します。
また、運用フローに関する社内ルール文書やマニュアルのドラフトも作成し、関係者の意見を募ってブラッシュアップします。パイロット検証を通じて得られた改善点を反映し、本番環境への切替えに備えます。
本番環境構築・運用開始
パイロットで問題がなければ、いよいよ全社向けの本番環境を構築します。クラウドサービスであれば本番テナントを正式契約し、オンプレミス型であればサーバーを用意してソフトウェアをインストールします。資産データを一括インポートし、社員や端末ごとの初期設定を行います。Active Directoryなど社内認証基盤と連携する場合はその設定も実施します。全端末へのエージェント配布や、スマホ管理用プロファイルの配信なども漏れなく行いましょう。
準備が整ったら関係部門へ周知し、運用開始です。初期段階では何らかの不明点やトラブルが起こりがちなので、専用の問い合わせ窓口を設けて迅速に対応できる体制を敷きます。徐々に利用者が慣れてきたら、通常運用へ移行していきます。
運用定着と効果改善
導入後は、ツールを使いこなせる状態を定着させることが大切です。情報システム部門内で担当者が代わってもスムーズに引き継げるよう、運用マニュアルや手順書を整備しておきます。定期的に操作研修を実施し、「誰が使っても同じ結果が得られる」ようにすることで属人化を防ぎます。
また、IT機器管理は情シス部門だけで完結せず他部署との協力も不可欠です。総務や人事からの人員情報提供、各部署での棚卸し協力など部門横断的な運用体制を築きましょう。運用が定着した後は、導入目的に対する効果測定と改善も続けます。例えば「棚卸し時間が◯%短縮」「紛失事故がゼロになった」といった成果を定期レポートし、さらに自動化できる作業はないか検討します。ツールと運用をPDCAで改善し続けることで、IT機器管理は初めて真価を発揮します。
自社に合ったIT機器管理を導入し、効率と安心を両立しよう
IT機器管理の基本から具体策、ツール導入のポイントまで解説してきました。ポイントは、自社の規模や課題に合った方法・ツールを選び、無理なく運用に乗せることです。適切なIT機器管理の実践によって、情報漏えいリスクの低減やコスト削減など「安心」と「効率」の両立が可能になります。
ぜひこの機会に自社のIT機器管理の現状を見直し、最適な管理体制の構築に取り組んでみてはいかがでしょうか。健全なIT機器管理は、企業の成長と信頼性を支える重要な土台となるでしょう。