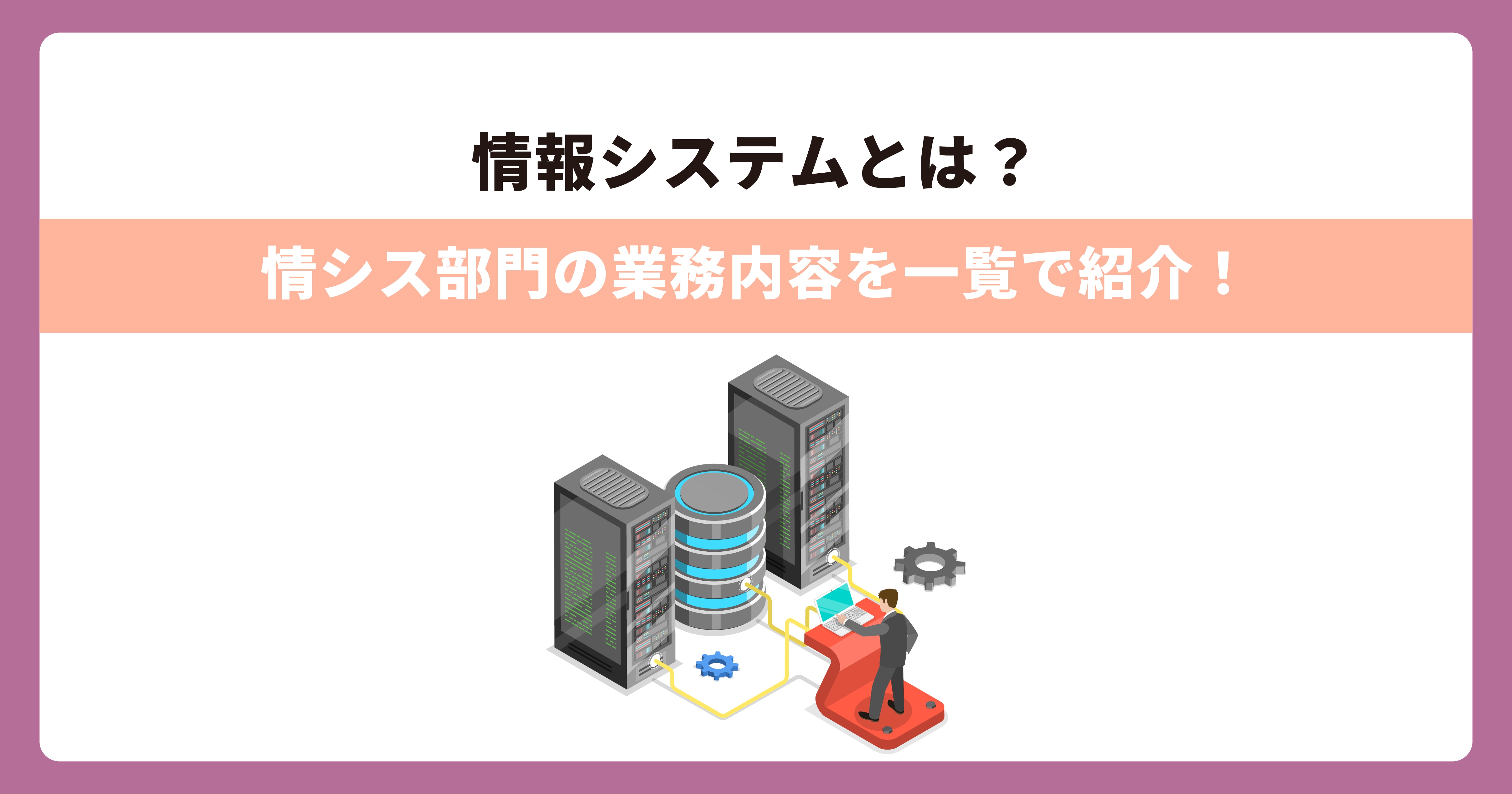
情報システムとは?種類や導入手順に加えて、情シス部門の業務内容を一覧で紹介!
社内のIT環境を整えたいと思った際、まず検討するのが「情報システム」です。しかし、いざ導入しようとすると「どんな種類があるの?」「情シス部門って何をしてるの?」「導入手順がよく分からない…」といった疑問に直面する方も多いのではないでしょうか。特に中小企業では、情シス担当者が一人しかいないケースや兼任担当者が多く、全体像をつかみにくいのが実情です。
そこで本記事では、情報システムの基本的な考え方から、基幹系・情報系の種類、情シスの役割、導入プロセスや注意点までをわかりやすく解説します。業務効率化やDXを進めたいと考えている方は、きっと参考になるはずです。
目次[非表示]
- 1.情報システムとは?
- 2.情報システムの種類
- 3.情報システム部門の役割と業務
- 3.1.情報システム部門の役割
- 3.2.情報システム部門の業務一覧
- 4.情報システム導入によるメリット
- 4.1.業務効率化と生産性の向上
- 4.2.コストの削減
- 4.3.データ活用による意思決定の迅速化
- 4.4.リスク管理とセキュリティ強化・コンプライアンス対応
- 5.情報システムの導入手順
- 5.1.STEP1:現状分析
- 5.2.STEP2:要件定義
- 5.3.STEP3:ベンダー選定
- 5.4.STEP4:システムの基本設計・要件定義
- 5.5.STEP5:システムの開発・導入
- 5.6.STEP6:システムの運用保守・効果測定
- 6.情報システム導入の際の注意点
- 6.1.事前に現状分析と要件定義を徹底する
- 6.2.費用対効果の検証
- 6.3.導入後の管理体制を整え、定着化を進める
- 7.情報システム導入で業務効率化と生産性向上を実現しよう
情報システムとは?
情報システムとは、情報を記録・処理・伝達するための仕組みのことです。現代ではコンピューターやソフトウェア、ネットワークなどを組み合わせて構築された企業のITシステムを指す場合が多く、業務で発生する膨大なデータを効率よく扱うために欠かせない存在です。
情報システムを導入することで、手作業では困難な大量情報の高速処理や社内外との迅速な情報共有が可能となり、企業活動の生産性向上に大きく寄与します。例えば、社員が日々利用するパソコンやスマートフォン、それらをつなぐ社内ネットワーク、その上で動作する業務アプリケーションやデータベースといった要素を総合したものが企業の「情報システム」といえます。なお、企業で情報システムの導入・運用を担当する部署は「情報システム部門」と呼ばれ、俗に「情シス」と略されます。
情報システムの種類
企業で利用される情報システムは、その役割に応じて大きく「基幹系システム」と「情報系システム」の2種類に分類できます。基幹系はビジネスの根幹そのものを担うシステム、情報系は業務を間接的に支援するシステムであり、両者は導入目的や重要度が異なります。
基幹系システム
基幹系システムは、企業の基幹業務(販売・在庫・生産・会計・人事など)と直接関わる重要なシステム群です。販売管理システムや生産管理システム、人事給与システム、財務会計システムなど、業種に応じて様々なものが含まれます。
基幹系システムを導入することで、業務の効率化やヒューマンエラーの削減、一元管理による重複作業の解消など、得られるメリットも豊富です。一方で、基幹系システムが止まると企業の業務自体が滞ってしまうため、他のシステム以上に高い安定性・セキュリティが求められます。
情報系システム
情報系システムは、企業経営の根幹には直接関与しないものの、各部門の業務効率化や情報共有の円滑化に資するシステム全般を指します。これらのシステムは、基幹系に比べて重要度が相対的に低く、導入・運用コストも抑えられる傾向があります。
情報系システムの具体例としては、メールやグループウェア、ビジネスチャット、Web会議システムといった社内コミュニケーションツール、あるいは営業やマーケティング部門向けのCRM(顧客管理)やSFA(営業支援)、BI(経営分析)ツールなどが挙げられます。
このような情報系システムを活用することで、社内情報の円滑な共有や意思決定の迅速化が図られ、ビジネス全体のスピードアップに貢献します。基幹系システムで処理したデータを情報系システムで分析・共有するなど、両者を組み合わせることで業務全体の最適化が可能になります。
情報システム部門の役割と業務
情報システム部門(情シス)は、企業内のIT基盤(ネットワーク、ITデバイス、業務システムなど)を構築・運用・管理する部署です。社内で使用するネットワークやPC・サーバ、基幹システムや業務システムの開発・保守、セキュリティ対策、ヘルプデスク対応など幅広い業務を担い、IT面から全社の業務を支援します。
また、IT戦略の立案と実行を通じて業務効率化や生産性向上、コスト削減など経営課題の解決に貢献する重要な役割を果たしています。近年では、クラウド活用やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に伴い、情シスには安定運用という「守り」の仕事だけでなく、新しいIT技術を活用した価値創出といった「攻め」の取り組みも求められるようになっています。
情報システム部門の役割
情シス部門の基本的な役割は、社内IT環境を整備・維持し、従業員が安心して業務にITを活用できるよう支援することです。ネットワークやデバイスの管理運用、業務システムの保守運営、ユーザーサポートなどを通じて、社内のITインフラを安定稼働させるのが使命となります。さらに、経営戦略に沿ったIT計画の策定やDX推進など、企業競争力の強化に直結するIT戦略をリードする役割も担っています。
情報システム部門の業務一覧
では、情報システム部門が担当する主な業務内容を項目ごとに見ていきましょう。
・IT戦略の策定と実行
情シス部門は経営戦略に基づいてIT戦略を立案し、必要なシステムの企画立案や要件定義を行います。社外のITベンダーから見積もりを取得して比較検討し、適切なパートナーを選定した上でプロジェクトの推進管理を実施し、ユーザー部門に対して新しいシステムを導入・提供します。また、クラウドやAI、IoTなど最新技術の導入による業務改革(DX)の推進もIT戦略の一環として情シスが担います。
・社内システムの導入・運用・保守
情シス部門の主要業務の一つが社内システムの導入・構築です。しかし、システムは導入して終わりではなく、安定運用と保守を継続していくことも大きな役割となります。システム稼働後は日々の監視や定期メンテナンスを行い、障害発生時には迅速に対応します。
また、ユーザーからの要望や業務プロセス変更に応じて既存システムの機能改善・カスタマイズを実施し、使いやすさの向上に努めます。特に基幹系システムの場合、トラブルが業務に直結するため、24時間365日の監視体制が敷かれることもあります。
・セキュリティ対策の実施
社内の情報セキュリティ対策を講じるのも情シス部門の重要な任務です。ネットワーク環境の安全性確保やウイルス対策ソフトの導入、ファイアウォール等のセキュリティ機器の管理運用、社員のアクセス権限設定やパスワード管理など、インフラ面で多層的な防御策を整備します。
さらに、機密データの暗号化や定期的なバックアップの実施、セキュリティポリシーの策定と社員教育を通じて、サイバー攻撃や内部不正による情報漏えいリスクを低減させます。昨今はランサムウェアなど高度化するサイバー攻撃の脅威が高まっており、情シスによるセキュリティ強化は企業継続の観点からますます重要になっています。
・ITデバイスの管理・運用
PCやプリンター、スマートフォンなど社内のあらゆるITデバイス(IT資産)の管理も情シス部門の仕事です。IT機器の購入・キッティング(初期設定)から社内各部署への配布、利用状況の把握、ソフトウェアの更新・ライセンス管理、故障時の修理対応、さらには老朽化したデバイスの廃棄・更新まで、IT機器のライフサイクル全体を一元管理し、最適な運用体制を維持します。
近年はテレワークの拡大により、社外に持ち出すノートPCやスマートフォンの遠隔管理(MDMツールの活用など)も情シスの重要な課題となっています。
・ヘルプデスク業務・問い合わせ対応
従業員からのIT関連の問い合わせやトラブルに対応するヘルプデスク業務も、情シス部門の重要な役割です。社員が日常業務で直面するPCやソフトウェアの不調、操作方法の不明点などに対し、迅速かつ丁寧に対応し、業務が滞らないようサポートします。
この業務は単なる「問い合わせ対応」にとどまらず、社員がITを活用して効率的に働ける環境を裏方から支えるものです。例えば、パスワードのリセット依頼への対応や業務システムの操作説明、よくある質問のFAQ整備など、社内の「困った」に幅広く応じて現場を支えます。必要に応じてベンダーへのエスカレーションを行い、大きなトラブルにも適切に対処します。
参考記事:企業のIT環境を支える情シスの仕事内容とは?現在の業務を見直して効率化を実現
情報システム導入によるメリット
情報システムを導入すると、企業の業務に様々な良い変化がもたらされます。ここでは主なメリットを4つ紹介します。
業務効率化と生産性の向上
情報システム導入の最大のメリットは、業務の効率化と生産性向上にあります。日常業務をシステム化・自動化することで、それまで人手で時間をかけていた処理を大幅に短縮でき、限られた人員でも多くの仕事をこなせるようになります。
また、情報を一元管理して「見える化」することで重複作業やムダを減らし、作業ミス(ヒューマンエラー)の削減や業務プロセスの標準化による品質向上にもつながります。こうした効率化により、生産性が高まり組織全体の業績向上が期待できます。
さらに、部門間でデータを共有することで部署の垣根を越えた協力体制が築きやすくなり、組織横断的な業務推進も円滑になります。
コストの削減
情報システムの活用はコスト削減にも寄与します。業務の自動化により、これまで人力に頼っていた作業を効率化して、人件費や残業代の削減につなげられます。システム導入によって不要な紙資料や在庫の削減、業務プロセス短縮による電力消費の低減など、副次的なコスト圧縮効果も得られるでしょう。
さらに、リアルタイムでデータを集約・分析してリソースを最適配分することで、無駄な在庫や設備投資を減らし、長期的なコスト最適化を図ることが可能です。例えば、在庫管理システムにより適正在庫を維持することで過剰在庫による資金圧迫を避け、不要な保管コストを削減できます。
データ活用による意思決定の迅速化
情報システムを導入すると、業務で発生するデータが蓄積・活用しやすくなり、経営の意思決定スピードが向上します。蓄積データをリアルタイムに分析すれば、過去の傾向や市場の変化を素早く把握できるため、経験や勘に頼らない根拠ある判断が可能です。
データに基づく意思決定は主観的な判断に比べてリスクが低く、より効果的な戦略立案につながります。さらに、データ分析により業務上の課題を早期に発見し改善策を講じることが容易となるため、継続的な業務改善サイクル(PDCA)のスピードアップにも寄与します。
リスク管理とセキュリティ強化・コンプライアンス対応
情報システムの導入は、リスクマネジメントやコンプライアンス強化の面でもメリットがあります。業務をシステム化することで、属人的な作業に伴うミスや情報漏えいのリスクを低減でき、データのバックアップや冗長化により災害時にも重要情報を保護し事業を継続しやすくなります。
アクセス権限の設定や操作ログの記録により、内部統制を効かせやすくなり、監査対応や法令遵守もスムーズに行えます。例えば、情報セキュリティ対策や事業継続計画(BCP)を適切に講じておけば、不測のサイバー攻撃やシステム障害が発生した場合でも被害を最小限に抑えることが可能です。
このように、情報システムは企業に安心と信頼をもたらし、リスクに強い経営基盤の構築に貢献します。
情報システムの導入手順
ここでは、情報システムを自社に導入する際の一般的な手順を6つのステップで紹介します。
STEP1:現状分析
まずは現状の業務プロセスを可視化し、問題点や非効率な箇所を洗い出します。各部署の担当者からヒアリングを行い、業務フロー上のボトルネックや重複作業などを明確にしましょう。
「なぜ社内システムを導入するのか」「導入してどの課題を解決したいのか」という目的を定め、定量的な目標(例:「作業時間を○%短縮」など)を設定しておくことも重要です。
STEP2:要件定義
次に、導入するシステムに求める具体的な要件を定義します。現場の業務要件を掘り下げ、「どの業務をどのようにシステム化したいか」を明確にしましょう。その上で、業務要件を実現するために必要なシステム機能や性能を洗い出し、機能一覧や処理フロー図などに整理します。
この要件定義フェーズで認識齟齬が残っていると後工程での手戻りリスクが高まるため、ユーザー部門と合意形成しながら慎重に詰めていきます。
STEP3:ベンダー選定
定義した要件を実現できるシステムの提供ベンダーを選定します。複数の候補ベンダーにRFP(提案依頼書)を提示して提案を募り、それぞれの提案内容や見積もりを評価・比較検討します。
機能要件への適合度、導入コスト、導入実績、サポート体制などを総合的に判断し、自社に最も適したベンダーと契約を結びます。導入後の定着支援までサポートしてくれるベンダーを選ぶと、スムーズな運用につながるでしょう。
STEP4:システムの基本設計・要件定義
次の段階では、システムの設計作業に入ります。選定したベンダーと協力し、システム全体の基本設計を行って仕様を確定させます。
パッケージソフトを導入する場合は、自社の要件とのギャップを洗い出し、必要に応じて追加開発する機能の設計を実施します。カスタマイズや新規開発がある場合は、設計書を作成してベンダーと内容を詰め、利用者目線での使い勝手も考慮しながら詳細な設計を固めます。
STEP5:システムの開発・導入
設計に基づいて、システムの開発および設定作業を行います。プログラムの実装やシステム設定が完了したら、テスト環境で十分な検証を実施し、問題がなければ本番環境へリリースします。既存システムから新システムへのデータ移行が必要な場合は、データ整備と移行作業を慎重に行います。
また、現場の従業員に対する操作研修を実施し、新システムの運用ルールを周知徹底します。こうした準備を経て、新しい情報システムが本番稼働を開始します。
STEP6:システムの運用保守・効果測定
システム導入後は、安定した運用と継続的な保守対応が欠かせません。専任のシステム管理者を中心に日々システムの状態を監視し、障害が発生した際には迅速に復旧対応できる体制を整えます。定期的にソフトウェアのアップデートやセキュリティパッチの適用、データバックアップなどの保守作業も実施します。
さらに、導入前に設定したKPI(重要業績評価指標)に基づき、新システム導入による効果を測定・分析することも重要です。計画通りの業務効率化やコスト削減効果が出ているかを評価し、もしギャップがある場合は、原因を究明して運用方法の見直しや機能追加改善などの施策を講じます。これにより、情報システム導入の成果を最大化し、継続的な業務改善サイクルにつなげていきます。
情報システム導入の際の注意点
最後に、情報システムを導入するにあたって注意すべきポイントを確認しておきましょう。
事前に現状分析と要件定義を徹底する
情報システム導入プロジェクトで陥りがちな失敗パターンの一つに、「目的や要件が曖昧なまま導入を進めてしまう」というケースがあります。これを防ぐため、導入前の段階で現状業務の課題を徹底的に分析し、「何のためにシステムを導入するのか」「導入によって何を解決・実現したいのか」を明確に定義しておく必要があります。
各部門と十分にコミュニケーションを取り、要件定義書に合意を得た上でプロジェクトを開始しましょう。準備段階に手間を惜しまず、万全の計画を立てることがシステム導入成功の鍵となります。
費用対効果の検証
情報システムの導入には多大なコスト(初期導入費用および継続的な運用費用)が伴います。その投資に見合うリターンが得られるか、事前に費用対効果をしっかり検証することが重要です。ソフトウェアやハードウェアの購入費用、開発・カスタマイズ費、保守運用費などを総合的に算出し、業務効率化による人件費削減額や業績向上への寄与など、期待される効果と比較検討します。
近年は、クラウドサービスの活用によって初期投資を抑える企業も増えています。クラウドは月額費用がかかる一方で、自社サーバを保守・管理する手間や設備投資が不要になる利点があります。
長期的な視点でコストと効果のバランスを見極めましょう。また、導入に必要な期間についても現実的な見積もりを行うことが大切です。計画が楽観的すぎるとスケジュール遅延を招き、追加コストの発生につながりかねません。
導入後の管理体制を整え、定着化を進める
システムは導入して終わりではなく、実際に現場で使いこなされて初めて価値を発揮します。そのため、導入後の運用・管理体制をしっかり整備し、新システムを社内に定着させることが非常に大切です。
例えば、専任のシステム管理者を配置して日常のシステム監視や障害対応、アップデート管理などを継続的に実施できるようにします。また、社員向けの操作トレーニングを実施したり、充実したヘルプデスク体制を用意して利用者の不安や疑問を迅速に解消したりすることで、現場へのスムーズな浸透を図ります。
社内の理解不足やサポート不足が原因で「導入したのに現場で使われない」という事態を避けるため、導入後も継続的にフォローアップを行いましょう。
情報システム導入で業務効率化と生産性向上を実現しよう
適切な情報システムを導入し活用することで、業務効率化や生産性向上、さらにはコスト削減やリスク低減など、企業活動に多くのメリットをもたらすことができます。導入手順に沿って計画的にプロジェクトを進めれば、中小企業であってもDX時代にふさわしいスピーディな業務改革が可能です。
情シス部門の知見や外部パートナーの力も借りながら、自社に最適な情報システム導入を成功させ、競争力強化と持続的な成長につなげていきましょう。そして、情報システムを積極的に活用することで、時代の変化に柔軟に対応できる強い組織を作り上げましょう。




