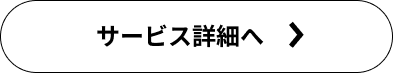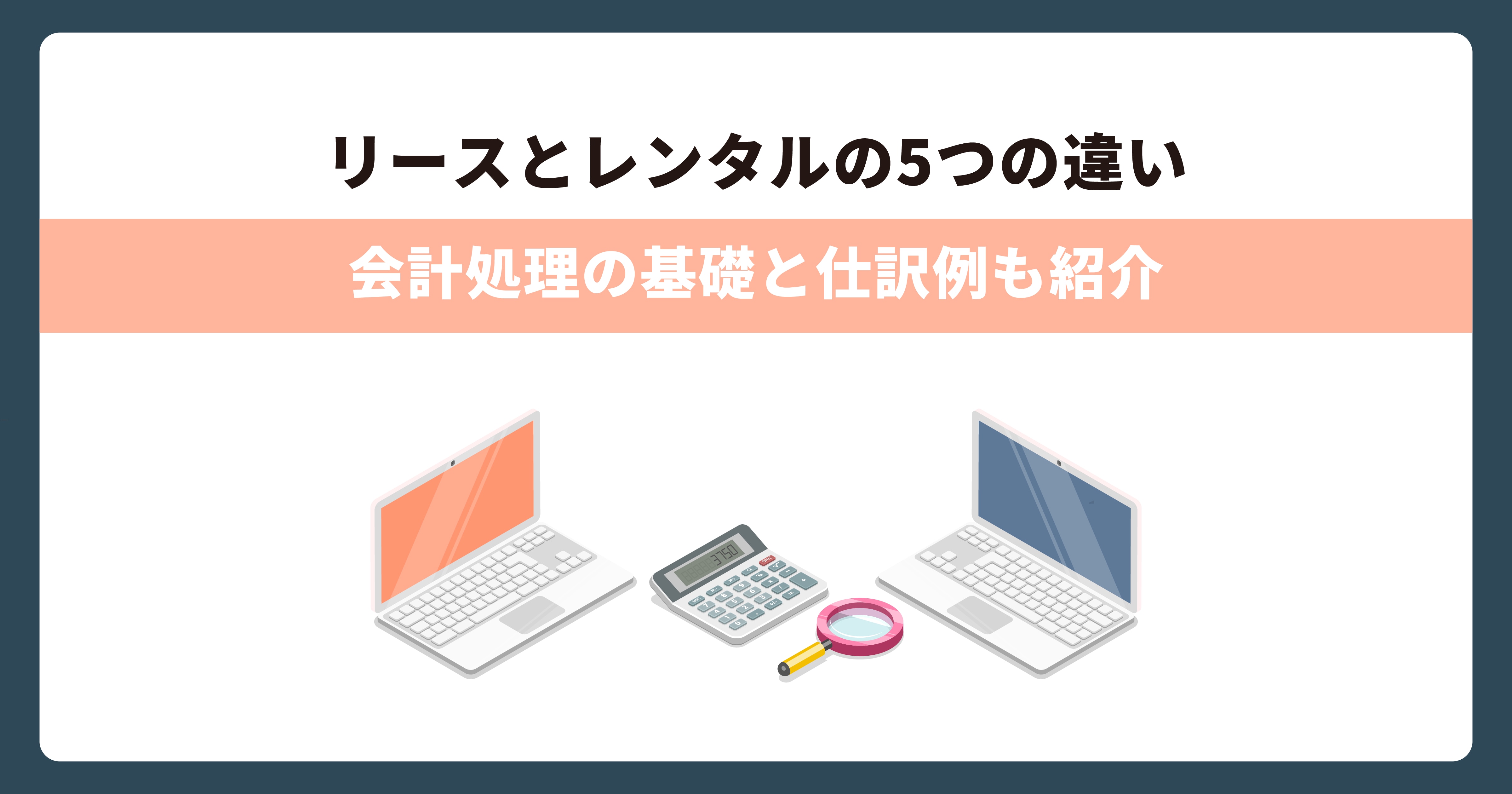
リースとレンタルの5つの違いを経理向けにやさしく解説|会計処理の基礎と仕訳例も紹介
自社の設備や機器を「買う」のではなく、リースやレンタルで調達する方法があります。それぞれ似た仕組みに見えますが、契約期間や費用負担、会計処理などに明確な違いがあります。
本記事では、中小企業の経理担当者に向けてリースとレンタルの5つの違いをやさしく解説し、仕訳の具体例や2027年の新リース会計基準への対応ポイントも紹介します。自社に合った調達方法を選ぶ参考にしてください。
目次[非表示]
- 1.リースとレンタルの5つの違い
- 1.1.長期契約と短期契約
- 1.2.自己保守と業者保守
- 1.3.解約不可と解約自由
- 1.4.割安長期型と高額短期型
- 1.5.資産計上と経費処理
- 2.リースとレンタルの仕訳例
- 2.1.リース会計:所有権移転ありの仕訳
- 2.2.リース会計:所有権移転なし・少額例外の仕訳
- 2.3.レンタル会計:賃借料処理の仕訳
- 3.新リースの会計基準(2027年)変更点と企業への影響
- 4.リースとレンタルの選び方
- 4.1.コストと会計処理で選ぶ
- 4.2.活用シーンで選ぶ
- 4.3.契約前のフローで選ぶ
- 5.リースとレンタルの理解が経営判断を変える
- 6.MacのリースもUTORITOにおまかせ!
リースとレンタルの5つの違い
リースとレンタルには以下の5つの違いがあります。
リース |
レンタル |
|
|---|---|---|
契約期間 |
長期(2~5年程度) |
短期(数日~1年以内) |
保守・修理 |
利用者が負担(自己保守) |
業者が対応(料金に含まれる場合多い) |
途中解約 |
原則不可(違約金・残額支払あり) |
自由に解約可(不要になれば返却) |
コスト |
長期利用で割安 |
短期向けで柔軟だが割高 |
会計処理 |
資産計上(減価償却・オンバランス) |
経費処理(オフバランス) |
以上のポイントについて、以下で詳しく解説します。
長期契約と短期契約
リース契約は比較的長期間の利用を前提とした契約形態です。
一般的に契約期間は2~5年程度の中長期となり、契約期間中は同じ物件を継続して使用します。契約満了時にはリース物件を返却するか、必要に応じて新たなリース契約を結んで継続利用することもできます。
一方、レンタル契約は短期間の一時的な利用を目的とした契約形態です。
契約期間は数日から数ヶ月、長くても1年以内程度が一般的で、必要な期間だけ機器を借りて使い終われば返却します。レンタルはリースに比べ契約期間の柔軟性が高く、短期のプロジェクトやスポット的な利用に向いています。
自己保守と業者保守
リース契約では、機器の保守・修理は借り手の責任となる場合が多い点に注意が必要です。
リース会社は機器の所有権を持ちますが、実質的な管理責任は利用企業側にあり、故障時の修理費用やメンテナンス費用は利用者(借り手)が負担するケースが一般的です。契約時に保守サービスを付加できる場合もありますが、その分リース料に上乗せされます。
一方、レンタル契約では保守・修理はレンタル業者が対応するのが通常です。
レンタル料金に基本的な保守サービスが含まれていることが多く、使用中に不具合が生じた場合はレンタル会社が修理・交換対応を行ってくれるため、利用者は保守費用を心配せずに済みます。
解約不可と解約自由
リース契約期間中は原則として中途解約ができない点にも注意しましょう。
リースはリース会社が利用者に代わって物件を購入し、その代金相当額をリース料で回収する金融取引の性質があるため、契約期間途中での解約は基本的に認められません。やむを得ず解約する場合でも、残存リース料の一括支払いなど高額の違約金が発生します。
一方でレンタル契約は途中解約が比較的自由にできます。
レンタルはレンタル会社所有の物件を一時的に借りるだけの形態のため、利用者の都合で契約期間を短縮して返却しても大きな問題にはなりません(※ただし契約内容によっては最低利用期間や解約手数料が定められている場合もあります)。このように、契約期間の柔軟性はレンタルの大きな特徴です。
割安長期型と高額短期型
コスト面では、リースとレンタルで考え方が異なります。
リースは長期継続利用を前提としているため、月々の利用料(リース料)は購入代金を分割した程度の水準に抑えられることが多く、総支払額は物件の購入価格と同程度か少し上乗せされる程度です。長期の安定利用ではリースの方が経済的メリットが大きいでしょう。
一方、レンタルは短期間だけ手軽に利用できる利便性と引き換えに、料金設定は割高になる傾向があります。
例えば同じ機器を3年間使う場合でも、レンタルで都度延長するとリース契約より総額が高くなるケースが多いです。ただしレンタルは必要な期間だけ費用を支払えばよいため、極めて短期間の利用で済む場合には購入やリースより割安に抑えられる利点もあります。利用期間の長短に応じて、どちらが総コストで有利かを検討することが重要です。
資産計上と経費処理
リースとレンタルは会計処理方法にも違いがあります。
リース契約で調達した資産は、会計上自社の資産として計上し、対応する負債(リース債務)も計上します。そして固定資産と同様に減価償却費を計上する、いわゆるオンバランス処理となります。
一方、レンタル契約の場合、使用料はその都度経費(賃借料など)として処理し、借りている物件自体は資産計上しません。言い換えればオフバランス取引となり、貸借対照表に計上しないで済むため、会計処理が比較的簡便です。
このように、リースは利用資産が自社の貸借対照表に計上され財務指標に影響を及ぼす点、レンタルは賃貸借取引として費用計上のみで完結する点が大きな違いです。
参考記事:リースとレンタルの違いとは?
リースとレンタルの仕訳例
ここからは、リース取引とレンタル取引それぞれの具体的な仕訳例を見てみましょう。
リース取引は契約形態(所有権移転の有無)によって会計処理が異なり、また、一定の例外規定もあります。レンタル取引は賃借料として処理するシンプルな仕訳です。それぞれ経理処理の基本を解説します。
リース会計:所有権移転ありの仕訳
所有権移転ファイナンス・リース(リース期間終了後に物件の所有権が借り手に移る契約)の場合、会計上は「ローンで資産を購入した場合」と同様の処理を行います。契約開始時にリース資産とリース債務をそれぞれ計上し、以後の支払で元本と利息を区分して負債を減少させていきます。
例えば、資産価格60万円・総リース料72万円(60回払い)の契約では、契約時に借方:リース資産 600,000円 / 貸方:リース債務 600,000円と仕訳します。毎月の支払時にはリース料を元本相当額と利息相当額に分け、借方:リース債務 10,000円、支払利息 2,000円 / 貸方:現金 12,000円のように計上します。決算時にはリース資産について減価償却費を計上し、借方:減価償却費 / 貸方:減価償却累計額の仕訳を行います。
リース会計:所有権移転なし・少額例外の仕訳
所有権移転外ファイナンス・リース(リース期間終了時に物件を返却する契約)の場合も、基本的な仕訳フローは所有権移転ありの場合と同じです。契約時にリース資産・リース債務を計上し、支払の都度リース債務の返済と利息を計上します。ただし所有権が移転しないため、減価償却費の計算において耐用年数をリース期間とし、残存価額をゼロとして償却する点が異なります(リース期間定額法)。
また、例外規定として「リース期間が1年以内の短期リース」や「少額のリース取引」については、通常の賃貸借取引と同様の処理(オフバランス処理)が認められています。
例えば、リース料総額が300万円以下で重要性が乏しい少額リース取引などが該当します。その場合、契約時の資産計上は行わず、毎月の支払時に借方:リース料 / 貸方:現金と仕訳して経費処理することが可能です。この簡便処理を適用する際は、一旦適用した基準を継続して用いる必要がある点に注意してください。
レンタル会計:賃借料処理の仕訳
レンタル取引は会計上賃貸借取引とみなされるため、その仕訳はシンプルです。
物件を借りて利用した期間に対応して支払うレンタル料は、その都度「賃借料」勘定で費用計上します。契約時に資産や負債を計上する仕訳は発生せず、支払時に借方:賃借料 / 貸方:現金(預金)と処理するだけです。
例えば、月末に当月分のレンタル料5万円を支払った場合、借方:賃借料 50,000円 / 貸方:現金 50,000円という仕訳になります。リースのような減価償却や利息計上も不要で、経理処理の負担が軽い点がレンタル会計の特徴です。
新リースの会計基準(2027年)変更点と企業への影響
日本では2027年4月1日以後開始の事業年度から、新リース会計基準が適用される予定です。
これは国際会計基準(IFRS第16号)に準拠したもので、リース取引の会計処理に大きな変更が加わります。ここでは新基準の概要と変更点、短期・少額リースの例外規定、新基準に向け企業が準備すべき実務対応ポイントについて解説します。
リース会計の新基準の概要と変更点
新リース会計基準の最も大きな変更点は、借手(リース利用企業)の全てのリース取引を原則オンバランス処理することです。
従来の日本基準では、ファイナンス・リースは資産計上(ただし一部例外あり)、オペレーティング・リースは賃貸借処理(オフバランス)と区分されていました。
しかし、2027年適用の新基準では、リース期間や種類にかかわらず原則すべてのリース契約で「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上することが求められます。これは国際的な会計基準IFRS16号をベースとしており、リース債務を財務諸表上に計上することで企業の実質的な債務状況を投資家が正しく把握できるようにする狙いがあります。
この改正により、従来オフバランスだった契約を多数抱える企業では貸借対照表の総資産が大幅に増加すると見込まれています。実際、約1,400社以上で総資産が増加する試算もあり、特に店舗や設備をリース利用している小売業などでは資産・負債の膨張による自己資本比率の低下やROA(総資産利益率)の悪化が懸念されています。
このように新基準は財務指標へ影響を及ぼす可能性があるため、企業価値評価や金融機関の与信判断にも注意が必要です。
リース会計の例外処理(12ヶ月以下・少額)
新リース会計基準でも、短期・少額のリース取引に対する例外規定が設けられています。
具体的には、リース期間が12ヶ月以下の短期リースや、少額のリース資産(一般的な目安として新品価額が5千ドル以下程度)については、従来どおり賃借料として処理することが認められます。
この例外を適用する場合、使用権資産・リース負債を計上せず、リース料を発生時に経費処理できます。日本基準においても「1契約あたりリース料総額が300万円以下で事業の規模からみて重要性が乏しい場合」などに賃貸借処理を選択できる旨が示されており、新基準適用後も同様の金額基準が運用される見込みです。
したがって、少額のパソコンや事務機器をリースで調達しているケースや、期間の定めが短いレンタルに近い契約については、無理にオンバランス計上せず経費処理を継続できる余地があります。
ただし、これら例外規定を適用するかどうかは企業の任意選択となり、一度適用方針を決めたら継続的に同じ基準で処理する必要がある点に注意が必要です。
リース契約見直しに向けた実務対応のポイント
新基準の導入に備え、企業は早めにリース契約の見直しと対応準備に取り組むことが重要です。
まず、自社が現在締結している全てのリース契約や類似の取引を洗い出し、新基準適用時にオンバランス計上の対象となるものをリストアップしましょう。
特に見落としがちなのが「リースに該当する可能性のある取引」の洗い出しです。例えば業務委託先が特定の資産(設備等)を自社専用に使用している場合など、契約内容によっては形式上はサービス契約でも新基準上はリースと識別される可能性があります。こうした取引も含めて契約書類を精査し、対象範囲を網羅的に把握することが必要です。
次に、リース資産・負債のオンバランス計上に伴う財務影響の分析を行いましょう。
リース債務の算定には契約ごとに現在価値計算が必要になり、リース料支払予定表の管理や、契約条件(延長オプションや変動リース料)の把握も求められます。
また、リース取引に関する注記情報の開示拡大にも対応しなければなりません。これらを踏まえて、自社の経理処理プロセスを見直し、必要であれば管理システムの導入や業務フローの構築を検討します。多数のリース契約を抱える企業では、専用のリース管理ソフトウェアを用いて契約情報や仕訳計算を一元管理することが実務上現実的でしょう。システム導入には時間を要するため、適用開始までに十分な準備期間を確保することも大切です。
さらに、新基準適用後はリース契約の開始・変更時における会計処理が格段に煩雑になります。
経理担当者への教育・体制強化も欠かせません。従来オフバランスだった取引も含め仕訳数は従来の3~4倍に増えるとの指摘もあり、現在の人員で対応が難しければ専門知識を持つ人材の増強も検討すべきです。総じて、新リース基準への対応は経理・財務部門だけでなく契約管理やIT部門も巻き込んだ全社的なプロジェクトとなるため、早め早めの準備対応が求められます。
リースとレンタルの選び方
以上の違いを踏まえて、リースとレンタルのどちらを選ぶべきかを判断するポイントを整理します。
コストや会計処理への影響、利用シーンの適合性、契約手続きの手間など多角的に検討することが大切です。自社のニーズに照らして最適な調達方法を選びましょう。
コストと会計処理で選ぶ
コスト面と会計処理の観点からは、利用期間の長さと自社の財務状況を考慮します。
長期的に継続利用する設備であれば、月額料金が低めに設定されたリースの方が総コストを抑えられます。
一方、短期間だけ必要な物品であればレンタルで必要な期間だけ借りる方が無駄がなく、リース契約を結ぶより安く済む場合があります。
会計処理についても、オンバランスで資産計上するリースは将来的に負債が増えて見える点や減価償却費計上による利益への影響を考慮する必要があります。
反対にレンタルは都度経費処理できるため、支出したタイミングで即損金計上できるメリットがあります。例えば当期の利益を圧縮したい場合、レンタル料として一括経費処理できる方が都合がよいこともあります(リース資産だと耐用年数に渡り費用配分されます)。
また、資産計上を嫌いオフバランスでいたいという財務戦略上の意図がある場合はレンタルを選択する余地があります(ただし今後は新基準で重要なリースはオフバランスにできなくなる点に留意)。
このように、トータルコストと会計上の扱いを比較し、自社に有利な方法を選びます。
活用シーンで選ぶ
利用シーンに応じてもリースかレンタルかの適性が異なります。
短期のイベントや季節限定のプロジェクトなど一時的な需要には、柔軟に期間設定できるレンタルが適しています。例えば展示会のブース用機材を数日だけ使う場合や、新入社員研修のために一時的にPCを増設する場合、レンタルなら必要な期間だけ借りてすぐ返却でき経済的です。
一方、オフィスの複合機や生産設備のように継続的かつ常設で必要な機器は、リースで長期契約する方が安定して使えます。リース契約なら契約期間終了時に新しい機種への入れ替えを検討する機会も得られるため、最新設備への更新サイクルを計画的に回すことも可能です。
また、リースは利用者の希望する機種をリース会社が新規購入して貸与してくれるため、自社のニーズに合致した特定モデルやスペックの機器を導入しやすい利点があります。
レンタルの場合、レンタル会社が保有する在庫品(カタログから選ぶ形)に限定されるため、選択肢がやや狭まることがあります。自社が求める機能や仕様を満たす機器がレンタルで見つからない場合は、リースを検討するとよいでしょう。
反対に、試験的に機器を使ってみたい場合や、使用頻度が低く保管場所の問題もある場合は、必要な時だけ借りるレンタルの方が適した選択肢になります。
契約前のフローで選ぶ
リースとレンタルでは契約手続きの流れにも違いがあります。
リース契約は金融取引の側面があるため、契約時にリース会社による与信審査や社内稟議など手続きに時間と手間がかかりやすいです。実際の契約書もリース期間・月額料金、保守条件など詳細な取り決めが盛り込まれ、契約締結までに打ち合わせや書類準備が必要となります。
一方、レンタル契約は比較的簡易で、レンタル会社が提示する利用規約に沿って必要事項を確認し合意すれば短時間で契約成立します。レンタルは利用希望者に対する審査も簡便なケースが多く、個人でもネットから申し込んですぐ借りられるサービスもあります。企業向けでも、レンタル会社との間で基本契約を結んでおけば、追加の機器を借りる手続きは迅速に行えます。
したがって、機器が急に必要になった場合や、煩雑な手続きを避けたい場合はレンタルが適しています。逆にリース契約を結ぶ場合は事前に余裕をもって社内外の手続きを進め、契約開始に合わせて機器が納品されるよう計画することが大切です。
リースとレンタルの理解が経営判断を変える
リースとレンタルの違いを正しく理解することは、企業の設備投資やコスト管理において重要な意味を持ちます。それぞれのメリット・デメリットを踏まえて適切な手法を選択すれば、資金繰りの改善や税務上のメリットを享受でき、無駄な支出を抑えることができます。
特に中小企業では限られた予算の中で設備を整える必要があるため、調達手段の選択一つで経営効率に大きな差が生まれます。昨今ではサブスクリプション型のサービスやクラウド利用など、新たな選択肢も登場していますが、根底にある「自社で資産を持たずに利用する」という点でリースとレンタルの原則は変わりません。
ぜひ本記事の内容を参考に、自社の用途や期間、予算を考慮して最適な調達方法を選択してください。リースとレンタルを使い分けるスキルは経理・財務担当者の重要な引き出しとなり、経営判断の質を高めることでしょう。
MacのリースもUTORITOにおまかせ!

株式会社Tooでは、Macの調達からキッティング、運用、返却まで任せられるアウトソーシングサービス「UTORITO」を提供しています。
UTORITO の特徴の一つである Apple Financial Services (AFS)という残価設定型のオペレーティングリースを活用することで、トータルコストを抑えて最新のMacを手軽にリースすることができます。
また、Apple Financial Services (AFS)を活用し、デバイスの使用期間を予め決めておくことで、デバイスの管理・運用まで、LCM(ライフサイクルマネジメント)を円滑にサポートできることもUTORITOの強みの一つです。
さらに、UTORITOには保守・修理費が含まれているため、基本的に追加費用は発生しません。
参考記事:ライフサイクルマネジメント(LCM)サービスとは?企業のIT機器運用管理をサポート
リースのデメリットをカバーしながら最新のMacを導入、運用する際は、ぜひ株式会社Tooの提供しているUTORITOをご検討ください。 Macのリースを活用して、貴社のIT環境をぜひ次のレベルへ引き上げましょう。